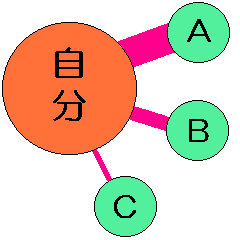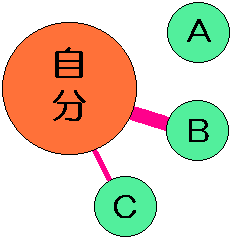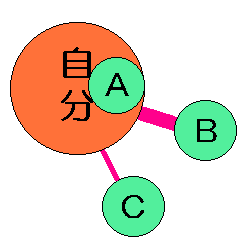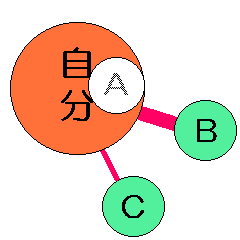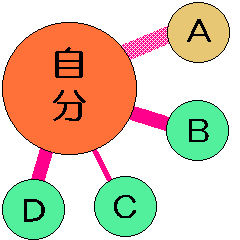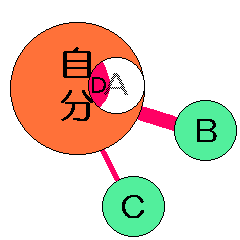《ペットロス》
以前の私は、愛鳥に先立たれて悲しみの状況にある方からメールを頂くと、非常に困惑しました。私自身はペットの死(ペットロス)に際して「悲しいのは自分なので、放っておいてもらいたい」と思うタイプであり、結局自分の文鳥を失った悲しみは、他人にわかるわけがないと信じて疑わないので、メールされた方を慰めて良いものか、まず悩んでしまったのです。礼儀上慰めの言葉を探すとして、例えば「星になった」と言えるほど詩才の持ち合わせはなく、「生まれ変わる」とほとんど信じてもいない事も言えず(私自身は「その気があれば、生まれ変わってきてくれ」と逝った者に語りかけることはある)、「あなたや私を含めて、死なない生き物なんてない」と禅僧並みに説破するのは、相手の現在の心情を思えばはばかられます。その宗教観も価値観も私にはわからない悲しみに沈む人に対して、どのように返事をしたら良いのか考えはじめると、途方に暮れてしまうっていたのです。
しかし、最近は深く考えなくなりました。悲しい時は悲しいわけで、ただひたすら泣こうと、じっと胸に秘めようと、悲しみの表現の違いだけで、その点他人に聞かせようとするのも、その悲しみの自己表現のひとつなのだと気がついたのです。つまり、ペットロスの現実に悲しいとメールする人は、他人の慰めに必ずしも重大な意味を求めているのではなく、ただ聞いて欲しいだけであることを、今更ながらに理解したわけです(男には結論のない話が苦手な者が多いという)。そこで私は、文鳥同好者の一員として、冥福を祈り少し励ます程度の内容に止めるようになりました。
さて、ひたすら沈黙する、泣く、誰かに話す、どのような表現方法で悲しもうと、普通の悲しみは時とともに変質していきます。現実の関わりから、記憶の中で対話する存在に変わっていくと言って良いでしょう。ところが、いつまでたってもペットロスの現実を受け入れられず、自己崩壊しかねない混乱状態となる人も、まれに存在します。いわゆるペットロス症候群と呼ばれる人々です。混乱が一過性なら、それも一種の悲しみの自己表現として普通の話ですが、症候群の場合は、長期間にわたりいつまでも悲しみが変質せず、繰り返し繰り返し心をかき乱してしまうのです。なぜ同じように愛する者を失ったにも関わらず、時とともに悲しみを変質出来る人とそうでない人がいるのでしょう。その理屈を考えておくと、そういった事態になってしまった時の予防効果があるかもしれません。
そのような考えで、ペットロス症候群についてかなり厳しい目で見ている私の考え方をここに提示します。今現在ペットロス症候群に苦しんでいる人に対して、あるいは叱咤激励にはなるかもしれませんが、癒す気持ちはまったくないので、精神的余裕のない方はお読みにならないで下さい。【2005年2月】
☆ 症候群の本質とは
いわゆるペットロス症候群とは、ペットロスで飼い主が精神的にダメージを受け、なかなか正常な状態に戻らない事を意味しているようである。しかし、私は少し違うと思っている。ペットロスを「ペットの死」と正しく認識できる人間は、当然悲しく嘆き落ち込む事になっても、いつまでもおかしな状態であり続けることは有り得ない、とは言いきれないまでも、本来あってはならない事だと思うのだ。
いわゆるペットロス症候群の人々が見せる、特にペットに関心のない第三者から見れば異常とも思える喪失状態の原因は、その飼い主がそのペットを人間並みどころか自分の分身と思っていた証拠と、私は見なしている。分身の死とはつまりは自分の死を意味するので、喪失感が格別になるのは当たり前と言えよう。自分の死を悲しむのに、自分以上の存在を、この世で想定するのは難しいではないか!
生死の別れが人間同士であれば、分身ともいえる者に先立たれた人の心情を察するのはたやすいだろう。例えば、昔、愛妻家で知られたある老作家が、その妻の死後に後追い自殺を遂げた。何十年も一心同体であった伴侶を失って、その後を生きる「半身の自分」を見出せなかったのかもしれない。自殺の是非はともかく、その心情と生前からの夫婦愛を思えば、同情して涙するのが人間と言うものではなかろうか。
さて、現在、ペット動物はコンパニオンアニマルと呼ばれているが、このコンパニオンとは伴侶の意味だ。ペット動物を伴侶として、自分と一心同体に生きる存在と見なしても不思議はないのが、現在の人間の精神性の主流なのである。そういった現実を理解していれば、ペットに無関心であっても想像力のある人間なら、ペットロス症候群の人を見れば同情をするのが常識ではなかろうか。もし「ペットの事くらいで、おかしいんじゃないの?」と言ってしまえるとしたら、自分の想像力の貧困と無知を恥じたほうが良いだろう。
しかし、違う考え方もあることは、ペットに深い愛情を注ぐ人も理解しておかねばならない。
私は今現在ペットロス症候群である人に同情する気持ちはあるが、それは人間とペットを同一視する一種の誤解によって生じていると、客観的には分析している。なぜなら、ペットに自由意志などはじめからなく、結局飼い主の保護下(拘束しているとも言えるが、人間に拘束されないとペット動物は生きられない)にあって、その立場はどう考えても人間と対等ではない。対等ではない以上、個人と個人が自由意志で一心同体化している人間同士の夫婦関係とは、所詮まったく違っているのを認めないわけにはいかないのである。
数あるペット動物の中で文鳥は、文鳥自身が飼い主を伴侶と見なす事もある稀有な存在であり、そうなれば本当の意味で伴侶動物であるから、相思相愛の飼い主がペットロス症になって何の不思議もないように思える。従って、文鳥好きの私にとって、文鳥の飼い主でペットロス症候群になってしまう人の気持ちは察するに余りある。しかし、それでも、それは思い込みでしかないと客観的に指摘する声に逆らう事は出来ない。なぜなら、文鳥と人間は別の動物で、文鳥には自由意志はないからだ。
「私は文鳥と一緒に巣作りも出来ないではないか!」
「どう考えても飼い主として、責任を持って飼育しなければならない立場だ!」
少し考えれば、文鳥を人間同士の一心同体の関係と同じと考えるのは、思い込みでしかないという疑惑を避ける事は出来ない。そして、その一方通行の愛情であった疑いを抱いた以上、手放しに悲しみに浸りこむ事が出来るだろうか?もし、なおも浸りたい気分なら、それは一体何を悲しんでいるのか。その悲しみも一方通行になっている思い込み、さらに言えば、死んだ者へのお仕着せになっているのではないだろうか。そのような息苦しいばかりの想念が、次から次に湧き起こってしまうのではなかろうか。
☆ ペットロスへの反応の違い
ペットロスによって、我々飼い主はどのような衝撃(喪失感)を受けるものか、さらに詳しく考えてみたい。
生きてあったものが死んでしまえば、生前付き合いのあった人間は多少とも喪失感を味わうことになる。ただし、名前を知る程度の他人の死と、親兄弟の死とでは、その受ける衝撃は同じであるはずはない。これは喪失感の主観的な量的相違によるものと言えるだろう。親しければ親しいほど喪失感は大きくなるのは、誰しもが共通する感情だと思う。
一方で、喪失したものが親兄弟、友人、ペット、と親しさの度合いは同じであっても、人によって生じる喪失感が異なって見えるのはなぜだろうか。私はこれを喪失感の主観的な量は同じでも質が違う結果だと考えている。その喪失感の質と量を図式化して、①一般的な飼い主と、②ペットロス症候群になる飼い主との、ペットを含む他のものへの認識の違いを説明すると次のようになるだろう。
|
①一般的な他との関係〔生存時〕 |
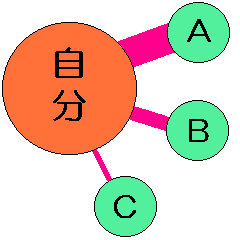 |
『自分』(オレンジ色)と『他』(緑色)が独立しており、『他』のそれぞれとの関係には親疎があり、つながりの太さが違う(ピンク色)。 |
|
↓ |
|
①ペットロス直後 |
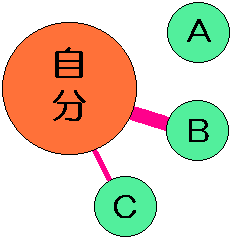 |
Aがいなくなる事で、今まで存在した関係が消滅し、他とのバランスが崩れ、『自分』が不安定になる。 |
|
|
②自己同一化する他との関係〔生存時〕 |
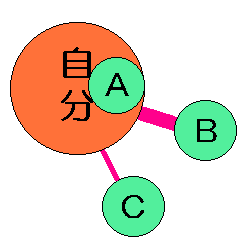 |
特別な『他』Aが『自分』の内部に存在し、自分の一部となっている。 |
|
↓ |
|
②ペットロス直後 |
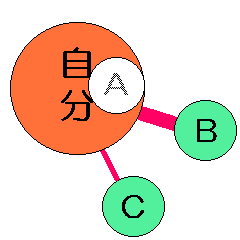 |
特別な存在Aがいなくなる事で、失われる面積(量)は①と同じでも、それにより『自分』の一部が失われ不安定になる。 |
|
ピンク色で示しているのは、『自分』(自己を形成している意識)と他のものA・B・Cとのつながりの深さだ。一般的な①に属する人は、太いつながりをもったものとの関係が、死など現実的な故障で断ち切られた場合、それだけ大きな喪失感を味わう事になる。そして、今までAとの関係でバランスをとっていた『自分』が、一時的に係留ロープを断ち切られた船のように不安定になっても、何ら不思議ではない。
一方、②に属する人の意識の中では親しい者=分身であり、すでに独立した他の生命ではなく『自分』の中に溶け込んでその一部分になっている。したがって、もしその分身がこの世の中から消えてしまう事態に遭遇すれば、その途端に『自分』が不完全な姿になってしまったように思えてしまい、まさに「心にぽっかり穴の開いた状態」、不完全な自分の存在にいつまでも思い悩み、失くした欠片を狂おしいまでに求めたくなるだろう。
愛する者を失った当初は①②の間でさほど差異はないかもしれない。泣く人は泣くし、呆然とする人は呆然とするし、外見に現れない人も同じように存在すると思う。しかし、問題はその後で、おそらくそれぞれのタイプの気持ちはが次の図のように変化していくと思われる。
|
①一般的な他との関係〔その後〕 |
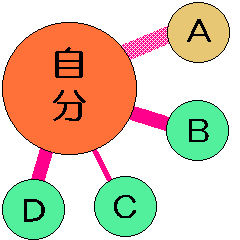 |
新たにDとの関係が構築されることで、『自分』は安定していく。
また、絶たれたかに見えたAとの関係は、記憶の中の実在として再構築される。 |
|
|
②自己同一化する他との関係〔その後〕 |
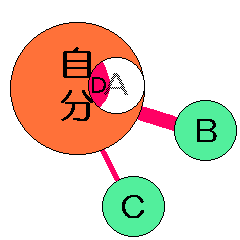 |
新たなDの出現を、Aの痕跡を消すものと感じて葛藤が起きてしまう。
結果として空白はいつまでも埋めにくく、不安定な状態が続く。 |
|
①の場合、新たなDとの関係は悲しみに沈む気持ちを安定するのに役立つ事が多い。文鳥の飼い主で言えば、新たな文鳥を飼い始めるのがこれに該当するだろう。また、Dのように新たな存在がなくとも、すでにあるBやC(主観の問題なので人間でも動物でも無機物でもよい)との関係を強化することで安定していく事も可能と思われる。
また、現実的な関係は喪失されてしまったAも、生きて存在した過去が消滅したと認識したわけではないので、記憶の中で生き続け、自分を支える一つとして生前とは少し違う形で意味づけが行なわれ、やはり自分を安定させる事になるに相違ない。いわゆる「死者との対話」が成立するのである。
一方②の場合、Dの存在はかえって悲しい気持ちに苦しみを加える結果になる可能性が高くなる。確かにDの存在は、他人から見れば失われたAの空白をいくらかでも埋めるように見えるかもしれない。しかし、このタイプの『自分』の主観から見れば、それはAが生きてあった証である空白を覆い隠す事以外ではないのだ。それはAと一心同体と考えていた『自分』にとっては、Aの存在を忘れようとしている、いわばAに対する背信行為のような後ろめたさとなり、その罪悪感が終始付きまとうといった性質を持っているのである。したがって、ペット動物の死により②の心情に至ったペットロス症候群の人たちは、むしろAの存在を忘れないために空白を維持することを求め、それを絶えず意識し、当然の帰結として悲観の循環から抜け出せなくなってしまう構造となってしまう。
またこの不完全な『自分』に耐えられなくなった場合、まったく逆に、Aの存在を完全に封印しようと試みるのも、それは自然な反応と言える。なぜなら、Aがはじめから存在しなければ、Aを失った事による空白も生じるはずがないので、Aが文鳥なら文鳥を飼う事のなかった以前の『自分』が取り戻せる理屈になるのである。つまり、しばしば見受けられる飼育していた記憶につながるものを一つ残らず処分する行動をとる人は、まさに自分自身の精神的崩壊を防ぐため、無意識のうちに自己防衛反応をとっているものと見なせよう。
さらに、『自分』に開いた穴を修復する手段を求めて、クローン技術にすがろうとする人間も現れるかもしれない。他のもので埋め合わせるのを、亡くなった者への背信行為として自己嫌悪を呼び起こす事になる以上、その空白を埋めるには死者に蘇生してもらう以外にないと、おそらく無意識に考えるわけである。実際、最近では数百万円をかけて飼い猫のクローンを手に入れた人がニュースになったくらいで、それは可能な話となってきており、ペット産業の一部として期待されているくらい、需要が見込まれている。
しかし、非常に冷たいようだが事実だけを言えば、クローン技術による複製は個体の蘇生ではない。たんに同じ遺伝子配列を持った生物がもう一つ出来るだけ、言ってみれば、一卵性の双生児が時を隔てて誕生したに過ぎないのである。つまり、似てはいても、他のもの、図で言えばDによって埋め合わせているのと事実上変わりはないのである。それなら普通に縁もゆかりも無いDを求めて、「Aの生まれ変わりだ」と信じたほうが、よほど簡単なように私には思える。
※ペットロス症候群でもなく、安易に死んだペットのクローンを求めるのは、たんに外見上(姿のみならず性向も含む)愛着のある同じものを望んでの事と見なせる。しかし、そのような考えを持つ人は、そもそもはじめから生き物を飼育するべきではない。
生き物というのは、ひとつひとつ違うから尊い、もしくは面白い。愛していたペットの個性を尊重せずに、クローンで代用が可能などと思い込んでいる人は、生き物など初めから飼わず、規格のそろった機械仕掛けの人形を相手にしていた方がはるかに簡単と言える。その方が、一つ壊れても、ほぼ同じものがすぐに手に入るではないか。
クローンを望む人は、自分の行為がどいったものか、とりあえず自分のクローンが存在することを想像してみると良いだろう。あなたは、あなたに似たそいつが、自分として生活するのを許せますか?もし許せるなら、簡単に代用のきくあなたの存在とは何ですか?
私の見るところクローン技術などというのは、食料としての畜産動物(良い肉の個体を複製することで、高級肉が一般化して安くなる)や医療分野(ES細胞を利用した器官の複製、これによりドナーの出現を待たず臓器移植が可能となり、拒否反応もなくなる)など実用的な手段として有効なものであって、ペットの複製などは技術の誤用以外の何物でもない。
そもそも常温動物の体細胞クローンは、現時点では非常に成功率が低く、成功しても平均寿命をまっとう出来ていない(老化が早い)。いまだに不完全な技術と言わざるを得ず、愛したペットの姿そのものの病弱な仔をいくつもわざわざ作り出すなど、私の理解をはるかに超えた身の毛もよだつ腹立たしい行為である。
☆ 症候群を回避する心構え
以上のように考えていくと、文鳥を自分自身の一部分、分身と考えるのは、実に危険な心の有り方と理解されるだろう。それは、いつの日か起きてしまうペットロスに際して、深い喪失感に苦しみ、心に開いた虚無感を抱えて日々を送るか、もしくは、楽しかったはずの文鳥との思い出を抹殺しなければならない状況に追い込まれることを意味しているのである。
しかし、ものは考えようだ。悲しみの量を減らす事は出来ないが、質を変えるのは自分の認識一つに過ぎないのだ。悲しみの堂々巡りをするよりも、
「まてよ、私は彼(文鳥)を愛したけれど、その間、人間としての生活もしていた。だって現に彼の卵は産めなかったし、私は彼(文鳥)の知らない人間の友達とも遊んでいたではないか・・・」
という動かしがたい現実を思い出してもらいたい。そして、少しは文鳥側のひとつの生命としての主体性について想像力を働かしてみてはどうだろう。
「私が外出している時、彼は『ああ、たまにはのんびり出来てよかった〜!』と少しは羽を伸ばしていたかも・・・」
と少しでも笑えるようなら、すでにペットロス症候群から救わていると言えよう。文鳥は、飼い主から与えられた環境の中でも、彼らなりに一生を送ったに相違ないと私は思う。そんな彼らの独立した生命としての存在を認めれば、どうしてその死後まで飼い主の鬱々した気持ちの中に閉じ込めるような事が出来るだろうか。飼い主の悲しく不幸な心情の原因まで文鳥たちに負わせて良いものか、しっかり自覚しなければならないと思う。
自分の文鳥を失えば誰でも悲しい。それが一羽飼育でも何十羽飼育していても、初めての経験でも何十回目の別れでも、悲しみの量など変わらないのである。ペットロス症候群の人は、自分だけが悲しみの量が多いと悩み、周囲から孤立してしまいがちだが、それはまったくの誤解で、実は質の違い、さらに言えばちょっとしたものの見方の違いでしかないのである。ものの見方を変えようとしないのは、ペットの責任でも周囲の人間の責任でもなく、自分自身の心持だと言う事に気づかねばならないだろう
。
死後に流す飼い主の涙の量が、生前の愛情の深さに比例するものでもなければ、いつまでも思い悩むのが亡くなった者への深い追悼の表れと言うわけではない。量は同じ、それをどのような質としてとらえて、悲しみを表現し消化していくかの違いでしかないのだ。そのように考えれば、まるで自分だけがペットの死を真に悼んでいるように錯覚し、悲劇の海に沈み込んでいるなど、たんに分身を失った自分への悲しみ、早い話が自己愛の表現を延々と繰り返しているだけと言えるのではなかろうか。
悲しむのは良い。誰だって悲しいのだ。泣くのも自由だ。それは一つの表現だから。しかし、悲しみに酔いしれて、いつの間にか、亡くなった者への哀悼が亡くした自分への哀れみに変わっては、そもそも亡くなった者に失礼というものだろう。ましてペットロス症候群などと、生前には飼い主に喜びを与えてくれたペットたちに、その死後に起きた飼い主の不幸の責任を負わせるようになっては、とんでもない心得違いであろう。
一個の生命を愛し尊重した飼い主なら、ペットロス症候群などにはなってはいけない。それが、確かにペットロスが引き金となっての精神の不安定であると一般的に認められ、心優しく物分りの良さそうな人の同情やカウンセリングが、あたかもそのペットロス症候群という言葉の流行の中で、やさしく癒してくれるように見えても、その本質が自分では見るはずもない自分の死を仮想体験して悲しむ強烈なナルシズムの所産であるなら、本来他人に甘えて癒されるような性質のものではない事に、自分自身で早く気づいた方が良いと、私は思う。
そもそも、あなたと分身と信じるペットとの付き合いが、他の人に変わってもらえる事など出来ないかけがえの無いものである以上、どうして今更、他人に完全に理解して癒してくれる事を望めるだろうか?最終的には自分で解決するしかないのである。
飼い主としての不心得のなせる業と言われないように、そして何より亡くなった文鳥のために、ここは意地でも自覚してにっこり笑って悲しみから立ち直らなくてはならないのではなかろうか。
表紙に戻る