 タネは早めに蒔いても、時期が来たら自然に発芽する。それまで眠っている。早く芽が出過ぎてしまい、霜にやられることはまずない。
タネは早めに蒔いても、時期が来たら自然に発芽する。それまで眠っている。早く芽が出過ぎてしまい、霜にやられることはまずない。米は針のような芽が出る。
6月中旬、米の苗が20〜30cmになり、それを約1mの冬草の間に植える。冬草は大きいが、元気がなくなっている。
 タネは早めに蒔いても、時期が来たら自然に発芽する。それまで眠っている。早く芽が出過ぎてしまい、霜にやられることはまずない。
タネは早めに蒔いても、時期が来たら自然に発芽する。それまで眠っている。早く芽が出過ぎてしまい、霜にやられることはまずない。
米は針のような芽が出る。
6月中旬、米の苗が20〜30cmになり、それを約1mの冬草の間に植える。冬草は大きいが、元気がなくなっている。
写真は、タネを蒔いている様子。
<赤目での基準>
| 1反=300坪=10a(アール)=1000m2の広さの田んぼには、 |
| 幅1.4m(両側から手が届く距離)、長さ20mの苗床に7合のタネを蒔く。 |
これを自分の田んぼの広さに換算して必要な苗床の広さとタネの量を求める。
<自分の田んぼで計算>
私たちが借りた田んぼ(畑)の陸稲を植えようとしている面積は27m2であった。
必要な苗床の長さ = 20 * 27 / 1000 = 0.54mこれより、1.4mx0.54mの苗床を作って、0.19合のタネを植えることにした。
必要なタネの量 = 7 * 0.54 / 20 = 0.19合
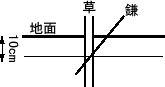
背高あわだちそう、笹、ヨモギは根から引き抜く(枯れているので抜けやすい)。スコップで切れ目を入れて手で根を掘り出す。表面20cmまで。
ススキのカブは苗床にするのは避ける。
後から苗床に草を被せるので、緑の冬草は丁寧に刈っておいておく。
枯れ草(稲ワラ以外)は去年の夏草なのでこれは絶対混ぜては行けない。
タネの選別には、水、風、塩水を使う3つの方法がある。
ここでは水選(すいせん)をする。 タネを水につけて沈んだものだけを使う(なすび、スイカ、ナンキンでも同じ)。
塩水は浮きやすいので、選別がより厳しくなる。浮いているのは、芽がでるかも知れないが、元気がない。沈んだものを網ですくって取り出し、蒔きやすいように水を切っておく。
米を水に浸けて、発芽を早くする方法もあるが、自然農では、芽出しを助けない。タネを蒔いた後にも一切水を蒔かない。
タネ蒔きの時期が遅れてしまったら、5日くらい川から汲んだ水に浸けておく。その場合、毎日、水を入れ替える必要がある。
生育途中の冬草や、米の稲わらを振りまく。野菜を植える場合は多めに振りまく。
緑の冬草は枯れると縮まるので多めにする。青草の方が苗がよく育つが、多すぎたらよくない。生育途中の草が土に返るより、一生を全うして死んだ草の方がよい。枯れ草に夏草が絡まっていると、夏草が一杯生えるので、夏草を丁寧に抜き取らなければならない。米の稲わらは20cm程度に切って振りまく。笹の葉は使えるが茎は太すぎてダメ。
モグラ対策として苗床の周囲に溝を掘る。モグラが通れないように溝の中には草も敷かない。掘り起こした土の固まりはそのままにしておき、田植えのときに固まりごと戻す。
肥料を与える場合
どうしても肥料が必要な場合は、苗床5m2に対して、菜種かす0.5升、または、米ぬか1〜1.5升でよい。
田全体にも、栄養のため、畝を作った後、1反で200kgの米ぬかを蒔く。12月に行うと、腐っていくのでよい。
よい作業時期
12月、苗床用に土をかき分けるところ(1.1)〜6)まで)を済ませ、米ぬかを蒔き、その上に稲わらを3cmの厚さに敷く。
4月、稲わらを取り除き、種を蒔く。
その他
川口さんは、鍬を使うとき、右手、右足が前に出る。そのとき、左手に力を入れて右手を舵取りにすると、疲れにくい。
鍬やスコップは重い方が、その重みを利用できるので、疲れにくい。
ビニール類など自然に帰らないものを見つけたら、必ず取り出す。
鎌を使った後は、地面に刺しておくと見失わない。
畝を作った方が、土がよい状態になるのが早い気がする。空気の通りがよくなるからだろう。
常緑樹は春に植えるのがよい。
落葉樹は冬に植えるのがよい。
木を植えるとき、根を束ねているものは、それを外して、根っこの形そのままで植える。根っこが長くて地面の腐葉土の層を突き破って砂利になっても構わない。このとき、根に小さい枝のようなものがあれば、その状態のまま地中に植える。根が落ち着くまでは、支えがいる。根を曲げて植えると、地上の幹も曲がって成長してしまうので注意する。
霜対策として、冬には、木の枝にわらをかけておく。傘の骨のようにして引っかけておけばよい。
川口さんはぶどうをつくった経験はあるが失敗した。
クローバは空気中の窒素を固定する役目を果たす。クローバのおかげで、米はよく育つかもしれないが、やりすぎると米が弱くなるのでよくない。
 下の段の畑の全貌。周囲に水路を掘り、右下に苗代をつくり、タネを植えている。
下の段の畑の全貌。周囲に水路を掘り、右下に苗代をつくり、タネを植えている。計画では、下の畑に陸稲(川口さんから頂いたうるち米)を作り、上の畑の山側半分に陸稲(タイの香り米)を作る。上の畑の残りには、野菜を植える。
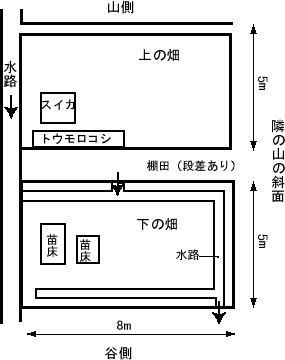
 水路、畝、畦を作った。昔の水路の跡があったので、それを利用して、水路、溝を掘った。水は、山側中央付近より入り、左と右下に流れていくようにした。
水路、畝、畦を作った。昔の水路の跡があったので、それを利用して、水路、溝を掘った。水は、山側中央付近より入り、左と右下に流れていくようにした。
イノシシよけの柵を寄せて、杭を打ち直した。
水が畑に侵入して水浸しになっていたので、低いところに土を盛って補修した。
苗代を作り、稲の種を蒔いた。
川口さんのアドバイス。「山側の水路の幅をさらに広くして、その土を積み上げる。そうすると、そのスペースに里芋などが植えられる。」
溝の掘り方
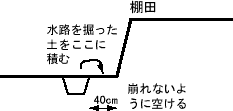
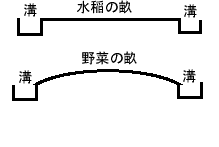
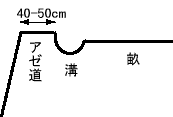 溝とあぜ道の高さ
溝とあぜ道の高さ
川口さんのアドバイス。「水路は山側には最初から水が流れているので、これ以上の水路、溝を作らなくてもよい。山側の水路の幅をさらに広くする。笹の茎が太すぎ量が多すぎるので、畑に蒔けない。先の細い部分は切って、畑に振りまいておくが、残りの太い茎の部分は畑の右上の位置にきちんと一本ずつ積み重ねて置いておく。斜面の笹も風通しと、日当たりをよくするために刈る。」
ホームにもどる 更新2000年5月15日