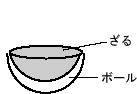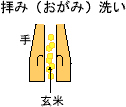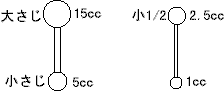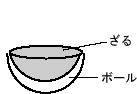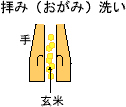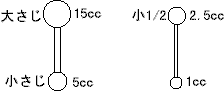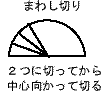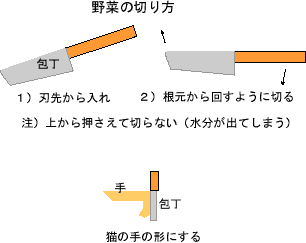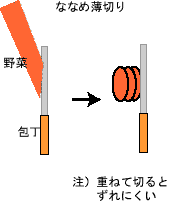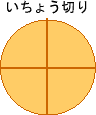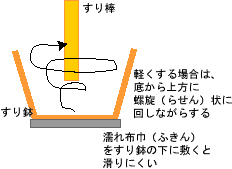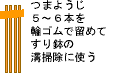正食協会クッキング−1−
これは1999年の春に私が正食協会クッキングスクール初級に通ったときのノートです。
4月10日(土)14:00〜17:00
講義
0.食とは
- おいしいもの・・・一般社会が追求
- おなかに優しいよいもの
→正食は両方を追求する
1.季節のもの
季節のものを食べる。
春
タケノコ、山菜、タラの目、ツクシ、ヨモギなどの
伸びる力の大きいもの、苦みのあるもの(体のあく抜きをする)を食べる。
冬の間は寒いので運動不足になるし、油濃いものを食べているので、春先のものを食べてお腹を掃除して出さないと、梅雨を乗り切れない。
夏
キュウリ、ナス、トマトなどの
水気の多い野菜・・・体を冷やしてくれる働きの強いもの
色は緑・紫・・・・冷たい色
夏にできるものはお腹の中でクーラーの働きをする。
秋
ダイコン、ゴボウ、ニンジン、カブラ、木の実、栗などの
特に土中のものがたくさん穫れる。
冬に向けての体作りを秋から準備する。
保存できる。
ダイコン、レンコン、ゴボウなどは濡れた新聞紙でつつんでおく。
日持ちのするものは1年中食べてもよい。体を温める。
冬
切り干しダイコンなどの
保存していたものを煮込む。
冬の間、太陽の当たった干し物で補う。おせち料理がその代表。
油濃いものが欲しくて、煮込み料理が欲しくなる、体を温めるのによい。
・・・・・・
春
繰り返し
このようにして体は整えられる
例えばイチゴの旬は5月なので、
その時期以外では栄養分は1/4になっている。
体が冷える。季節以外のものを取り込まない。しかしどうしてもその材料を使わなければならない場合は、その働きを弱める料理法を学ぶ。
2.一物全体食
野菜を丸ごと料理する。
つまり皮をむいたり、ゆでこぼしたり、あく抜きをしない料理をする。
米も玄米(胚芽米でも可)
白米は玄米の外の皮を除いたもので、取り去った栄養を補うために副食が多量に必要になるが、白米と計算した副食を食べるのは困難。
玄米には副食不要、もしくは少量で可。本能的に要らなくなる。
野菜も皮ごと食べる。
タマネギの皮以外は食べられる。タマネギの皮も血圧を安定させるので、スープのだしに使える。
3.生命のあるもの
加工されていないもの
芽の出るもの(玄米は水につけておくと発芽するが、白米は腐る。→白米は体を弱める)
手の加わってないものを食べる。
4.主食と副食のバランス
人には奥歯20本、犬歯4本、前歯8本があり、それぞれ穀物を噛み砕く、肉を噛み切る、野菜を噛み切る働きをする。
これより、穀物5、動物(肉)1、野菜2の割合で食べるのがよい。
歯は食物の門。歯の数で示してくれている。バランスが崩れると、肩こり、目ヤニ、かさかさ肌になる。まずは軽い症状から現れる。
重い症状をもった人は厳格に守らなければならないが、そうでない人は自分のペースでよい。
茶碗1杯、副食は半分、副食の2/3が野菜、1/3が肉。
つまりステーキ1片で野菜はボール一杯に相当。
5.食べ方
よく噛む。
噛むと、唾液が出て胃腸の消化を助ける。
顎(あご)でポンプ状になり、脳に血液が行く。頭が冴える。
痴呆症の人に噛ませるとよい。
奈良で実践しているが、寝たきりの人が動けるようになった。
血液の流れをよくしてくれ、体中の錆を落としてくれる。ガン細胞を押さえる効果もある。空気中の自然界から入った異物を除去してくれる。胃腸の弱い方は特によく噛んで食べること。
6.身土不二
自分の住んでいる土地の近くで穫れるものを食べる。
寒いところで育つ作物は体を温めたり引き締めたりし、暖かいところで育つ作物は体を冷やしたりゆるめたりする。
流通が発展していて外国の食べ物が入っているが日本国内のものを食べる。バナナは暑い国の人が食べて体を冷やす食べ物。温暖な日本には合わない。
例えば、ミクロネシアでは、ある時期はバナナを食べない。病気になって民族が滅びるという言い伝えがある。生で食べるのは観光客で、現地の人は土の中で蒸してから食べる。暑い国で穫れる食べ物は日本には合わない。
日本の狭い国でたくさんの国民を賄うのに最適な食べ物はお米。お米1粒を播く→3000〜2000粒も収穫できる(2/3カップ相当)→ご飯茶碗3杯分・・・つまり一人一食食べられる計算
「米粒の中には3体の仏様がいて、一粒たりとも粗末にしてはならない。」
玄米の炊き方
玄米は吸水性が悪い。
- 玄米を洗う。
玄米は冬の時期は拝みあらい(おがみあらい)(拝むように手をこすり合わせてその間で玄米を洗う)。夏になると、カビが生えやすいので白米のように研ぐ。 お米を2〜3回流水で洗う。
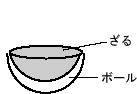
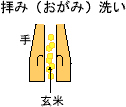
- 水を切って20〜30分以上置く。
- 水を入れる。
水の量は米の1割〜3割増。 (米2カップに対して水3カップ、米3カップに対して水4カップ。)
- 塩をまんべんなく入れる。 塩は1%。(米10カップに対して塩大さじ1。)
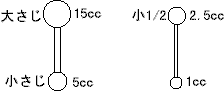
(大さじ=15cc、小さじ=5cc)
- 圧力鍋のフタを締めておもりをのせる。
- 強火(15分程で沸騰し、おもりが揺れる)。
- 弱火25分。(いつまでもおもりが動くのは火が強すぎ、全くおもりが動かないのは火が弱すぎ。)
- 消火。
- 蒸らし15分。
- おもりを傾けて蒸気を出す。
- フタを取り、下と上のご飯を混ぜてほぐす。
- 乾いた布巾を上から被せて水分をとる。木のおひつに移す。
(木のおひつに移すのはアルミなどの金属類が溶け出さないのと、水分調節によいから。)
みそ汁
動物性は使わない。
- 干しワカメ
軽く洗って砂を落とす。ボールの水に浸けておくと栄養が逃げる。
- 玉ねぎ
まわし切りする。・・・(くし形切り)中心に向かって切る。 芯もだしになる。根も利尿剤。
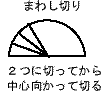
- うす揚げ
油抜きする。
つまり、湯の中でぐらぐらし、拝む(おがむ)ように手のひらで挟んで絞っておく。 細切りする。
- 鍋を温める。
フタのできる鍋を使う。手が熱くなるまで温める。
- ゴマ油を入れる。
2cc
- 玉ねぎを入れる。
ジャーという音がするのは火が強すぎ、音がないのは火が弱すぎ。
- 揚げを入れる。
- 塩を入れる。
2本の指で1つまみして入れる。
うまみを引き出す。
- フタをして弱火にする。(蒸らし)
水分が出て、蒸し煮状態。終える目安は鍋の縁から湯気が出る。
- だし汁を入れて強火にする。
だし汁は1人150g
昆布を一晩水に浸けておいたもの。
強火にするのは、野菜から酸味が出て酸っぱくなるのを防ぐため。
沸騰するまで続ける。具が柔らかくなれば弱火にする。
- 味噌を入れる。
1人15gの味噌(梅干し1個の大きさ)
網で味噌をこすようにして鍋の中で溶かす。または、味噌をすり鉢ですって溶かす。
- 沸騰前に火を止める。
味噌を入れて沸騰させるとまずくなる。
- ネギを入れる。
ネギの根も利尿剤になるので捨てない。
きんぴらごぼう
常備菜。秋に穫れるが保存できるので年中食べてもよい。
- ゴボウ
斜め薄切りにし、ずらして重ねて細切りにする。
左手を猫の手にしてゴボウを持ち、右手の包丁で切る。
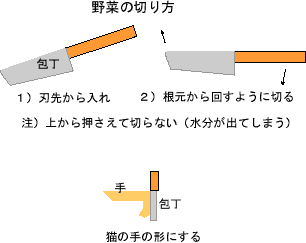
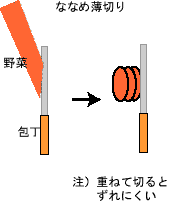
- ニンジン
斜め薄切りにし、ずらして重ねて細切りにする。
- レンコン
大きいものは1/8、小さいものは1/4(イチョウ切り)に切る。
黒いヒゲは取るが、すり下ろして煮汁を飲むと咳止めになる。フシレンコンは気管の弱い(喘息)人に役立つ。
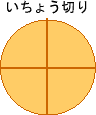
- 鍋を温める。
- 油を小さじ1入れる。
- ゴボウを入れ、油をまわす。
- 隠し味として梅酢(または塩)を入れる。
- フタをして弱火にする。
鍋の底とコンロの間に敷くものがあり、これを使うと極弱火にできる。
- レンコン、ニンジンを炒める。
フタを取ったらゴボウのアクが抜けて、甘い香りに変わっている。
- 水をヒタヒタに入れ、強火にする。
入れた水の量を量っておく。
ヒタヒタとはゴボウが水面上より少し出ている程度の水。
すらいちとは水面上に出ていない程度の水。
煮立ってから弱火にする。
- 醤油を水の1/10入れ、煮汁がなくなるまでそのまま煮る。
ごま塩
- 塩
「海の精」がおすすめ。
- ごま
あらいごま、生ごま、と言われているるものを使う。
スーパーで普通に売られているのはいりごま。
- 鍋を温める。
- 塩を入れて鍋を揺する。(炒る(いる))
塩に色がつく。
- すり鉢で勢いよくする。
ザラザラの塩が小麦粉状になる。
すり鉢、すり棒は乾いているものを使う。
すり鉢の下に濡れ布巾を敷くとすべらない。
- 鍋を温める。
- ごまを入れて鍋を揺する。(炒る)
- パチパチと飛び出す前に火から下ろし、フタをして余熱で鍋を揺する。
- すり鉢で軽くする。
筆を持つようにすり棒を持ち、すり鉢の底から上方に円を描くようにすっていく。勢いよくすると油が出るのでダメ。
80%程ごま粒がなくなったら出来上がり。
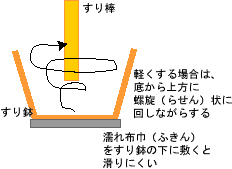
すり鉢の溝にはいったものは爪楊枝(つまようじ)を束ねた物で取り出せる。
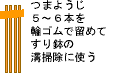
ビンの中に入れて冷暗所に保存しておく。
ごまの酸化はにおいがするし、体に悪い。
食べ方は、1食につき小さじ1杯を玄米にかけて食べる。
ホームにもどる