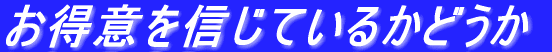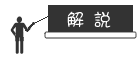私の50年の事業体験から申しますと、もし私が小売屋さんであるとして、隣にスーパーができたとします。そしてある物を安く売るというようにいたしたとします。すると客は、必ず隣に買いに行くだろうと、こういうことが一応いえます。そうすると自分の店は困るなと心配するわけであります。しかし、今の私はそれを心配しません。というのは、私は50年の経営の体験から、そういうものができても、自分は十分に自分の店を維持してやっていけるということを知っているからであります。「そんなことを言ってほんとうにできるのか。かりに自分のほうではナショナルのものを1万円で売っておった。隣がそれを9,500円で売ったならば、同じナショナルの商品やから、隣のものを買うのが当たり前や。そやから売れんようになるんや。それは困るやないか。そういう場合にはどうか」と、こういうお尋ねがあるだろうと思うんです。
ちょっと考えると、そういうように思うのであります。しかし私は心配ないと思うんです。そりゃおかしいと皆さんおっしゃるかもしれませんけれども、これは、隣にできたスーパーの経営者の経営いかんにもよりましょう。すばらしくすぐれた人であり、すごい魅力のある人であり、またわれわれの気のつかないようなすばらしい経営法を案出して、そして町の人気をさらっていくという何千人に1人、何万人に1人というようなすぐれた人であれば、これはあるいは自分の得意が半分なくなるかもわからんと思います。しかしまずそういう人は現実にはございません。すぐれた点もあるが、また一面に欠点もあるのが人間の姿であります。
そうでありますから、決して自分の老舗のお得意というものは、そう無条件に動くものではないというその信念が、私は大事やと思うんです。きょう買うてあした使って雲散霧消するものであれば、それはあるいは安いことによって流れるかもわからない。しかしわれわれの商品というものは、売ったならば自分の娘を嫁にやったようなものです、早くいえば。うまく働くか働かないか、気に入ってくれるか気に入ってくれないかというようなものだと思うんですね。自分の娘を嫁にやるように、われわれは物を売っているんです。だからその買ってくださった家と自分の店とは親戚になっているわけです。親類であるということを、われわれがグッと認識すれば、親類になるんです。親類やない、赤の他人である、その人はどこに行くかわからんと考えたら、そのとおりになる、私はそう思うんです。お得意を信ずるか信じないか、こういう考えをまず商店の経営者がもっているかもっておらないかということである。
(昭和42年11月22日 京滋地区ナショナル店会連合会躍進大会 於:国立京都国際会館)