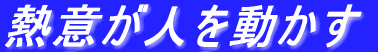中国の戦国時代、蘇秦という人がいた。一民間人にすぎなかったが、自分の学び修めたものを世の君主に用いてもらおうと考え、各地を訪れたものの、最初はどこでも相手にされなかった。けれどもそれにもめげず、ついに燕の国王に用いられた。当時の中国には、燕をはじめ、秦、趙、斉、魏、韓、楚の七国があったが、西方の秦がしだいに強大になり、他は圧倒されつつあった。そこで蘇秦は、燕を足がかりに、趙、韓、魏、斉、楚を順次訪れ、各国の王に、共同して秦に対抗するよう熱心に説いた。各王ともそれに動かされ、ついに蘇秦は、六カ国の宰相の地位を兼ねるにいたり、さすがの秦も、十五年間は他国に攻め入ることはできなかったという。
戦国の時代には、各国とも進んで人材を求める風潮が強く、したがって、志を抱いて王公を説き、登用された人は少なくないようである。しかしその中で、六カ国の宰相の印綬を帯び、天下に号令した蘇秦の業績はきわ立っている。
これは、蘇秦の策が当を得たものであり、また弁舌がきわめて鮮やかであったこともあろうが、同時に、そのことに対する彼の熱意がきわめて強かったこともあるのではなかろうか。昔の不便な時代に、広い中国中を説いてまわるのはずいぶん大変なことであろう。また、燕の国で国王に謁見を許されるまで、一年余りもかかっているともいう。ふつうではあきらめてしまうところを熱意を持ってやり通したところに、彼の成功があったのだと思う。
実際、熱意こそ物事をなしとげる一番の要諦だと思う。なんとなくやりたい、という程度ではなかなか事はなるものではない。なんとしてもこれをやりとげようという熱意があって、はじめて知恵もわき工夫も生まれてくるのである。
特に指導者は、こと熱意に関してはだれにもまけないものを持たなくてはならない。知識なり、才能なりにおいては、人に劣ってもよいが、熱意については最高でなければならない。指導者に、ぜひともこれをやりたいという強い熱意があれば、それは必ず人を動かすだろう。そしてその熱意に感じて、知恵ある人は知恵を、才能ある人は才能をといったように、それぞれの人が自分の持てるものを提供してくれるだろう。
指導者は才能なきことを憂うる必要はないが、熱意なきことをおそれなくてはならないと思う。
(『指導者の条件』より)
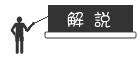
人を生かし、動かすための心得として、弊社創業者・松下幸之助は指導者みずからが最高の熱意を持つことが必要であると訴えていました。いかに知識や才能があっても、熱意に欠ける指導者であれば、人を動かすことはできません。たとえ知識や才能に少々乏しい点があったとしても、強い熱意があれば、その姿を見て思わぬ援助、目に見えない加勢が集まり、成果が自然に生まれてくるものだというのです。
こんなエピソードがあります。
松下がある商品についての説明を技術担当者から受けていました。デザインに疑問を持った松下が、「きみ、この商品はもうちょっとこうしたほうがええのとちがうか」と意見を述べると、担当者は「はい、実は私も製作段階でそう思っていました。しかし、上司の反対にあいましたので、今のような形にいたしました……」と答えました。それを聞いた松下は急に表情を厳しくして、「いいと思ったのであれば、なぜ上司を説得せんかったのか。上司説得の権限はきみにあるんだよ」と叱責したといいます。
一人の社員に熱意がなくても、組織であればそれなりに仕事は流れていくものです。しかし、熱意なくして流れた仕事が、自分も周囲も満足できる結果に結びつくはずがありません。組織の論理だと最初から上司への進言を諦めてしまったその担当者に、松下は熱意が足りないもどかしさを感じたのでしょう。
仕事は互いの知識や才能の乏しさを補って、はじめて成立していくものです。それには社員一人ひとりが仕事に対する熱意を持つことが必須です。彼らの熱意を生み出すために、指導者はあたかも磁石が周囲の鉄粉を引きつけるように、ひときわ強い熱意をまずみずからが有していなければなりません。人を動かせるだけの熱意を持っているかどうか、時に省みるべきではないでしょうか。