
松下幸之助の「商いの心」
〜仕事を見直す心得とは〜

平成23年02月
まあ太閤さん(注:豊臣秀吉)といえども、自分の怒りなり愚痴なり、そういうものはたくさんもっておったと私は思うんです。それを訴えたい、しゃくにさわってしかたないんやというて話したいと思っても、うっかり話はできない。それが積もり積もれば、神経衰弱になるということもあるかもわからん。けれども、信長(注:織田信長)に仕えてだんだん天下を取っていく、戦争で勝っていくという非常に危険といえば危険きわまりない日々を送る中で、太閤さんが神経衰弱にならずして、反対に陽気な人であったのは、その愚痴を、その悩みを三成(注:石田三成)に訴えていたからでしょう。三成だけが「分かりますよ」「承知しました」「こうですよ」と、愚痴をよく聞いてあげたんでしょう。
皆さんでも、部下をたくさんおもちになっていると思いますが、部下のうちに、だれか一人、自分の悩みを訴えられる人があるかどうか。あれば非常に皆さんは精神的にお楽になると思います。けれども、幸いよく働く人がたくさんあっても、自分の悩みを訴える部下がなかったら、これは疲れますよ。それでは自分の働きが鈍ってくるということもあるわけですね。
ところがそういう部下があったならば、社長でも、部長でも、課長でも、その人のもてる力全部を生かすことができるということになる。家へ帰って奥さんに愚痴を言うことも、ストレスの解消になりますけれども、そこまでいくと具合悪い。やはり自分の直接の部下の中に、すべてを訴えられる、機密も打ち明けられるという人があれば、これは非常に楽やと思うんです。
だから、その人がいい働きをするかしないかは別として、愚痴を訴えられる人、うまく愚痴を聞いてくれる人、そういう部下があれば非常に助かると思うんです。私はそういう意味において、三成が太閤をして太閤たらしめたのは、太閤さんがもっている愚痴を全部彼が吸収して、「分かりました。心配しなさんな。やりなさい」というようなことを適当に言うたからやと思うんです。
皆さんが今後責任者としていろんな仕事をしていく上において、そういう部下、そういう話し相手というものが、できるかできんかという問題、これは一つは運命でしょうけれども、そういう人ができる運命をもっているということが非常に大事であると私は思います。そうすると三倍も四倍も働けると思います。
(昭和51年12月7日 日産自動車幹部研修会における話)
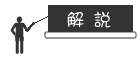
昭和7年に当時の松下電器製作所に入社し、同22年、松下電工社長に就任、以来30余年にわたって同社を日本一の「住まいの総合メーカー」に育て上げ、弊社創業者・松下幸之助を支え続けた丹羽正治氏に次のようなエピソードがあります。
戦後、全国の企業に労働組合が誕生しましたが、昭和23年ごろは世間の労使関係が非常に荒れていました。そうしたある日のこと、松下がふらりと丹羽氏の部屋にやってきました。丹羽氏の社長室には机が2つあり、1つは丹羽氏のもの、もう1つは松下のものです。
松下は丹羽氏のとなりの自分の椅子に座りながら、ポツリと「な、きみとぼくとは“封建”でいこな」と言ったのです。このときの松下の様子を丹羽氏は著書『任して任さず』(東洋経済新報社刊)の中で、こう述懐しています。
(当時の風潮では労働組合の幹部は、社長を社長と思わなかったし、自分自身がすごく偉くなったと思い込んでいて、口のきき方、態度が実に横柄で、ときには社長の机の上に腰をかけたり、ひどいのになると、机の上に足を乗せて、「オイ、社長」などと、偉そうな口をきいたりした。そんなことに、すっかりいや気がし、しみじみと戦前の家族主義的な社風を懐かしがったのである。“封建”といったのは、なにも封建時代の上下関係というより、義理人情というか、日本のよき伝統を守ろうという意味であったと思う。)
長年、松下に寄り添い、松下のことを「おやじ」と呼ぶ丹羽氏だからこそ、松下は気を許して本音を言ったのでしょう。丹羽氏は松下のいいつけに何でも「ハイ」と答えていたそうです。ただそれはけっしてやみくもに答えていたのではなく、長年の関わりからいちいち理由や事情を考えなくとも、相互に安心感があるからでした。丹羽氏によれば、松下が自分に頼みごとをするという場合は、「おやじはいま味方少なく敵多い仕事に立ち向かおうとしているんだ。何人かの無条件支持者がいることは、おやじの勇気の根源になるから、という思いでいた」と述べています。松下も丹羽氏のそうした心がけに安心して愚痴が言えたにちがいありません。
経営者にとって丹羽氏ほどの理解を示してくれる部下が1人でもいれば、大いに慰めが得られるといえましょう。