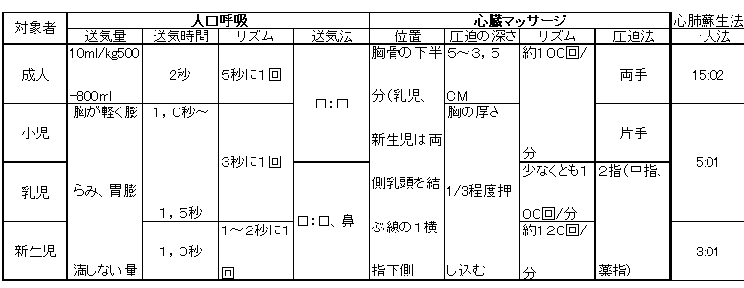�~���蓖�̊�b���Z
�~���蓖�Ƃ́A�����a�C�ɂ��A���a�҂��ˑR�Ɉӎ���Q�A�ċz��~�A�S�z��~�Ȃǂ̏��ԂɂȂ����Ƃ���A��o���ɂ�萶���̊�@�Ɋׂ������ɍs���鉞�}���u�������܂��B�~���蓖�ɂ́A�S�x�h���@�Ǝ~���@�Ƃ�����܂��B
�@��X�w�����́A���R����̐g�̐������A���a���肵�Ă���킯�ł�����A���S�ɃX�C�~���O���C�t�i�ł���悤�A�S�����Ă��܂��B
���S�x�h���@�̗���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���l�A�W�Έȏ�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iY)yes (N)no
���a�҂̔����ˈӎ��ׂ�B�iY)���ċz�ׂ�iY)���̈ʂɂ���
���a�҂̔����ˈӎ��ׂ�B�iN)�����͎҂��遨�C���̊m��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ċz�ׂ�iN)���������݂Q��
�z�̃T�C���ׂ遨�l�H�ċz�A�S���}�b�T�[�W
�@�E�ċz�����邩
�@�E���������邩
�@�E���������邩
���h���@�́A�~�}�����A�܂��͈�t������܂ő��s����B
�@�i�Q�`�R�����Ƃɏz�̃T�C���ׂ�B�j
���~�}�p�V�[�g
���K�C�h���C���Q�O�O�O�ɔ����������e
���p��̒�`
�@�@�@���}�蓖�[�~�}�h���@����������ʎs���̎蓖
�@�@�@�~���蓖�[��ʎs�����s���~�}�h���@
���N��̋敪�̒�`
�@�@�@�E�o����Q�W�������[ �V����
�@�@�@�E�o����Q�W���ȏ�P�Ζ����[ ����
�@�@�@�E�P�Έȏ�W�Ζ����[ ����
�@�@�@�E�W�Έȏ�[ ���l
�����o���̊m�F
�@�@�@�ӎ����Ȃ���Ό��o���̊m�F�����Ȃ��Œ����ɋC���m��
���ώ@�v��
�@�@�ċz�m�F�[�C���m�ۂ���P�O�b�ȓ��Ōċz�̗L���f����B�K�������A�P�O�b�Ԋώ@�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���̊ԂɌċz�̗L�����m�F�ł���P�O�b�����Ŏ��̎蓖�Ɉڍs�ł���B
�@�@�����m�F�[�Q��̌ċC�����ݐl�H�ċz���s������A�ċz�����邩�A�P�����邩�A�̓��̂����ꂩ�����邱�Ƃɂ���āA�S��~�f����B
���l�H�ċz�@
�@�@���l�@�E���C�ʂP�Oml/kg(500-800ml)
�E���C���Ԃ́A�Q�b������B
�@�@�@�@�@�@�E���Y���́A�T�b�ɂP��̊���
�@�@�@�@�@�@�E�����y���c��ޒ��x
�@�@�����@�E���C�v�̂͋����y���c��݁A�݂��c�����Ȃ�
�@�@�@�@�@ �E���C���Ԃ́A�P�`�P�C�T�b
�@�@�@�@�@�@�E���Y���́A�R�b�ɂP��̊����@
�@�@�����@�E���C�v�̂͋����y���c��݁A�݂��c�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�E���C���Ԃ́A�P�`�P�C�T�b
�@�@�@�@�@�@�E���Y���́A�R�b�ɂP��̊����@
�@�V�����@�E���C�v�̂͋����y���c��݁A�݂��c�����Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�E���C���Ԃ́A�P�b
�@�@�@�@�@�@�E���Y���́A�P�`�Q�b�ɂP��̊����@
���S�x�h���@
�@�@���l�@�E�P���ԂɂP�O�O��̑����ŐS���}�b�T�[�W
�@�@�@�@�@�@�E�����ʒu�͋����̉�����
�@�@�@�@�@�@�E�����̐[���͂R�C�T�`�Tcm
�@�@�@�@�@�@�E�ŏ��ɐl�H�ċz��Â��ɂQ��s�Ȃ��A�z�̃T�C�����ώ@�A�Ȃ���ΐS���}�b�T�[�W���s��
�@�@�@�@�@�@�E�S���}�b�T�[�W�Ɛl�H�ċz�̊����͂P�T�Q
�@�@�@�@�@�@�E�S�T�C�N���s������z�̃T�C���̗L�����Ċm�F����B�Ȍ�A�Q�`�R�����Ƃɏz���̃T�C�����m�F����B
�@�@�@�@�@�@�E��l�̋~���҂��܂��S�x�h���@���s�Ȃ��A���̐l�͂P�P�X�Ԓʕ��A�ЊQ���h�~�����s���B
�@�@
�@�@�����@�E�P���ԂɂP�O�O��̑����ŐS���}�b�T�[�W
�@�@�@�@�@�@�E�����̐[����1/3���ڂޒ��x�ŕЎ�ʼn���������B
�@�@�@�@�@�@�E�����ʒu�͋����̉������i����ˋN�Ƙ]�����łł���؍��̎w�P�{�������̈��u�j
�@�@�@�@�@�@�E�S���}�b�T�[�W�Ɛl�H�ċz�̊����͂T�P
�@�@�����@�E�P���ԂɂP�O�O��̑����ŐS���}�b�T�[�W
�@�@�@�@�@�@�E�����̐[����1/3���ڂޒ��x�ŕЎ�ʼn���������B
�@�@�@�@�@�@�E�����ʒu�͋����̉������i���E�̓��������Ԑ��Ƌ������������镔�����w�P�{�������̋�����j
�@�@�@�@�@�@�E�S���}�b�T�[�W�Ɛl�H�ċz�̊����͂T�P
�@�V�����@�E�P���Ԃɖ��P�Q�O��̊����ŐS���}�b�T�[�W���s�Ȃ�
�@�@�@�@�@�@�E�����ʒu�A�[���A��Z�͓����Ɠ����B
�@�@�@�@�@�@�E�S���}�b�T�[�W�Ɛl�H�ċz�̊����͂R�P
�@�P�P�X�Ԓʕ�
�@�@�@�����A�����A�V�����ł́A�����ɂP�P�X�Ԓʕł��Ȃ��Ƃ��́A�z�̃T�C�����Ȃ����ΐS�x�h�����P���s�Ȃ��A���̂��ƂɂP�P�X�Ԓʕ̉����A���͂����߂�B�������A�~���҂���������ꍇ�́A���R�~���蓖�ƂP�P�X�Ԓʕ����s���čs���B
�@�S�x�h���@���~�
�@�@�E�\���Ȏ����ċz�A�z�������ƔF�߂�ꂽ�ꍇ�B
�@�@�E�~���҂Ɋ댯����������A�d�x�̔�J�ɂ��p��������ɂȂ����ꍇ�B
�@�@�E�~�}���A��t����O�҂Ɉ��p�����ꍇ�B
�@�@�E�����Ȏ葱���ɂ�菑�ʂŖ{�l���S�x�h���@�����ۂ��Ă���ꍇ�B
���ٕ������v��
�@�E���l�A�����̏��a��
�@�@A)�P�����Ă���ꍇ�́A���̂܂܋����P�����܂���悤�ɂ���B
�@�@B)�ӎ��̗L���ɂ�����炸�A�ٕ��ɂ�钂���������^����ꍇ�ɂ́A�����ɔw���@���@����ё������������@�ňٕ����������݂�B�n�C�����b�N�@�͈ӎ��̂���W�Έȏ�̏��a�҂ɐ��������B�i�����A�V�����A�D�w�͓K�p�O�j
�@�@C)�ӎ����Ȃ��C�����m�ۂ��Čċz���Ȃ���ΐl���ċz�A����Ȃ���ΐS���}�b�T�[�W���s���B���{���ɁA�ٕ������F�ł���Γ��R�A�w�@�@�ł����o���B
�@�E�ٕ�����������A�ċz�A�z�����Ă��ӎ���Q������ꍇ�͉̈ʂ��Ƃ点�A�Q�`�R�����Ɍċz�A�z��Ԃ̊ώ@���s���B
�@�E�ٕ�����������Ă��ċz���\���łȂ��ꍇ�͐l�H�ċz���A�z�̃T�C�����F�߂��Ȃ��ꍇ�͐S�x�h�����s���B
�@�E�����ٕ̈������v�́@
�@�@A)�����ɑ��Ă͂܂��S�`�T��̔w���@�Ŗ@�����݂�B
�@�@B)�w���@�łŏ����ł��Ȃ��ꍇ�́A���̗v�̂ňٕ��������s���B
�@�@�@�菶���ō��E�̌��b���̊Ԃ��T��A�����Ē@���B
�@�@�A�����ē���Ⴍ�ۂ����܂܋�ʂɂ������̉������i���E�̓��������Ԑ��Ƌ������������镔�����w�P�{�������̋�����j�̋�����S���}�b�T�[�W�̗v�̂ŁA�P�b�ԂɂP��̊����łT������B
�@�@�B����ňٕ����o�Ȃ���Δw���@�Ŗ@�T��Ƌ��������@�T����J��Ԃ��B
���~���@
�@�E���ڈ����@�A�~���і@���厲�Ƃ��w������B
�@�E�Ԑڈ����@�͎Q�l�I�Ɏw������B
�@�E������сi�����сj�̍��ڂ�S���폜
�@�E�~���т̕����Rcm�Ƃ����B
���e�Ԋm�F�`COR�̎菇
�@�P�D�ӎ����m�F����B
�@�@�@�|��Ă��鏝�a�҂���������A�����������āA�吺�ňӎ��̊m�F�����܂��B
�@
�@�Q�D�P�P�X�Ԃ֒ʕAAED����������B
�@�@�@�Ăт����ɔ����������ꍇ�A�����ɂP�P�X�Ԃ֒ʕAAED�@�@�@���A���a�҂̂��Ɏ���܂��B
�@�R.�C�����m�ۂ��A�ċz���m�F����B
�@�@�@�C�����m�ۂ�����ԂŁA�E�ċz�����@�E�ċz�ɔ������̓���
�@�@�@�ċz�m�F�͂P�O�b�ȓ��ɍs���܂��B
�@�@�@����炪�ċG�l�Œ��Ȃ��ꍇ�́A�ċz�����Ă��Ȃ��Ɣ��f���܂��B
�@�S�D�l�H�ċz������B
�@�@�@�l�H�ċz���Q��s���Ă��������B
�@�T.�u�z�̃T�C���v���m�F����B
�@�@�@����Ȍċz
�@�@�A����
�@�@�B�̂̓���
�@�@�@���a�҂̗l�q�����Ɩڂł悭�ώ@���u�z�̃T�C���v���m�F���܂��B
�@�@�@����Ȍċz�͊m�F�ł��Ȃ����A�Ȃ�̂̓����ȂǁA���̑��́u�z�̃T�C���v������ꍇ�͐l�H�ċz�̂ݍs���܂��B
�@�U�D�S���}�b�T�[�W������B
�@�@�@�u�z�̃T�C���v���m�F�ł��Ȃ��ꍇ�A�܂��́u�z�̃T�C���v�Ɏ��M�����ĂȂ��ꍇ���S���}�b�T�[�W���J�n���܂��B
�@�@�@�S���}�b�T�[�W�͂P�T�܂��B
�@�@�@�P���ԂɂP�O�O��̃��Y���łP�T���Ĉ������A���̌�l�H�ċz���Q��s���܂��B�y������A�̓�����P�T�C�N���Ƃ���z
�@�@�@�S�T�C�N���s���A
�@�@�@�P.����Ȍċz
�@�@�@�Q�D����
�@�@�@�R�D�̂̓����́u�z�̃T�C���v���m�F���܂��B
�@�@���X�N�[���́A
���]���̐S�x�h���@�ɉ����A
�@�@AED���g�p���܂��B