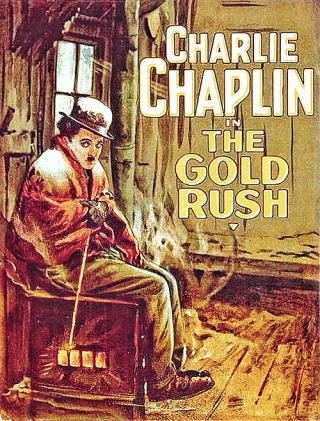
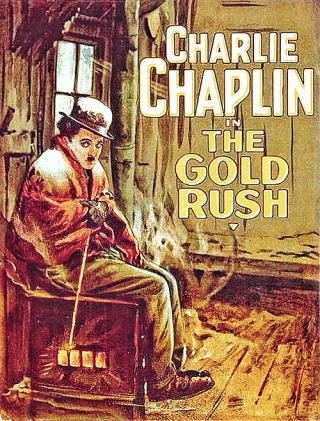
安藤佐和子&渚美智雄
安藤「この『黄金狂時代』は映画史上、最も有名な1本ですが、制作年をみてビックリしました」
渚「1925年ですね・・・昭和元年、つまり昭和100年。・・・我々は100年前に作られた映画について話してるんです」
安藤「ただただオドロキ・・・・。もちろん当時はトーキーはありませんからサイレント映画なんですが、後にチャップリン自身がナレーションと音楽をつけてトーキー版を残しました。今日、私たちが観るのはこのトーキー版ですね」
渚「チャップリン自身、それほどこの映画に愛着を持っていたんだと思いますね。チャップリンという人はサイレント映画こそが映画の純粋形で音を付けるのは邪道だと言っていたんですが、その後のトーキー映画の発展を観て、自分の宗旨を変えたんです。『黄金狂時代』はサイレント時代の代表的な傑作ですが、これだけはトーキー時代になっても残したかったんでしょうね」
安藤「いわゆるドタバタ喜劇時代のチャップリンの到達点であることは確かですね。今見ても笑っちゃいますよ(笑)」
渚「チャップリンが創造したギャグの中でも特に秀逸なものが、この映画には詰まってますからね」
安藤「特に有名なのは、お腹が減って自分の靴をゆでて食べるシーんですよね。靴ひもをスパゲッティのようにフォークに巻きつけて食べようとするシーンは最高! 思い出すだけでも笑ってしまう(笑)」
渚「机の上でシナリオを書いていて思いつくようなレベルではありません。この人は自分で演じるわけですから、撮影現場で演じながらギャグを発展させていったんじゃないでしょうか」
安藤「撮り終えてから新しいアイデアを思いついて撮り直しするみたいなことが何度もあったみたいですね」
渚「そのために、撮影期間が伸びてしまって、1年3ヶ月もかかったみたいです・・・(笑)」

安藤「完全主義者ですね。自分が納得するまで、やり直しを繰り返して・・・チャップリンがトーキー化に反対したのも、こういう手作りの世界が消えてしまうことへの危機感だったんじゃないのかな・・・」
渚「そうでしょうね。トーキーとなると、制作手順はすべて固定化し、撮り直しすればすごくコストがかかってしまいますから」
安藤「チャップリンの後、第二、第三のチャップリンが現れなかったのは、そういう映画作りの抜本的な変化ということもあったんでしょうね」
渚「楽観主義に貫かれたストーリーもこの時代ならでは・・・。アメリカの1925年(昭和元年)は得意絶頂の時代です。第一次大戦の勝利国として物凄い経済成長をしていた頃ですから。“ジャズエイジ”なんて言われますが、世の中全体がスイングしていたような時代でした。ま、今風に言えばバブルなんでしょうが・・・」
安藤「何かすれば必ず報われるという“信仰”のようなものが社会に蔓延してたんでしょうね。チャップリンという人はそういう社会の気分に非常に敏感な人でした。ゴールドラッシュの時代の大成功者を素材にした映画を思いついたんですね。ゴールドラッシュというアメリカの歴史上の“夢の時代”を面白可笑しく見せれば必ず受けるというひらめきから始まったんでしょう・・・」
渚「傑作というのは、発想された瞬間に既に傑作なんです。ああでもないこうでもないと机の上でアイデアを上塗りしていっても傑作にはなりません。かえってバラバラなまとまりのない映画になってしまいがちです(笑)」
安藤「チャップリンの映画はこれに限らず、発想(企画)段階で既に成功作だったと言いたくなる映画が多いと思いませんか? 『モダンタイムス』も『独裁者』もそんな気がしますね」
渚「天才の仕事というのはそういうものでしょうね。この人が第二次大戦後、あまり映画を撮らなくなったのは、ハリウッドから追放されたという創作環境の悪化という事情が大きかったでしょうが、“天才的ひらめき”が後退していったという事情もあったんじゃないですかね・・・」
安藤「いかなる天才も永遠に“黄金郷”に住めるわけじゃない。いかなる大成功者も永遠に“人生の黄金時代”を過ごす訳にはいきません・・・」
渚「そういう意味では、チャップリンという人は、大戦間期に巨大な花を咲かせた大スターであり稀代のアーティストでした。第一次大戦と第二次大戦の間はわずかに20年しかない。しかも極めて変化の激しい時代でした。それに翻弄された人々も多かった・・・」
安藤「特に前半と後半では両極端に振れていく。この『黄金狂時代』の4年後には、ニューヨーク株式の大暴落が起きますし、そこから世界中を巻き込む大恐慌の時代が始まる・・・」
渚「『モダンタイムス』は資本主義社会の矛盾を風刺した大傑作ですし、この大恐慌下で生まれた独裁政治を徹底的に批判した『独裁者』は史上最高の反戦映画の金字塔です」
安藤「時代が悲劇的状況になったとき、表現者は何をすべきなのか、ということをチャップリンは考えたんでしょうね。『黄金狂時代』のような調子のいい楽天主義は通用しないという」
渚「『黄金狂時代』の製作が5年遅れていたら、この映画はここまで成功しなかったかもしれない。チャップリン映画は大衆と共にあり、その歓びや哀しみと共にあった。第二次大戦後は、そのあまりの惨禍にチャップリン自身が平衡感覚を失ったんでしょうね。最大の問題作、『殺人狂時代』はそういう時代の産物なんです(笑)」
安藤「そのあとは、自分の原点である芸人としての半生を振り返るような『ライムライト』という自伝的名作を撮ったり・・・“喜劇の王様”という自分のレッテルを抑制的にしていきます」
渚「『ライムライト』があれほど観客を泣かせたのは、チャップリンの人生の労苦がにじみ出ているからです」
安藤「『黄金狂時代』と対照的なのね。私たちは、その後のチャップリンの人生を知っていればこそ、『黄金狂時代』には大成功者となった達成感と自芸に対する自信を感じて感慨を感じますよね。そういう映画だからこそ、100年たっても世界中の喜劇ファンが笑い転げるのね・・・。最もハッピーな映画と言えるかもしれないわね」
渚「あの映画の中のチャップリンは、どの映画よりも過酷な目にあって苦労してるんですけれどね(笑)」

安藤「一種のマゾ芸ですよ(笑)。それとチャップリン映画の中ではスケールが大きい。ゴールドラッシュをテーマにしても、西部じゃなくて舞台をアラスカにしてますからね・・・自然の過酷さが際立ってくる。私は特に山小屋が強風に吹かれて絶壁の際まで移動してしまうギャグが最高に好きです」
渚「安藤さんは、チャップリンとは逆にサディストの気がある?(笑)」
安藤「チャップリン映画に笑い転げる観客は皆、サディストなんじゃないのかな・・・。あんなひどい目にあうチャップリンを観て、自分の今の状況はまだましだと思い、映画を観終わったあと、素直に苦労したものほど大きな成功をつかむのだというメッセージに勇気づけられる。世界中の大衆の人気をさらった理由はそういうことでしょう」
渚「邦題の『黄金狂時代』も良いですが、今なら『大成金時代』かな・・・。もっとも今の大富豪たちは金融資産を太らせて儲けた人ばかり・・・チャップリンのように“働いて働いて働いて”成金になりましたという訳じゃない。チャップリン映画の楽しさは、汗水たらして働く姿とそれが報われる幸福なオチにある。だからこそ人々をいつまでも、こんなにも幸福な気分にしてくれるのです・・・(笑)」