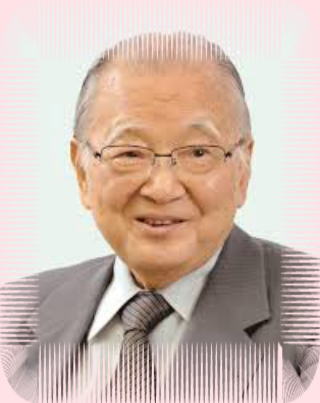
葬送エッセイ
さようなら ありがとう
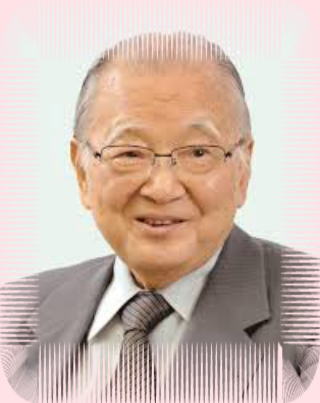
故不破哲三さん
今から36年前、激動の昭和が終わった年には、昭和という時代を支えた多くの著名人が、まるで昭和天皇を追うように鬼籍に入ったことを思い出す。松下幸之助、手塚治虫、美空ひばり・・・。
時代は平成から令和へと移り、昨年は“昭和100年”という言い方が流行った。苛烈な戦争の時代から一転して高度成長の栄光に続きバブル景気の狂奔に終わった昭和は、“失われた30年”と言われる後代を見ずに終わったが、歴史上、極めて特異で劇的な変転に彩られた時代だったことは間違いない。
その昭和100年にもまた、多くの著名人が世を去った。それぞれ戦後の昭和の輝きを担った人達であった。
中でも、左翼系政党の大きな節目を作った二人の政治家の訃報は感慨深いものがあった。10月に101歳で逝った村山富市氏(社会党党首にして日本国首相)・・・共産党の指導者として冷戦後の党の行き方を方向づけた不破哲三氏は、村山氏を追いかけるかのように二か月余り後の12月30日に逝去した。95歳。いずれも堂々たる大往生だった。まるで昭和100年の節目に合わせるかのような最期。戦後の政治史を考えるうえでも欠かせない二人が、昭和100年の同じ年に世を去ったことになる。
社会党と共産党。日本政治の左派を代表する二大政党の終戦後の歩みは対照的だった。共産党は戦前から党を率い戦中は政治犯として監獄に捉えられ、米軍に進駐されるや自由の身になった立場から、米軍を“解放軍”とみなした錯誤は、共産党のその後の行き方に混乱を与えた。
その後の中国の毛沢東に影響された“山村工作隊”といった武力革命の準備に注力したあげく、ソ連のスターリン逝去後に後継者のフルシチョフによってなされた“スターリン批判演説”で、日本共産党は梯子を外されたような状態になった。一方の社会党は、社会科学を基盤にした党運営によって“理論の左派政党”として、大衆の信頼を勝ち得ていった。
今思えば、1955年(昭和30年)こそは、戦後政治の大転換だった。保守二党が合併して自由民主党が生まれ、社会党と二大政党的な構図を形成した“55年体制”において、日本共産党は寄る辺なき衰退政党になったといってもいい。そこから武装闘争路線を大転換し、宮本顕治氏(元委員長)のもとで崩壊の危機を乗り越えていった。
戦後政治の次の巨大な節目は、左翼政党の思想的後ろ盾となっていたソ連の崩壊(1991年)による冷戦の終焉である。まさしく90年代は世界的構造転換のなかで暗中模索の政治状況に陥った。“失われた30年”は何もバブルの崩壊だけが原因ではない。政治の混迷にも根本的な要因があった。自民党の狡猾な党略によって日本国総裁に祭り上げられてしまった社会党の村山富市氏は、立場上、自衛隊を容認し天皇制すら肯定せざるを得なくなった。結果として社会党の“根幹思想”を放棄することになり、党は急速に党勢を失っていく。
このとき、共産党に新世代の優れたリーダーが登場した。不破哲三氏である。東大物理学科卒業の理系エリートとして鉄鋼労連を舞台に主として理論による指導力を鍛えていった。党理論誌『前衛』に初寄稿した『民族解放民主革命の理論的基礎』において使用したペンネームが“不破哲三”だった。それ以降、常に共産党の理論的支柱であり続けた。党綱領を改訂し、“マルクス・レーニン主義”という表現を避け、2000年代に入ると、天皇制容認を打ち出し、国民世論の多数派との乖離を避けた。一方、ソ連崩壊で世界中のほとんどの共産党が党名変更に踏み切る中、断固として“日本共産党”の党名は堅持する道を選んだ。必要なのは党名変更ではなく、党の存在理由を示す綱領の再定義であると訴えた。
結果、日本共産党は昭和100年を過ぎても、日本の代表的左派政党として存続し続けている。但し、立憲民主党や国民民主党といった野党勢力に押され、その存在感は大きくはない。政局に振り回される日本政治の波動の中で、今一度、“理論の政党”としての国家ヴィジョンを再構築し訴求力を復活させねばなるまい。
不破哲三氏は常に言い続けた。『政治状況はすべて理論で説明できるものだ』と。不破氏が存命なら、今日の高市解散をどう理詰で説明してくれるだろうか。最近まで自民党と組んでいた公明党が一転して野党第一党の立憲民主党と組み、『中道革新連合』なる新党を立ち上げた。“中道”という言葉は、左派勢力と右派(保守)勢力の対決が鮮明な時代にこそ意味を持つのであって令和の時代に理解する人は多くあるまいと思うが・・・。こういう安直で政治哲学を持たない独善的な政界の動きを、さすがの不破氏も、ただただ苦笑するだけかもしれない。
政権と対峙するには、与党以上に明確な理論武装が要ることを、『中道革新連合』の幹部は肝に銘じねばなるまい。理論派左派政党の確固たる存在こそが民主政治を健全化させる不可欠な要素であることを、不破哲三氏は、これからも思い出させてくれるに違いないのである。