映画/演劇/鑑賞記録
映画「新あつい壁」の特別試写会(東本願寺にて)。ハンセン病問題に関連した菊池事件をあつかったもの。菊池恵楓園内の特別法廷で開かれた裁判で、公正な審理が行われたのか疑わしいとされている菊池事件のあらましがよくわかる。冤罪ではないか、という疑いもこい。この映画の普及活動がこれからはじまる。(2007/6/9)
映画「しゃべれども、しゃべれども」。1997年度“「本の雑誌」ベスト10”の第1位に輝いた佐藤多佳子の長編小説を映画化。監督は『愛を乞うひと』で日本アカデミー賞を受賞した平山秀幸。主人公の落語家をTOKIOの国分太一が演じる。けっこう面白い。演じられるのは古今亭志ん生で有名な「火炎太鼓」。(2007/6/1)
映画「パッチギ! love & peace」(2007/5/26)
映画「東京タワー」(2007/5/18)
映画「スパイダーマン3」(2007/5/6)
映画「ラブソングができるまで」(監督マーク・ローレンス=『トゥー・ウィークス・ノーティス』、すっかり人気のなくなった80年代のポップスター、アレックス役にヒュー・グラント、作家志望の女性ソフィーにドリュー・バリモア)。軽いタッチのラブコメディ。ヒュー・グラントがまたもダメ男役だが、今回は最後に恋も成功もかちとってハッピーエンド。
映画「クィーン」。(監督=スティーヴン・フリアーズ、女王役=ヘレン・ミレン)1997年8月31日の交通事故からダイアナ元妃の国葬が執り行なわれるまでの数日間の英国王室、エリザベス女王を描く。女王の夫君はかなり「悪役」に描かれていたり(さすがに息子2人には何も語らせないが)、どれだけ事実なのかフィクションなのか、わからないけれど、王室を題材にこれだけの政治映画をつくったことに、そして、この映画を1つの「表現」として発表させる社会に感心した。(2007/4/28)
映画「バベル」。(監督はメキシコ人のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ)題名は「神は、人類が大それたことをしないよう、言葉を別々にして、人々をバラバラにしてしまった。」という旧約聖書のバベルの塔の話から来ているとか。モロッコ、メキシコ、アメリカ、日本を舞台。モロッコを旅行中に銃撃されるアメリカ人夫婦リチャードとスーザンにブラッド・ピットとケイト・ブランシェット。東京編には聴覚に障がいを持った女子高生のチエコ(菊地凛子)の奇怪な行動が描かれる。3つの「つながり」を映画を見終わったあとに必死に考えた。「家族のつながり」みたいなことが共通項かな? モロッコ編がその風景といい、人々の暮らしぶりといい、一番心にせまってきた。ただ騒がれているわりには・・・・という印象。(2007/4/29)
映画「ブラッド・ダイヤモンド」(監督エドワード・ズウィック。ダイヤの密売人ダニー・アーチャー=レオナルド・ディカプリオ、漁師ソロモン=ジャイモン・フンスー。ジャーナリストのマディージェニファー・コネリ)。1990年代後半のアフリカ、シエラレオネでの激しい内戦が舞台で、深刻な内戦の争いを描く。その争いの裏にある“ブラッド・ダイヤモンド”というダイヤモンドの不正な取引。ベルギーのダイヤモンド会社の関わりや南アフリカの傭兵などを教えられた。アフリカの現実を学べる、けっこういい作品。「ロード・オブ・ウオー」「ホテル・ルワンダ」や「ナイロビの蜂」につづいて、アフリカの現実を告発するすざまじい映画でした。少年兵問題を直接扱っているので、目をおおいたくなるようなシーンがでてきた。知り合いには「DVDになってから部屋を明るくして自宅で見た方がいいかも。」と助言した。(2007/4/22)
映画「オール・ザ・キングスメン」(監督スティーヴン・ザイリアン、主演ショーン・ペン(=政治家ウィリー・スターク)、ジュード・ロウ(=ジャーナリストのジャック・バーデン))。スタークのモデルはルイジアナ州知事のヒューイ・ロング(1928年から32年まで知事をつとめ、その後、上院議員。1935年大統領選挙に立候補し活動中に暗殺された)。富を分配し、格差を是正しようと訴えて、社会下層の勤労者層から支持を受ける。映画での演説ぶりは、かのヒトラーを思い浮かばせるものがある。そういえば、同じ時代に生きた人か。(2007/4/20)
映画「ブラックブック」(監督ポール・ヴァーホーヴェン)を見る。オランダにおけるナチス抵抗運動の中の女性エリス(カリス・ファン・ハウテン)を追う。密告で家族を全員殺されたエリスは、レジスタンスに加わるが、命令で、ナチスの情報将校の「女」になり、情報を盗む。いったんは成功するかにみえた人質救出作戦も「罠」だったことがわかる。そこで、エリスはナチスとつながっていたようにはめられてしまう。解放後、実は本当のスパイが誰だったのか、わかる。解放がけっして「すべてよし」というわけではなく、むしろ解放した連合国側のリンチのひどさなども描かれている。サスペンスというより、戦争の悲惨を人間関係から描いた秀作。(2007/4/15)
映画「ホリディ」(監督ナンシー・マイヤーズ)。ロスとロンドン(サリー)に住む、恋にやぶれた2人の女性(アマンダ=キャメロン・ディアス)とアイリス=ケイト・ウィンスレット)が「ホームチェンジ」して、新しい恋をみつけるというラブコメディ。ロンドン編はイングランドの美しい田園が舞台。ロス編には、かつての名脚本家の話がはいって、映画として厚みがでている。(2007/4/7)
映画試写会「ボビー」。1968年6月4日(?)のロバートケネディ暗殺の日に、その現場となったロスのアンバサダーホテルに宿泊し、暗殺者の流れ弾があたった人、ホテルマン、歌手、引退した人などを中心に描く。ボビーは、実写フィルムと顔もはっきりしないわずかのシーンにしか登場しない。だから前半は雑多なシーンばかりで映画の筋がいったいどんなものかわかりにくい。最後の暗殺のところでようやくかろうじてつながりがわかる。映画的な盛り上がりがなく、評価が低いだろう。(2007/3/2)
映画「不都合な真実」。映画「不都合な真実」。最近話題の作品、今年、ドキュメント部門でアカデミー賞を獲得した。ゴアの地球温暖化、環境破壊のシナリオ講演を映像化したもの。たしかに地球温暖化、環境破壊の現実を映像でみせられると驚きもするが、それほど新しい視点があるわけでもない。米国人にはあれで新鮮なのだろうか? (2007/3/1)
映画「ドリームガールズ」。ショービジネスに生きる3人組の女性トリオ、辣腕マネージャー、歌手などのからみを描くミュージカル。音楽もテンポもよくてなかなかの出来だと感じた。(2007/3/11)
「ラストキング・オブ・スコットランド」を見てきた。アフリカはウガンダのアミン大統領の話。すさまじい虐殺シーンがある。ただ「ナイロビの蜂」「ホテルルワンダ」などアフリカの現実をしっかり見つめようとする映画がでてきたのは、とても重要な動きだと感じた。(2007/3/17)
「グッドラック&グッドナイト」(G・クルーニー監督、主演もかねる)マッカーシーの実写フィルムを交えて、CBSのニュース現場における報道陣のシーンしかでてこない白黒映画。しかし、それがけっこうな緊張感をもたらしていた。ジャズの音楽もいい。報道局長役のG・クルーニー、エド・マロー役のデビッド・ストラザーンも好演。CBSのマッカーシー批判のシーンのもたらす緊張感もいい。
映画「歓びを歌にのせて」(スェーデン映画・監督 ケイ・ポラック )。天才指揮者のダニエル(ミカエル・ニュクビスト)は、あるとき舞台で倒れてしまう。現役を退いた彼は幼少時代を過ごした村に戻り、レナ(フリーダ・ハルグレン)ら教会の聖歌隊のメンバーと知り合う。コーラスを通じて、人々の心が充たされていく。同時にダニエルも愛を知っていく。なかでもアルコール中毒の夫によるDVに耐えかねて、家をでたガブリエラ(ヘレン・ヒョホルム=スウェーデンで有名な歌手とか)が、聖歌隊のコンサートで歌うソプラノがとても透き通った印象で美しかった。思わず涙がでてしまいそうに。ただこの映画、たんなる音楽映画だけでなく、DVやダニエルを追放しようとする牧師の偽善と家庭内の対立、奔放な異性関係をつづけるレナに対する地域の非難とか、いろいろな問題をふくむ社会派映画。
映画「白ばらの祈り」(マルク・ローテムント監督、ユリア・イエンチ(ゾフィー・ショル)主演)。ナチスに抵抗したミュンヘン大学の学生の物語。抵抗運動としては「すき」だらけで、兄妹ほかはつかまってしまう。法廷のシーンが圧巻。でもゾフィーは普通の女の子だったんだと、最後の実写を見て、考えさせられた。どうして、日本映画はこういう素材を作れないのだろう。つくっても、どうしてもナレーションつき「解説」映画になってしまう(残念だけれど昔みた映画「小林多喜二」がそんなかんじ)。感じる映画としてつくることができないというか。
映画「ホテル・ルワンダ」。アフリカのルワンダにおける民族対立の結果の大虐殺を描く。そこで多くの命をすくったホテルマンが主人公。鹿児島でやらなかったので、宮崎の映画館でみた。いま世界で起きていることを映画で教えられた。アフリカについてほとんど知識がなく、かつて南アフリカのアパルトヘイト反対を描いた「遠い夜明け」以来。
映画「かもめ食堂」。フィンランドの家庭料理屋を舞台にした作品。これといって盛り上がる場面や激しいラブシーンがあるわけでもなく、淡々と日常を描く。そこがこの映画の魅力か。福岡/天神でみた。
映画「ナイロビの蜂」(監督フェルナンド・メイレレス、主演レイフ・ファインズ、レイチェル・ワイズ)。ケニアの自然が美しい。行動派のテッサはどんどんアフリカにいって、そこでの薬品会社と英軍、政府との癒着を告発する。そして消される。妻テッサの協力者アーノルド医師も虐殺されてしまう。その妻の行動を知ろうと外交官の夫がその秘密をつきとめていく。そして最後には。アフリカのどうしょうもない貧困が映画をとおして知らされる。ケニアのスラム街のすごさ。暴力のすさまじさ。
映画「シリアナ」。中近東を舞台にした政治的なテーマを扱った映画。サウジの王家の中の争い、暗躍するアメリカCIA、皇太子を支援する銀行マン、2つの石油会社の合併にたずさわる弁護士、イスラム原理主義にひかれる移民労働者と何人かの人物の絡み合いがあって、やや難解。ドラマ仕立てでなく、たんたんとドキュメンタリーのように描いているところがみそか。
映画「雪に願うこと」(監督根岸吉太郎、伊勢谷*主演。ほかに小泉今日子、佐藤浩市ほか)
「嫌われ松子の一生」(監督中島哲也監督、主演中谷美紀)。ある女性(松子)の転落の一生を描く。しかし、松子はみんなに愛されていたことがテーマ。CGを交えた画像、けっこう、このテンポは面白い。
DVD「下妻物語」(深田恭子主演)ロリータ趣味の少女(深田)と女暴走族のこころのふれあいを描く。見る前は、軽い、内容のない映画かと思ったら、けっこうリズム感があって、2人の心と心のふれあいまで描いて、けっこうひきつけられた。映画評も高いのもうなずける。
DVD「モンスター」(シャリーズ・セロン主演)7人の「客」を殺害し、のちに死刑になった実在のコールガールをモデルにした映画。彼女がなぜ「客」を殺さざるをえなかったのか。カネとひきかえに非人間的な行為を要求し、ばかにし、罵倒する「客」たち(「はじめて」といって、彼女に心やさしく接した客には彼女は殺意をしめさなかった)。怒りの中で発射される銃弾。社会のなかで最低辺に生きる女性の悲劇を描く。その中で知り合った唯一心を許せる相手(レズの関係)としてのセリーズの存在も描かれる。世間から「モンスター」と呼ばれた彼女の内心に迫ろうとする力作だ。14キロ体重を増やし、シミを強調するために独特のメーキャップをし、眉毛まで剃り落としたシャリーズ・セロンがすごい(2003年アカデミー主演女優賞)。
映画「プルーフ・オブ・マイライフ」(監督 ジョン・マッデン、主演グウィネス・パルトロー 、アンソニー・ホプキンス 、ジェイク・ギレンホール 、ホープ・デイヴィス 、ダニー・マッカーシー)。キャサリン(グウィネス・パルトロウ)は天才数学者の父(アンソニー・ホプキンス)を亡くし、失意の底にいた。そんな時父の教え子のハル(ジェイク・ギレンホール)が、遺されたノートを見に訪ねて来る。
映画「スタンド・アップ」(監督 ニキ・カーロ、出演 シャーリーズ・セロン 、フランシス・マクドーマン)。
夫からの暴力(DV)に耐えかね、離婚して故郷の北ミネソタに帰って来たジョージー(シャーリズ・セロン)は2人の子供を抱え給料の高い鉄鉱山で働くことを決心する。しかし、女性をはじめて労働者として迎えいれた、その職場には想像を絶するような男性社員からのわいせつなことば、性的な暴力、嫌がらせが待ち受けていた。彼女は社長と掛け合い、なんとか職場環境を変えようとするが、まわりの男性から総スカンをくい、女性たちも及び腰になっていく。しかし、彼女は裁判で訴える。組合員集会でもいんわいなやじが浴びせかけられる。そのとき、父親がはじめて娘を援護する。裁判の法廷で、彼女の男遍歴があきらかにされようとするが、反対に彼女が教師によってレイプされたことが明らかになる。そして、一緒に裁判に原告となって争う仲間がひとりひとり立ち上がる。まず筋萎縮症に冒された*、さらに職場でひどいセクハラをうけたジャーリー、そして父親、男の同僚もまた立ち上がる(スタンド・アップ)。
レイプ、DV,セクハラと女性に対する人権侵害を正面から扱った力作である。組合員集会、法廷のシーンもいい。
(2月)
市民劇場「ドライビング・ミスデイジー」(無名塾と民芸のコラボ・県文化センター)
席も前のいい席で、時間も1時間45分と短く、楽しめた。仲代達也と奈良岡朋子という名優が、アメリカ南部のお金持ちの老婦人とそれに仕えるアフリカ系の従僕を演ずる。その心がすこしずつふれ合って老境を迎えていくさまがなんともいい。仲代は好演とみた。これまでの「リア王」みたいな堂々さでなく、人のいい老人をうまく表現している。
映画「博士の愛した数式」(小泉堯史監督)。天才的数学者の博士(寺尾聡)は、兄嫁(浅丘ルリ子)と恋におち、薪能を見学したあとの事故で、80分しか記憶がもたない人間になってしまう。そこに家政婦に頼まれた女性(深津絵理)は、同じことばを繰り返す博士だが、その語る数学のさまざまな不思議にふれる中で、その人間味を感じていく。ルートとあだ名された息子もふくめ、3人のふれあいが美しい光景(桜並木や夕日、海)の中で描かれる。後に高校の数学教師になったルート(吉岡秀隆)が語る数の不思議と博士の思い出が映画のナレーションとなってすすめていく。「素数」「約数」「友愛数」「完全数」など数の定義と意味・相関がけっこう興味深い。数学科をこころざす知也にみせたかった。
映画「ミュンヘン」。ミュンヘンオリンピックでイスラエルの選手団が選手村で人質になり、搬送途中の空港で虐殺(犯人たちも銃撃戦の末、射殺された)された事件をうけて、イスラエル政府は「報復殺人」を決定し、秘密警察モサドを通じて、アヴイーにその暗殺者役を命令する。よき父親であった彼が、一転、欧州各地にいるミュンヘン事件に関与したアラブ過激派を殺しにいく。爆破、射殺とすさまじいばかりのシーンがつづく。けっこうこわい。その中で彼はこういう「報復の連鎖」に対して疑問を投げかけ、新しい任務に戻ることを拒んでいく。最後の拒絶シーンをNYのブルックリンにし、かなたに世界貿易センターを望ませているのは、スピルバーグのメッセージである。
映画「フライトプラン」。大型飛行機の中で突然娘が行方不明になる。しかし、そのことに誰も気づかず、かえってすでに死亡していると、母親(ジュディ・フォスター)を精神病者扱いで危険視する。そこで必死に機内を探すが、結局、機内にいる捜査官につかまってしまう。着陸して逮捕寸前になったところで、一転、犯人が浮かび上がる。そして、その犯人との機内での格闘。娘を抱いた母親の姿に、乗客、CAなどはそれまでの態度を一変させる。前半は誰が犯人、どこが犯罪なのかはっきりしないサスペンス(レスたー博士を思い出させる)、後半になって、犯人がみずから明かしてしまうあたりは、ややがっかり。あのシーンは余分では。
映画「オリバーツイスト」(ポランスキー監督)。19世紀末のイギリス・ロンドンの暗い雰囲気を再現している。ただオリバーが活発に動いて、危機をのりこえていくといったものでなく、回りのいろいろな人の中でなんとなく消極的・受動的。だから映画の筋としてあまりドキドキするようなところはなく、やや暗さのみが残る。評価は3・5。
映画「ジャーヘッド」(監督サム・メンデス)。海兵隊に入隊したスオフォード(ジェイク・ギレンホール)がまず隊でうけるしごき。この辺は軽いいタッチ(音楽もポップ系)。しかし、湾岸戦争が勃発して、クゥェートに派兵されて、一気に緊張が高まる。米軍によって攻撃されたイラク車両に残る真っ黒にこげた死体、油田が爆破され、あたり一面黒い雨が降る。真っ赤になった夜空に照らされた中で真っ黒になった馬が1頭さまよう。画面としても赤で美しい。それだけに戦争のすさまじさが伝わってくる。主人公の属する海兵隊員は結局だれひとり殺すことなく終わるが、彼らはなんのための戦争かを思い知らされる。りっぱな反戦映画。こういう映画をつくることのできるアメリカ映画界は奥が深いと思わざるをえない。
映画「イン・ハー・シューズ」。ちょうど毎月1日の「映画デー」だったこともあって、けっこう人がいた。
「in a person's shoes」とは、辞書で調べたら、「人の立場に立って」という意味だそうだ。遊び人の妹(キャメロン・ディアス)としっかり屋の姉(トニー・コレット)。それぞれ私生活でも仕事でもいろんな悩みをかかえている。そして、姉の家にころがりこんできた妹の起こすトラブルに、つい姉は切れて、追い出してしまう。妹は、祖母のいるフロリダに向かい、そこではじめは金をたかるつもりだけだったのが、老人ホームの人々とふれあう中で、自分を取り戻していく。姉は、不倫相手と別れ、職場の同僚と恋をする。しかし気がかりは妹のこと。二人はふたたび老人ホームで出会う。互いを理解し合っていくことの大切さを教える。キャメロン・ディアスが「あほ女」からすこしずつ変わっていく様を好演。女優らしくなってきた。
映画「sayuri」をmitte10に妻と観に行く。芸者の置屋に売られた少女(成人してからチャン・ツィ・イー)が、ふと出会った紳士(渡辺謙)といつか出会うことをしんじて芸者になり、芸者同士の裏切り、葛藤のなかで、その紳士と結ばれていくという物語。スピルバーグが製作(プロデュース)した映画だが、アメリカ人のつくる日本はいつもけったいなものになって、当の日本人には違和感をひどく感じさせる。花街の風景しかり、農民の家しかり、芸者学校の風景しかり。筋的にはけっこう関心のもてるものなのに、その違和感が先行してしてしまうのが残念。
DVD「北の零年」。淡路島にいた武士たちがお家の都合で北海道に渡り、困難な中、開拓のいどむ。その中で先頭にいた小笠原は、所用ででかけて行方不明となり、数年後に政府開拓使の役人となってかえってくる。そこでのこされた妻(吉永小百合)と娘との再会する。
DVD「ザ・インタープリテーター」。国連の通訳ジュリアン・フィルマー(ニコール・キッドマン)はある夜、偶然、アフリカのある国の大統領暗殺計画を聞いてしまう。シークレットサービス(トニー・ベン)は彼女が暗殺者ではないか、とうたがう。実際、彼女の家族はその大統領一派に殺されていた。その彼女の周辺におきる奇っ怪な事件、爆破。そして、国連総会で大統領が演説する日、しくまれた暗殺未遂事件が起きる。その中で彼女は大統領に迫っていく。国際政治を背景にした、サスペンスもの。はらはらどきどきする。
「ラヴェンダーの咲く庭で」をシネシティ文化に妻といっしょに見に行く。チャールズ・ダンス [初監督作品]。ジュディ・デンチ(アーシュラ役)、マギー・スミス(ジャネット役)、ダニエル・ブリュール(アンドレア役、どこかで観たと思っていたが、ベルリンの壁崩壊を描いたドイツ映画「グッバイ!レーニン」にでてきた男優)。舞台はイギリスのコーンウォール(南西部の半島)地方。そこに暮らす二人の初老の姉妹と、どういうわけか岸辺に流れ着いた青年アンドレアのふれあいを描く。
初老の女性アーシュラが、年齢の差を超えて、青年にいだく秘めた「恋心」。それを名女優ジュディ・デンチ(「恋におちたシェークスピア」で女王エリザベス一世役をやった「ショコラ」で子どもと離れて暮らす大家の役)がとても真に迫った演技でえがく。言葉ではいえないので、それを目とか、髪の毛をとかす動作の中に表している。
バイオリンの天分を認められ、ロンドンにでてアンドレアが演奏するシーンの音楽がなかなかすてき。(吹き替え)その演奏会にでかけてアンドレアに会い、脚光を浴びる彼に別れをつげることもなく、またコーンウォールに戻っていく二人。はでな演出とか、大がかりなシーンはないけれど、いかにもイギリス映画らしい小品。
市民劇場「銃口」(前進座・三浦綾子原作)。青年教師北森が、教師になり綴り方教育に薫陶して、弾圧をうける。そして徴兵で中国へ。敗戦により帰国、ふたたび教師に戻るまでを描く。やや堅いところもあるが、私はしっかりとかつて戦争と教育・社会のありかたを見つめるこの姿勢をしっかりとうめとめたい。
映画「メゾン・ド・ヒミコ」(監督、柴咲コウ、オダギリ・ジョー主演)。老齢を迎えたゲイたちのホームの物語。「卑弥呼」のママは、さおりの父親。さおりは父親に反発しながら、その最後をみとり、ゲイの人間性にふれて心ひらいていく。テーマがやや特殊だが、柴咲コウが町の普通の娘をうまく演じる。
DVD「父と暮らせば」(黒木和雄監督)を借りる。二度目だが、いい作品だと改めて思った。宮澤りえがすてき。おそらく被爆直後のヒロシマにあのような美しく化粧した娘がいたとは想定できないが、その娘の美しさが絶望の中の希望を表しているのかもしれない。
DVD「血と骨」(崔洋一監督、北野たけし主演)。「怪物」と呼ばれた在日朝鮮人のすさまじい半生を描く。はげしい暴力シーン、性描写(ぼかしが入った)もあり。たけしの演技の「稚拙さ」については評価がわかれるだろう。あういう素人演技だからかえってこの人物がリアルになった側面もあるかもしれない。日本映画にめずらしい歴史的スケールの大きさがある。最後の北朝鮮でのシーンはあくまで想像の産物。
映画「ヒトラー〜最後の12日間〜」(オリヴァー・ヒルシュピーゲル監督、ブルーノ・ガンツ(ヒトラー)主演)を観る(20時20分から)。ベルリン陥落直前の地下にある総統府を描く。ヒトラーの狂気、側近たちの腐敗・酩酊、幹部家族の悲劇、それに外の一般市民や兵士の悲惨さも描かれる。ヒトラー夫妻、ゲッペルス一家の最後など知識では知っていたが、その凄惨さに驚かされた。ドキュメンタリーに近い作品。ナチス打倒50年を記念してつくられた。最後にこの原作を書いた元秘書が「白バラ」のゾヒィー・ショルを語っているところにその意思が伺える。こういう映画をつくろうというところに「非戦」の気概をみる。
映画試写会「always 3丁目の夕日」(吉岡秀隆主演)。有名な西岸良平の漫画が原作。ちょうど自分のこどものころが舞台。主演のこどもたちは同年齢だ。映画の進行とともに東京タワーが建設され、すこしずつ完成していく。売れない小説家・茶川竜之介と突然まいこんできた古行淳之介とのふれあい。鈴木オートの一家に集団就職できた少女(六子)の苦悩、など人間味豊かに描く。まあ中高年向きということか。
映画「シンデレラマン」(ラッセル・クロウ、レニー・ゼルウィガー主演、監督ロン・ハワード。)実在のアメリカ人ボクサーの物語。成功したボクサーが一九二九年の大恐慌で破綻する。一時は生活保護をもらうまでに落ち込んだ彼が、世界チャンピオンになるまでの物語。大恐慌で危機にあった当時の社会が背景に描かれていて、当時の様子が伝わってきた。ただし、ボクシンング映画としてはもっと出来のいいものがあるような気がする。やや甘い。
試写会「蝉しぐれ」(藤沢周平作の長編時代小説を市川染五郎主演で映画化した時代劇映画。監督は『英二』の黒土三男)。山田洋次監督の「たそがれ清兵衛」「隠れ剣 鬼の爪」と藤沢周平3部作みたいになり、ヒラ侍の生活苦、そこにかかわる女性たち(これまでは宮澤りえ、松たかこ、今回は木村佳乃)、藩内の争い、斬り合い(果たし合い)とおなじような主題があつかわれている。「蝉しぐれ」は。初恋からつづく愛という主題が一番つよくでている。初恋相手でのちに藩主の側室になるふく(木村佳乃)と会うところの最後の涙のシーンが印象的。しっとりとした作品にしあがっている印象。映像的にもきれいな場面が多々ある。
ミュージカル「アスペクト・オブ・ラブ」(劇団四季)。女優ローズをめぐるアレックスとジョージの三角関係。そこにジェーンというローズの娘がからんでくるから相関図が難しい。一幕目はそれほどのシーンがない(汽車の中で歌うところくらいか)が、二幕目のジェーンとアレックスの踊りのシーンがきれい。それにジョージの葬式のところも。アンドリュー・ロイド・ウェーバーの作品としては、「オペラ座の怪人」「エビータ」などと比べて小振りな作品に仕上がっている。そういう志向の変化を示したものなのか、それともやはり衰えなのか。あまり音楽も印象的な曲がないような気がするが。
映画「クレールの刺繍」(フランス映画・カンヌ国際映画祭批評家週間でグランプリを受賞した、エレオノール・フォーシェ監督のデビュー作。「匿名出産」を題材に、フランスの片田舎に住む少女の葛藤を描いた。主演のローラ・ネマルク)。それほど感動的な場面はないが。フランス映画らしく、淡々と人の心の動きを写す。
映画「容疑者・室井慎次」(『踊る大捜査線』スピンオフ企画第2弾。主演。柳葉敏郎演じる室井慎次を主役にしたクライム・サスペンス巨編。若き女弁護士役に田中麗奈、徹底的に室井を追い詰める弁護士に八嶋智人。)やや現実感にとぼしい作品。そもそも、なぜ室井が容疑者になるのかが不可解。
黄金週間はレンタル・ビデオでのんびりと、とはいかなかったけれど。(2005/05/10)
映画「ヴェロニカ・ゲリン」(ケイト・ブランシェット主演)。
1996年6月26日に麻薬密売組織によって暗殺された、アイルランドのジャーナリスト(サンデー・インデペンデント紙記者)ヴェロニカ・ゲリンの取材から暗殺までをえがく。実話を映画化したもの。
女性記者ゲリンは子どもたちまでまきこんで麻薬の密売が横行していることに憤慨して、その元凶がだれか追求していく。そしてとうとうその人物に接近する。すると、自宅には銃弾がうちこまれ、クリスマスイブの夜には、あやうく殺されそうになり、足に傷を負う。それでもその元凶の自宅まででかけていって、ひどくなぐられる。そして、その男相手に訴訟を起こす。相手からは金の支払いという取引条件が示されるが、拒否。組織はとうとう彼女が交通違反で裁判所に出かける日をつかみ、二人のヘルメットをかぶった男がオートバイで彼女の赤い車を追いかけ、ちょうど信号で停止した道路上で拳銃によって暗殺する。
彼女の死後、アイルライドでは世論がもりあがり、麻薬取引を禁止し、その収益によって得られた財産を没収する法律がつくられた。犯人たちも逮捕され(仲間の名前を自白させるかわりにその身の安全を当局が保証する証人保護システムによる、と映画にでてきた)、刑に処せられた。
見ていて、ひとりで取材する方法はずいぶん危険だなと思ったし、危険を察知できなかったかとも思う。イギリスの新聞のスクープは往々にしてひとりの記者と情報提供者との関係から生まれるが、反対にそこに大きな危険もついて回る。こういう硬派のテーマを映画化する英米の映画界に感心する。なかなかいい映画だった。
見終わった後、車を運転した。隣にオートバイが寄ってきて・・・なんてことにならないか、とすこしこわくなった。
DVD「白いからす(原題はthe Human Stain」(アンソニー・ホプキンス、ニコル・キッドマン主演)。はじめは大学の人種差別発言で失職した老教授と、人生につかれはてた感じの放浪する女性との恋愛をベースにすすむのかと思ったが、後半になって、彼のかくされた過去/出生の秘密が明かされていく。
アメリカにおける人種差別の根深さを、別の角度から描いた作品。これまた、なかなかいい。
黄金週間はレンタル・ビデオでのんびりと、とはいかなかったけれど。(2005/05/10)
映画「ヴェロニカ・ゲリン」(ケイト・ブランシェット主演)。
1996年6月26日に麻薬密売組織によって暗殺された、アイルランドのジャーナリスト(サンデー・インデペンデント紙記者)ヴェロニカ・ゲリンの取材から暗殺までをえがく。実話を映画化したもの。
女性記者ゲリンは子どもたちまでまきこんで麻薬の密売が横行していることに憤慨して、その元凶がだれか追求していく。そしてとうとうその人物に接近する。すると、自宅には銃弾がうちこまれ、クリスマスイブの夜には、あやうく殺されそうになり、足に傷を負う。それでもその元凶の自宅まででかけていって、ひどくなぐられる。そして、その男相手に訴訟を起こす。相手からは金の支払いという取引条件が示されるが、拒否。組織はとうとう彼女が交通違反で裁判所に出かける日をつかみ、二人のヘルメットをかぶった男がオートバイで彼女の赤い車を追いかけ、ちょうど信号で停止した道路上で拳銃によって暗殺する。
彼女の死後、アイルライドでは世論がもりあがり、麻薬取引を禁止し、その収益によって得られた財産を没収する法律がつくられた。犯人たちも逮捕され(仲間の名前を自白させるかわりにその身の安全を当局が保証する証人保護システムによる、と映画にでてきた)、刑に処せられた。
見ていて、ひとりで取材する方法はずいぶん危険だなと思ったし、危険を察知できなかったかとも思う。イギリスの新聞のスクープは往々にしてひとりの記者と情報提供者との関係から生まれるが、反対にそこに大きな危険もついて回る。こういう硬派のテーマを映画化する英米の映画界に感心する。なかなかいい映画だった。
見終わった後、車を運転した。隣にオートバイが寄ってきて・・・なんてことにならないか、とすこしこわくなった。
DVD「白いからす(原題はthe Human Stain」(アンソニー・ホプキンス、ニコル・キッドマン主演)。はじめは大学の人種差別発言で失職した老教授と、人生につかれはてた感じの放浪する女性との恋愛をベースにすすむのかと思ったが、後半になって、彼のかくされた過去/出生の秘密が明かされていく。
アメリカにおける人種差別の根深さを、別の角度から描いた作品。これまた、なかなかいい。
この春にみた映画(2005/04/09)
映画「パッチギ」(井筒和幸監督)。1968年あたりの京都を舞台にした青春もの。府立高校と朝鮮高校との張り合いのなかで、芽生えた恋。そのなかでとくに在日の若者たちの苦悩とつっぱりぶりを描いている。そのバックに流れるなつかしい「イムジン河」のメロディ。死んだ在日少年の告別式で父親が痛烈に日本批判をし、友人であろうとした主人公の修介を追い出してしまう。その悲しみのなかでギターを1度は鴨川にすててしまった修介がラジオの前で「イムジン河」を歌う。流れてくるラジオをみんなに聞かせる。いいシーンだな。あのメロディを歌う高校生のシーンで涙がでてきた。まさに自分がすごした高校生時代を思い出させた。もう戻らないあの時代へのなつかしさからか。思えば、自分もまさにこの同時代に生きてきた。「イムジン河」を歌い、「ベトナム反戦」を叫んでいた。そんなことがふと思い出されて、ついグッときてしまった。そのあと、在日の友人に教えられたとおりに 「二人でハーモニーをかなでよう」といったはずなのに、馬鹿な下ネタだったことで「アホ」といわれるシーンもいい。関西/中部出身のものにわかる愛情込めた「アホ」の台詞だった。沢尻エリカ演じるキョンジャの清楚な感じがよかった。
ただあの暴力シーンの連続はどうだろう。あれがなければ井筒作品でないという人もいるのかもしれないけれど、私が脚本家ならむしろ最後の鴨川の決闘までたたかわず、緊張をもりあげていく。そして死傷事件。そこで二人は・・・ともっていく。文字通り「ロミオとジュリエット」さらに「ウエストサイド物語」そっくりになってしまうのだが・・・。
* *
中国映画「故郷の香り」(京橋のテアトル銀座にて)。好評だった「山の郵便配達」を監督したフォ・ジェンチイの作品。トーンが基本的に同じ。故郷へ10年ぶりに帰った主人公がかつての恋人にばったり会う。彼女をたずねた主人公によみがえるなつかしく、かつ苦い思い出。彼女は、聴覚障碍者(香川照之)のヤーバの妻になっていた。しかし、最後にヤーバが彼女=暖(ニュアン)を心から愛しつづけていたことを知る。中国の山村の美しい光景が背景に、いまの中国の抱える都市と農村の格差・差別をもうかがわせる。香川照之が力演。
* *
韓国映画「大統領の理髪師」(渋谷bunkamuraのル・シネマにて)。朴大統領の専門の理髪師となった男の半生をコメディタッチで描く韓国映画。どこまでがフィクションで、どこまでが実話かよくわからないけれど、底流に流れるのは、民衆の権力に対する批判精神である。こういうコメディをつくるくらいに韓国映画も水準が高くなった証明か。
* *
映画「ブリジットジョーンズの日記 きれそうな私の10か月」。あいかわらずのイギリスのラブコメディ。しかし、イギリス人はこういう映画をつくるのがめっぽううまい。「ラブ・アクチュアリー」以来。レニー・ゼルウィガーはこの映画のために肥満になり、パンパンのはちきれんばかりの体になっている。ロンドンのなつかしい場所がたくさんでてきた。家はノッチングヒルという設定だとか。あの英語が十分にわかったら面白いだろうな。コリン・ファースは人権派弁護士(が、外国の経済産業大臣となぜ会談するのかわからないけれど)。イギリスの法曹界の格式ばったところが法曹界のパーティの場面ですこしでてくる。ヒュー・グラントはまたも女たらしの役。
* *
映画「オペラ座の怪人」。ミッテ10という新しい映画館なので、音楽と画面はさすがにすばらしい。かつてロンドンでミュージカルをみたが、これだけのあらすじだったのか、とあらためて知った。最後の「ドンファン」の場面での怪人とクリスティーヌの掛け合いのところなどよかった。クリスティーヌ役には若い エミー・ロッサム(デイ・アフター・トモローにでてきた)を抜擢したが、その美しさはいいが、声が残念ながら声量不足。かえっておろされる元プリマのほうがさすがにいい声に感じた。ロンドンの芝居ではびっくりさせられた地下の水路シーンも映画になるとあのときほどの感動はない。かえって、あたらしく入れられた墓地のシーンの方がきれいで印象にのこる。
* *
映画「ニュースの天才」。米国の週刊誌「NewRepublic」の若い花形記者の記事ねつ造事件をドラマ化したもの。はでな戦闘シーンもあでやかなラブシーンもない。むしろドキュメントに近い。記者グラスがねつ造が判明し、だんだん精神的に追いつめられて、「顔」がかわっていく様を「Star Wars episode2」の ヘイデン・クリステンセンが好演。
3つの日本映画を見て(2004/11/28)
「笑の大学」(三谷幸喜原作、役所広司、稲垣吾郎主演)。警視庁の検閲官・向坂(さきさか)と浅草の座付き脚本家兼演出家・椿一の検閲室での「対決」が見所。声高な戦争批判ではなく、人間にとって奪うことのできない「笑い」というテーマで戦争とあの暗い時代を考えさせる。原作、台本の面白さが決め手。ちなみに、この向坂という姓は、私たちの世代だとマルクス主義経済学者・向坂逸郎を思い出させるのだけれど、ここもパロディなのかな。評価=A、
「海猫」(森田芳光監督)。伊東美咲の迫真の演技が話題だが、いかにもへた。義弟(仲村トオル)と結ばれるまでがまったく唐突で、これは台本の欠点。佐藤浩市、仲村トオルもなにかのっていなくて仕方なく合わせているような感じがした。評価=D
「透光の樹」(根岸吉太郎監督、秋吉久美子、永島敏行主演)。東京のシネカノン有楽町でみた。ちなみに岐阜県青少年保護育成条例で有害映画と認定されていたので、より関心をもった。まあ、濡れ場シーンが多いけれど。「笑の大学」ではないけれど、有害映画かどうかを判定する方々が試写室かなんかでじっと見て「これはいけませんね」とかいって、ペタリと「有害」の印を押すのかしら。映画自体の評価=C、
「Dr. コトー診療所」放映(KTS)。
夜9時から、昨晩と今晩、連続で放映。4時間半ドラマ。好評だったドラマの特別編。今回のテーマは「家族」。1つの話は漁師の息子/剛洋が、医師目指して、東京の中学に転校するまで。親の思い、金策。そこに、淡い初恋の物語りが加わる。ぜんそく治療のため、東京から転校してきたひなちゃんと剛洋とのふれあい。「小さな恋のメロディ」のようなシーン。もう1つの話は、彩香の母親・雅代が豊漁祭りの夜、脳内出血で倒れる。夫(総務課長)は酒を飲まないでいたら、と悔やむ。娘の彩香も母からの電話をそっけなく扱ってしまったことを悔やむ。後遺症の母親の看病のために一度は神戸への転院を決意したのだが、剛洋を「送る会」に小学校にやってきた車いすの雅代にすこしの笑顔が戻ってくる。そして、この島での治療がはじまる。今回は、コトーの奮戦場面より、ふたつの家族をめぐる、ふれあいとわかれに重点をおいた作品。私も40年前、剛洋のように都会にでようと、ふるさとを離れたころのことを思い出し、遠く離れた母親のことを考えた。つれあいは、子どもたちの歌う「ビリーブ」に涙ぐんでいた。フジテレビはバカなバラエティ番組ばかりが目立つが、「北の国から」「白線流し」「Dr. コトー診療所」とドラマはいいものをつくる。いいスタッフが残っているのだろう。
ちなみにあのドラマの舞台は沖縄県与那国島だが、実際のお医者さんの話は鹿児島県甑島。
�
秩父の自由民権のたたかい 映画「草の乱」(神山征二郎監督)
自由民権運動で名高い秩父困民党事件を扱った社会派映画。死刑を逃れて33年もの間、北海道で偽名で暮らした井上伝蔵(緒方直人)の臨終の際の遺言から話が始まる。生糸の暴落、高利貸しのあこぎな利子支払い催促に耐える貧困な人々の苦しみ、それを知って心うたれて蜂起の指揮をとる富農たち(井上、田代、加藤織平=杉本哲太)。田代や井上は慎重にことをすすめようとするが、いきり立つ農民たちの強硬論に押されて、上州、信州からの援軍もなくついに蜂起にたつ。田代の蜂起の前の「もはや、ここまで」というのは、勝負の行方をすでに見定めた言葉だったか。高利貸しや警察を襲い、郡役所を占拠し「革命本部」をかまえたまではよかったが、支援する友軍なく、軍の介入で崩壊。ついに井上は総理・田代栄助(林隆三)のすすめもあって、逃げのびる。その中に妻とのふれあいと別れのシーンが挿入される。
有名な歴史的な事件を映画にしたこともあって、その展開は歴史再現のようで興味深い。しかし、自分が冷めているせいだろうか。映画の主人公たちの人間としての苦悩、生き様みたいなものがもう一つ伝わってこなかったような気がするのだが・・・。当日は自主上映実行委員会の主催だったこともあり、終了時に拍手まで起きたのに。緒方直人は好演。(2004/10/31)
映画「ロスト・イン・トランスレーション」(フランソワ・コッポラ監督)
東京にCMの撮影に来た往年の映画俳優ボブ・ハリス(ビル・マーレイ)と、写真家の夫につきそって東京に来た女性 シャーロット (スカーレット・ヨハンソン=「真珠の耳飾りの少女」の主演女優) の出会いと心のふれあい、そして別れを描く。この二人の話だけなら、よくあるラブストーリーだが、その背景になっているのが渋谷、東京、日本である。東京の町のワイゼツさがこれでもかというくらいに表現されている。夜たずねてくる日本人の女(これはLとRとをうまく区別して話せないことをギャグとして表している)、「テンション高めて」とわけもわからず怒りまくるCM監督、バラエティ番組の出演者(藤井隆)、くねくね踊りの変なヌードダンサー、病院の受付のおじさん、治療にきている老人、すこししか訳さない通訳、ゲームセンターやバーで遊びまくる若者たち。意識的に馬鹿らしく描かれている感じ。欧米人からみれば、この日本人たちはけったいな(変な)人間たちに見えるのだろう。アメリカなどではこの日本人の会話に字幕をつけていないそうだから、日本というわけのわからない「異国」の中の孤独を印象づける演出なのだろうか。しかし、その国に住み、その言葉がわかる人間としては、やや違和感が残る。
観客は最初自分ひとり。あとから一人がきて、二人だった。東京では満員だったというが、渋谷から遠くはなれた、この街とはあまりにちがう「東京物語」。(2004/10/24)
映画「swimming pool」。(フランソワ・オゾン監督、シャーロット・ランプリング(サラ・モートン)、リュディヴィーヌ・サニエ(ジュリー)主演)。(2004/10/16)
イギリスのスリラー小説作家サラとその愛人の娘ジュリーとのフランスの別荘でのできごと。とてもドキドキするような展開だが、肝心の問題、なぜ、ジュリーがフランクを殺してしまうのか、よくわからない。ジュリーの母親の死についてもなにか秘密があるらしいのだが、映画からだけではこれもよくわからず。やや消化不良。音楽はテンポがあって雰囲気をだしている。
映画「真珠の耳飾りの少女」(ピーター・ウェーバー監督、スカーレット・ヨハンソン、コリン・ファース主演)(2004/10/15)
バン・フェルメールの同じ題名の絵をモチーフに描かれた作品。3つの台詞がキーワードのように思った。
フェルメールの家の使用人となったグリート。しかし、彼女はフェルメールの部屋の掃除をしながら、その美的な才能に目覚めていく。「(窓を開けると)光が変わります。」
フェルメールは彼女をみとめて、助手にし、ついにはモデルにする。肉屋の息子という恋人がありながら、グリートもフェルメールにひかれていく。そして書かれた絵。「心まで描くの?」。
そのモデルに嫉妬する妻、そしてパトロンも彼女に手を出そうとする。そこでフェルメールはとうとう彼女を追い出す決断をするが、妻をとがめて「彼女は理解しているんだ」。
まるでフェルメールの絵を再現したようなきれいな映画。とくにアトリエのシーンなど光の入り具合、やや沈んだ色、小間物など絵そっくりである。映画の映像・撮影の美しさにひかれた。衣装もきれい。
この映画はイギリスの公的援助(その資金は宝くじからだが)を受けてつくられている。最近のイギリス映画にいいものが多いのはそのためでもある。日本もそうなったら若い有能な人たちが心うつ作品をつくるだろうに
(追記)アムステルダムのマダム・タッソーろう人形館(ロンドンのが有名だがアムスにもあります)のフェルメールのろう人形(絵「絵画芸術」のアトリエを再現)をふと思い出した。
市民劇場・俳優座「きょうの雨 あしたの風」(藤沢周平原作、吉永仁郎脚本)。(2004/10/4)
江戸の長屋に住む3つの家族の物語。旦那と死に別れ、ひとり住まいの「おとき」。ひょんなことからいきずりの男(幸太)を泊めることになる。母子ほど年が離れたふたりだが、養子になろうという提案がつい男と女の仲になってしまう。しかし、幸太は若い遊女おまちにひかれ、でていってしまう。最後にもどってくるけれど・・・。「六助・およね」夫婦。酒に酔った勢いでいつものように酒場で知り合った人を家につれてきてしまい、泊める羽目に。今回は、臭いにおいの老婆。しかし、この老婆が赤子の命を救いなどするうちに大切に思うようになる。そこへ問屋を経営する息子が嫁との確執から家出した母を迎えにやってくる。最後に「おしず/栄次」姉弟。栄次は暮らしの退屈さからばくちに走り、やくざに大きな借金を負ってしまう。一膳飯屋で働くおしずはその「方」としてやくざにつれさられてしまう危機におちいるが、そのとき、おしずに思いを寄せる重吉、昔のやくざもので今は老人の作十(30両を盗み、やくざとの果たし合いで死亡する)に助けられる。この3家族のからみを淡々とえがく江戸時代もの。いかにも藤沢作品らしい香りがする。
映画「誰も知らない」(2004/9/27)
カンヌ映画祭の主演男優賞受賞で一気に話題になった作品。台詞とも演技ともつかないこどもたちの動きに感心する。おそらく長期にわたってカメラを意識させないところまでまわし続けたのだろう。あらすじはずいぶんつらい。悲しいくらいに能天気な母親。母親代わりの兄弟思いの、しかし、子供の気持ちをもちつづけている長男・明。これが実際の話だとしたら、日本の社会はなんと他人を顧みない寂しい社会か。(是枝裕和監督、柳楽優弥主演)。
映画「lovers」=なんだか晩年の黒沢作品に似ている(2004/9/3)
唐の時代、朝廷と反政府の武装団との争いのなかでの愛憎を扱う。味方が敵のスパイだったりとやや入り組んでいるが、基本的には恋愛もの。映像自体は色彩豊かできれいだ。ワダ・エミの衣装のせいか。チャン・イー・モアの作品はだんだんと晩年の黒沢の作品、たとえば「乱」「影武者」に似てきて、映画のすじや主張より、映像美、様式美に凝っていく傾向をしめしているような気がする。(チャン・イー・モア監督、アンディ・ラウ、金城武、チャン・ツー・イーなど出演)。
映画「華氏911」(ごぞんじマイケル・ムーア監督)(2004/8/30)
いろいろと撮影されたフィルムをかなり編集・構成し直しているから、その1コマ1コマをきりとれば、こっけいなシーンもでてくる。オン・エアー前の化粧直しもその場だけとりあげれば、ブッシュの馬鹿さかげんもかなり伝わってくることになる。しかし、これはやや意図的演出といわざるをえまい。あたらしい事実の発掘がそれほどふくまれているわけでもない。だから、ドキュメンタリー映画としてはそれほどのものではない気がした。「ボウリング・フォー・コロンバイン」の方がドキュメンタリー映画として印象が強かった。もちろん米国政府高官のかくされている裏側をあきらかにしようとしているという点は買える。反ブッシュの雰囲気がとくにリベラル派に強く、CNN、FOXなどのように「愛国」報道の蔓延するアメリカではヒットしたことはわかる。しかし、ひるがえって日本では反ブッシュ感情もなく、みんながそれなりに知っている情報だけではあまりヒットしないように思うのだが。
市民劇場=「罠」(五五の会)(2004/8/21)
妻が行方不明になった夫(山本学)のところに、「妻だ」と名乗る女(大空真弓)と神父がのりこんできて、その財産をわがものにしようとする。夫は「詐欺で、まったくの別人だ」と主張するのだが、警察の部長(金田竜之介)はとりあってくれない。後半になって、証人があらわれたりして、すこしずつ夫が有利になっていくのだが、その証人も殺されてしまう。とうとう追いつめられた夫は、「妻がいれくれたら」と切におもい、その妻の秘密を明かしてしまう。最後の5分の「大逆転」がこの劇のすべて。脚本の勝利であろう。自分の気持ちが夫に向いていったときの「大逆転」なので、その鮮やかさがより印象に残る。おもしろい芝居だった。
秩父の自由民権のたたかい 映画「草の乱」(神山征二郎監督)
自由民権運動で名高い秩父困民党事件を扱った社会派映画。死刑を逃れて33年もの間、北海道で偽名で暮らした井上伝蔵(緒方直人)の臨終の際の遺言から話が始まる。生糸の暴落、高利貸しのあこぎな利子支払い催促に耐える貧困な人々の苦しみ、それを知って心うたれて蜂起の指揮をとる富農たち(井上、田代、加藤織平=杉本哲太)。田代や井上は慎重にことをすすめようとするが、いきり立つ農民たちの強硬論に押されて、上州、信州からの援軍もなくついに蜂起にたつ。田代の蜂起の前の「もはや、ここまで」というのは、勝負の行方をすでに見定めた言葉だったか。高利貸しや警察を襲い、郡役所を占拠し「革命本部」をかまえたまではよかったが、支援する友軍なく、軍の介入で崩壊。ついに井上は総理・田代栄助(林隆三)のすすめもあって、逃げのびる。その中に妻とのふれあいと別れのシーンが挿入される。
有名な歴史的な事件を映画にしたこともあって、その展開は歴史再現のようで興味深い。しかし、自分が冷めているせいだろうか。映画の主人公たちの人間としての苦悩、生き様みたいなものがもう一つ伝わってこなかったような気がするのだが・・・。当日は自主上映実行委員会の主催だったこともあり、終了時に拍手まで起きたのに。緒方直人は好演。(2004/10/31)
 はじめに戻る
はじめに戻る
映画「ロスト・イン・トランスレーション」(フランソワ・コッポラ監督)
東京にCMの撮影に来た往年の映画俳優ボブ・ハリス(ビル・マーレイ)と、写真家の夫につきそって東京に来た女性 シャーロット (スカーレット・ヨハンソン=「真珠の耳飾りの少女」の主演女優) の出会いと心のふれあい、そして別れを描く。この二人の話だけなら、よくあるラブストーリーだが、その背景になっているのが渋谷、東京、日本である。東京の町のワイゼツさがこれでもかというくらいに表現されている。夜たずねてくる日本人の女(これはLとRとをうまく区別して話せないことをギャグとして表している)、「テンション高めて」とわけもわからず怒りまくるCM監督、バラエティ番組の出演者(藤井隆)、くねくね踊りの変なヌードダンサー、病院の受付のおじさん、治療にきている老人、すこししか訳さない通訳、ゲームセンターやバーで遊びまくる若者たち。意識的に馬鹿らしく描かれている感じ。欧米人からみれば、この日本人たちはけったいな(変な)人間たちに見えるのだろう。アメリカなどではこの日本人の会話に字幕をつけていないそうだから、日本というわけのわからない「異国」の中の孤独を印象づける演出なのだろうか。しかし、その国に住み、その言葉がわかる人間としては、やや違和感が残る。
観客は最初自分ひとり。あとから一人がきて、二人だった。東京では満員だったというが、渋谷から遠くはなれた、この街とはあまりにちがう「東京物語」。(2004/10/24)
映画「swimming pool」。(フランソワ・オゾン監督、シャーロット・ランプリング(サラ・モートン)、リュディヴィーヌ・サニエ(ジュリー)主演)。(2004/10/16)
イギリスのスリラー小説作家サラとその愛人の娘ジュリーとのフランスの別荘でのできごと。とてもドキドキするような展開だが、肝心の問題、なぜ、ジュリーがフランクを殺してしまうのか、よくわからない。ジュリーの母親の死についてもなにか秘密があるらしいのだが、映画からだけではこれもよくわからず。やや消化不良。音楽はテンポがあって雰囲気をだしている。
映画「真珠の耳飾りの少女」(ピーター・ウェーバー監督、スカーレット・ヨハンソン、コリン・ファース主演)(2004/10/15)
バン・フェルメールの同じ題名の絵をモチーフに描かれた作品。3つの台詞がキーワードのように思った。
フェルメールの家の使用人となったグリート。しかし、彼女はフェルメールの部屋の掃除をしながら、その美的な才能に目覚めていく。「(窓を開けると)光が変わります。」
フェルメールは彼女をみとめて、助手にし、ついにはモデルにする。肉屋の息子という恋人がありながら、グリートもフェルメールにひかれていく。そして書かれた絵。「心まで描くの?」。
そのモデルに嫉妬する妻、そしてパトロンも彼女に手を出そうとする。そこでフェルメールはとうとう彼女を追い出す決断をするが、妻をとがめて「彼女は理解しているんだ」。
まるでフェルメールの絵を再現したようなきれいな映画。とくにアトリエのシーンなど光の入り具合、やや沈んだ色、小間物など絵そっくりである。映画の映像・撮影の美しさにひかれた。衣装もきれい。
この映画はイギリスの公的援助(その資金は宝くじからだが)を受けてつくられている。最近のイギリス映画にいいものが多いのはそのためでもある。日本もそうなったら若い有能な人たちが心うつ作品をつくるだろうに
(追記)アムステルダムのマダム・タッソーろう人形館(ロンドンのが有名だがアムスにもあります)のフェルメールのろう人形(絵「絵画芸術」のアトリエを再現)をふと思い出した。
市民劇場・俳優座「きょうの雨 あしたの風」(藤沢周平原作、吉永仁郎脚本)。(2004/10/4)
江戸の長屋に住む3つの家族の物語。旦那と死に別れ、ひとり住まいの「おとき」。ひょんなことからいきずりの男(幸太)を泊めることになる。母子ほど年が離れたふたりだが、養子になろうという提案がつい男と女の仲になってしまう。しかし、幸太は若い遊女おまちにひかれ、でていってしまう。最後にもどってくるけれど・・・。「六助・およね」夫婦。酒に酔った勢いでいつものように酒場で知り合った人を家につれてきてしまい、泊める羽目に。今回は、臭いにおいの老婆。しかし、この老婆が赤子の命を救いなどするうちに大切に思うようになる。そこへ問屋を経営する息子が嫁との確執から家出した母を迎えにやってくる。最後に「おしず/栄次」姉弟。栄次は暮らしの退屈さからばくちに走り、やくざに大きな借金を負ってしまう。一膳飯屋で働くおしずはその「方」としてやくざにつれさられてしまう危機におちいるが、そのとき、おしずに思いを寄せる重吉、昔のやくざもので今は老人の作十(30両を盗み、やくざとの果たし合いで死亡する)に助けられる。この3家族のからみを淡々とえがく江戸時代もの。いかにも藤沢作品らしい香りがする。
映画「誰も知らない」(2004/9/27)
カンヌ映画祭の主演男優賞受賞で一気に話題になった作品。台詞とも演技ともつかないこどもたちの動きに感心する。おそらく長期にわたってカメラを意識させないところまでまわし続けたのだろう。あらすじはずいぶんつらい。悲しいくらいに能天気な母親。母親代わりの兄弟思いの、しかし、子供の気持ちをもちつづけている長男・明。これが実際の話だとしたら、日本の社会はなんと他人を顧みない寂しい社会か。(是枝裕和監督、柳楽優弥主演)。
映画「lovers」=なんだか晩年の黒沢作品に似ている(2004/9/3)
唐の時代、朝廷と反政府の武装団との争いのなかでの愛憎を扱う。味方が敵のスパイだったりとやや入り組んでいるが、基本的には恋愛もの。映像自体は色彩豊かできれいだ。ワダ・エミの衣装のせいか。チャン・イー・モアの作品はだんだんと晩年の黒沢の作品、たとえば「乱」「影武者」に似てきて、映画のすじや主張より、映像美、様式美に凝っていく傾向をしめしているような気がする。(チャン・イー・モア監督、アンディ・ラウ、金城武、チャン・ツー・イーなど出演)。
映画「華氏911」(ごぞんじマイケル・ムーア監督)(2004/8/30)
いろいろと撮影されたフィルムをかなり編集・構成し直しているから、その1コマ1コマをきりとれば、こっけいなシーンもでてくる。オン・エアー前の化粧直しもその場だけとりあげれば、ブッシュの馬鹿さかげんもかなり伝わってくることになる。しかし、これはやや意図的演出といわざるをえまい。あたらしい事実の発掘がそれほどふくまれているわけでもない。だから、ドキュメンタリー映画としてはそれほどのものではない気がした。「ボウリング・フォー・コロンバイン」の方がドキュメンタリー映画として印象が強かった。もちろん米国政府高官のかくされている裏側をあきらかにしようとしているという点は買える。反ブッシュの雰囲気がとくにリベラル派に強く、CNN、FOXなどのように「愛国」報道の蔓延するアメリカではヒットしたことはわかる。しかし、ひるがえって日本では反ブッシュ感情もなく、みんながそれなりに知っている情報だけではあまりヒットしないように思うのだが。
市民劇場=「罠」(五五の会)(2004/8/21)
妻が行方不明になった夫(山本学)のところに、「妻だ」と名乗る女(大空真弓)と神父がのりこんできて、その財産をわがものにしようとする。夫は「詐欺で、まったくの別人だ」と主張するのだが、警察の部長(金田竜之介)はとりあってくれない。後半になって、証人があらわれたりして、すこしずつ夫が有利になっていくのだが、その証人も殺されてしまう。とうとう追いつめられた夫は、「妻がいれくれたら」と切におもい、その妻の秘密を明かしてしまう。最後の5分の「大逆転」がこの劇のすべて。脚本の勝利であろう。自分の気持ちが夫に向いていったときの「大逆転」なので、その鮮やかさがより印象に残る。おもしろい芝居だった。
映画「父と暮らせば」(東京・岩波ホールでみる)(2004/8/12)。
最近みた映画のなかの最も秀作といってよかった。原作は井上ひさし。筋立ても劇とほとんどかわらない。ただ舞台でみたときは、すまけいの演ずる親父・竹造が幽霊だと気がつくまで時間がかかった。「お天道様のような光りを真正面にうけて・・」などという台詞によってはじめて気がつき「あっ」と思った。映画は、筋立てを知っていたせいか、やや早く幽霊であることがわかる。被爆のシーン、焼け落ちた広島の町、3ヶ月の後の広島の町などのCGによるシーンは映画独自のもの。宮沢りえ扮する福吉美津江が「うちには幸せになる資格はない」というあたりのシーンは心うつ。さらに、こどもに昔話を語るさまをひとりで鏡の前で演ずるシーン、宮沢りえの美しさが光る。「たそがれ清兵衛」で「大女優への予感」を感じさせた宮沢りえが本当にその道を歩き始めたことを実感させた。(黒木和雄監督、原田芳雄、宮沢りえ)
(2004/8/18)
招待券があたり、ついでに連れ合いもさそって(2500円なり)ウラジミル・ミシュク(ロシア)の「ロマンティック・ピアノ2004」コンサートを市民文化ホール第2に聞きにいく。曲目はベートーベン「月光」、ショパン「幻想即興曲」、ドビッシー「月の光」、ラヴェル「水の戯れ」、リスト「ラ・カンパネラ」と美しい曲だった。低音と高音のバランスがうまい感じ。さすがに生のピアノはここちよく。あのくらいのサイズのホールだったこともよかったのかも。
映画「ブラザーフッド」(2004/7/23)
朝鮮戦争下の韓国が舞台。強制的な徴兵で兄弟は兵隊にとられてしまう。そこで弟思いの兄は、弟の除隊を願って、ひたすら勲章めざして奮闘する。釜山ちかくまで追いつめられる韓国軍。そして、反撃。ソウルへ、ピョンヤンへ。中朝国境への進軍、中国人民義勇軍の参戦、冬のさなかの撤退。帰ってきたソウルでの白色テロ(今回、韓国のいわば恥部ともいえる右派による住民殺害を描いていたことはあたらしい知識であった。このように描けるようになった事自体、韓国の民主化の進展を示すものであろう。)弟も婚約者も殺害されたと知った兄は一転、北朝鮮軍に加わるが、戦場で弟と出会い、こんどは弟をまもるために北軍に機関銃の雨嵐をあびせかける。最後の部分はやや突飛な印象か。
DVD「ジョンQ」(ダンゼル・ワシントン主演)(2004/7/17)
子供が心臓の障害で倒れるが、病院は失業者に近いジョンがしっかりした保険にはいっていないことを理由に、心臓移植のリストにのせてはくれない。そこで、彼は、病院に人質をとって立てこもり、要求をつきつける。「悪人」のはずのジョンが人質たちの共感を得ていく。そして、最後はハッピーエンド。最初の交通事故のシーンの意味があとでわかってくる。銀行強盗ものの、暴力的な映画かとおもっていたら、現代アメリカ社会の金持ち優遇の社会保障制度批判、医療批判もあって、なかなか面白い。
映画「ハリーポターとアズガバンの囚人」(2004/8/15)
娯楽作品としては、やや話がこみいっていて、とくに前半の展開がわかりにくい。後半の3人の主人公と妖怪たちとのたたかいはけっこう面白いが。
韓国映画「シルミド(島)」(2004/7/8)
パク政権下の韓国は、ソウル攻撃を企てた北朝鮮への報復として、金日成暗殺をねらって、特殊部隊をひそかに組織・養成する。死刑囚が、うまくいけば名誉回復だというえさにつられて、集められ、きびしいしごきにも似た軍事訓練で鍛えられる。そして、決行となる。しかし、出発直後、「作戦中止」が指令され、反対に、この特殊部隊の「抹殺」が指令される。それを知った訓練兵たちは反乱をおこす。そして、ソウルの大統領官邸めざして「進軍」する。「共産ゲリラ」と呼ばれて、彼らの絶望はさらにつのり、軍隊の停止線の前で、ついに自爆する。韓国で実際に合った話らしい。情報公開でようやく知られるようになった。こういう歴史の秘話を映画にする例は日本映画にはほとんどない。「シュリ」「JSA」「二重スパイ」とつづいて、今回の作品。テーマはいずれも南北の軍事対立、パク政権下の弾圧への抵抗。アメリカの80年代の映画には「ベトナム戦争の影」があったが、いまの韓国映画にもどうようの伏流がある。それにひきかえ、日本の映画はどうだ。あいかわらずの私生活主義映画ばかり。
市民劇場「ミュージカル 俺たちは天使じゃない」(2004/7/6)
刑務所を脱獄した3人組が、人質にしようとした山の一軒家でかえって、その家族の危機を救ってしまう物語。さすがに、いずみたくの作曲だけのことはある。相聞歌のように、男と女の二重奏がきれい。「いま、いま、愛を知るとき」の曲も「あ、この作品だったのか」と思わせる。
美しい風景を写す二つの中国映画(2001/11/15)
映画「山の郵便配達」((原作)ポン・ヂェンミン(監督)フォ・ジェンチイ(出演)トン・ルゥジュン、リィウ・イェ)。
中国・湖南省に働く郵便配達人は足がいうことを効かなくなる。そこで、その仕事を息子に譲る。はじめて仕事にでかける息子に父親はついて2泊3日の配達の旅にでかける。手紙をまちわびる老婆、少数民族の美しい娘(浅野温子に似たタイプ)、通信教育に励む少年、宿を提供してくれる女性などさまざまな人とのふれあいが描かれる。その中で息子は、これまであまり家庭をかえりみてこなかった父親をゆるし、地域の人たちの心の支えになっている父を理解するようになる。川で父親を背負って渡る息子。このあたりのシーンは泣かせるなあ。風でとびそうになった手紙を必死でおいかける父親の姿も、父親の郵便配達を「聖職」と考えるこころをよく示している(このシーンは原作の小説にはない)。シェパードの「次男坊」も熱演(やや演出過剰かな?)。あぜ道ですれ違う娘たち、村の祭りで踊る若者たち、この映画にでてくる中国の若者たちがなんと純朴にみえることか。
中国映画ということで、見たいと思っていた「初恋の来た道」(チャン・イー・モウ監督、チャン・ツィー・イー主演)をDVDで見た。
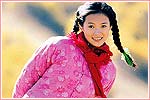
中国北部の町に赴任した学校教師にその土地の娘ディは淡い初恋の思いをいだき、必死に料理をつくり、学校の近くの井戸までわざわざ水を汲みに行く。その思いは教師に伝わり、彼も娘に好意をいだくが、「反右派闘争」にまきこまれて(1959年)、拘束される。それを待ちつつける娘。
回想シーンをカラーで、現実をモノクロで描く。現実の世界では、成人して大学にまですすんだ息子は、母ディの父への思いをくんで、父の葬式を伝統にしたがって、人々が道を運ぶやり方を選ぶ。そこに集まる教え子たち。母は息子に父の思いをついでほしいと想っているが、息子は、父のたった教壇で父が作った教材を使って。1時間の授業を行なう。この様子がたんたんと描かれる。
回想シーンの色彩はきれい。落葉の黄色、うすく積もった雪の白。チャン・ツィー・イーは素朴さがでていて、かわいかったなあ。意識的にもんぺのしたに何か入れて、腰を太くさせて。いかにも田舎の娘を表現していた。
ふと、これらの映画は、かつての日本の「キューポラのある街」ではないだろうかと思った。この二つの映画に悪者は出てこない。「いい人」ばかりなのだけれど、「キューポラ」も二人の姉・弟と人々のふれあいを描いていた。そういうふうに考えると、この中国映画は、日本が経済の高度成長の中で忘れてしまった何かを思い出させる。
中国映画の水準の高さを教えられた。
 はじめに戻る
はじめに戻る
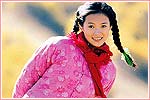
 はじめに戻る
はじめに戻る
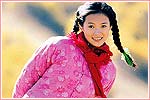
 はじめに戻る
はじめに戻る