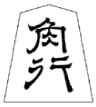|
駒知識百か条
|
| 駒マニアを問わず将棋好きなら誰でも、「いい駒にめぐり合いたい」と一度は思うことがあるはず。駒を選ぶとき、そんな方々にひとつの目安として活用してほしいのが、ここに掲げた「駒知識百か条」。 もっとも「いい駒にめぐり合った」からといって、棋力がアップするわけではないのですが、これからの長い将棋のパートナーとして、駒は最適!! |
| 1 | 駒の種別は4種類(書き、彫り、彫り埋め、盛り上げ) |
 駒木地・虎斑 |
| 2 | 最初に作られたのは書き駒 | |
| 3 | 江戸期に彫り・彫り埋め駒が流布 | |
| 4 | 明治初期までに、盛り上げ駒の製法完成 | |
| 5 | 駒の素材は、黄楊と漆が基本 | |
| 6 | 製法は駒師によってそれぞれ異なる | |
| 7 | 駒は勝負に介在する遊具、または道具である | |
| 8 | 道具を超えた駒の真の魅力 | |
| 9 | 駒木地に最も適すのは黄楊 | |
| 10 | 「駒は黄楊に限る」という故事 | |
| 11 | 国産の島(御蔵島)黄楊と薩摩黄楊 |
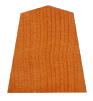 駒木地・赤柾 |
| 12 | 外国産のシャム黄楊と中国黄楊 | |
| 13 | 各黄楊にある長所と短所 | |
| 14 | 黄楊の堅さは、榧盤に適切 | |
| 15 | 「木の宝石」ともいわれる黄楊の美しさ | |
| 16 | 厳しい自然が高級材(虎斑、赤柾、根杢)を産出 | |
| 17 | 黄楊の伐採は、木が生長しない冬季に行う | |
| 18 | アオ(シミやカビ)が入っては駒材としてはダメ | |
| 19 | 駒木地はとれる部位によって異なる | |
| 20 | 櫛型か平行びきで作る板木地 | |
| 21 | 駒木地は柾目取りが基本で、残りが板目 |
 駒木地・根杢 |
| 22 | 高級材は罫書き(板木地に駒形を記す)が大事 | |
| 23 | 駒木地の種類は豊富 | |
| 24 | プロ棋士に好まれる赤柾は、対局時に目にやさしい | |
| 25 | 駒一組が、必ずしも同じ原木とは限らない | |
| 26 | 現存する最古の駒は墨書き | |
| 27 | 墨書きから漆書きへ | |
| 28 | 古将棋(中将棋など)はほとんどが書き駒 | |
| 29 | 僧侶や公家が書き駒の制作者 | |
| 30 | 書き駒のルーツは「水無瀬駒」 | |
| 31 | 水無瀬家の筆をもって宝とす | |
| 32 | 天童で独自に発展した書き駒 | |
| 33 | 漆書きは熟練の技を要する |
|
| 34 | 書き駒から彫り駒への経緯はつまびらかではない | |
| 35 | 普及品として彫り駒は流布 | |
| 36 | 駒作りの基本は彫り駒 | |
| 37 | 地味な作業でも、目止めが駒の出来を左右する | |
| 38 | 彫りのそろいは基本だが、時には不ぞろいも味が… | |
| 39 | 彫りあとに漆がたまってはダメに | |
| 40 | 浅彫りと深彫りで趣が違う | |
| 41 | 深彫りを得意とする駒師もいる | |
| 42 | 駒の後ろに作者が見える「手作り駒」 | |
| 43 | 一見、彫り埋め駒は墨書きに見える | |
| 44 | 指し将棋に一番向いている彫り埋め駒 | |
| 45 | 盤に吸いつくような感触は、彫り埋め駒の味 | |
| 46 | 埋め方には2種類ある | |
| 47 | 漆だけを埋まるまで何度も塗り重ねていく | |
| 48 | サビ漆で効率よく埋める | |
| 49 | 漆は固まるときにヤセる(へこむ) | |
| 50 | 彫り埋め駒の別名は、研ぎ出し駒 | |
| 51 | なんといっても華のある盛り上げ駒 | |
| 52 | 四段以上のプロ棋士が盛り上げ駒を公式戦で使用 | |
| 53 | 盛り上げの漆には高低がある | |
| 54 | 漆がある程度減るまで、盛り上げは回って指しにくい | |
| 55 | 駒字をアレンジしやすいのは盛り上げ駒 | |
| 56 | 盛り上げ用の目止めも必要 | |
| 57 | 彫りはやや細めが盛り上げやすい | |
| 58 | 漆が飛んでも、作り直しがきく盛り上げ駒 | |
| 59 | 駒に使用する漆には数種類ある | |
| 60 | 作者の好みだが、呂色漆が基本 | |
| 61 | 漆はブレンド(呂色+木地呂など)使用もあり | |
| 62 | 耐久力と「漆黒の美」が漆の身上 | |
| 63 | 時を経てツヤと深みを増す漆 | |
| 64 | 漆の乾燥には湿気が欠かせない | |
| 65 | 一定温度と一定湿度が漆を乾かすには大切 | |
| 66 | 湿度の与えすぎは、漆が急激に乾燥して縮む | |
| 67 | 面取りで駒が手になじむ | |
| 68 | 面取りの度合いは作者の好み | |
| 69 | 面取りのしすぎは、指しやすいが駒がダレて見える | |
| 70 | 磨きの違いで駒はガラリと変わる | |
| 71 | 磨くときの焼き入れが駒に金属質を生む |
表が隷書、裏が篆書の「英朋」の字母紙
|
| 72 | 最終仕上げの磨きは、作者でかなり異なっている | |
| 73 | 油(椿、クルミなど)のつけすぎは駒によくない | |
| 74 | 駒を使ったら、布でカラぶきが一番 | |
| 75 | 駒の表字は楷書か行書、裏字は草書が基本 | |
| 76 | 隷書や篆書、それに混在型など変わり書体もある | |
| 77 | 駒の書体にはそれぞれに確立経緯がある | |
| 78 | 駒字の版木や字母紙は駒師の財産 | |
| 79 | 近代将棋駒の祖・豊島龍山が残した「字母帖」 | |
| 80 | 古来から数多くの書体(100種類以上)が伝わる | |
| 81 | 同書体でも駒師によって異なっている | |
| 82 | 現在でも新書体が作られている | |
| 83 | 駒師の始まりは、公家や僧侶か? | |
| 84 | お城将棋などにも使われた水無瀬家の駒作り | |
| 85 | 江戸期に一般的な職業としての駒師出現 | |
| 86 | 将棋所・大橋本家の駒作り | |
| 87 | 豊島龍山の出現で、東京の駒作りは花開く | |
| 88 | 明治〜昭和にかけて多くの名工が輩出 | |
| 89 | 1991年、金井静山没で東京にプロの駒師消滅 | |
| 90 | 江戸末期、将棋の町・天童で駒作りが始まる | |
| 91 | 1980年代、天童で高級駒が作られるようになる | |
| 92 | 1977年、アマチュアの駒作りが本格的に始まる | |
| 93 | 書体名と号(作者名)が記されているのが駒銘 | |
| 94 | 駒銘の入れ方には決まりがない | |
| 95 | 駒銘は作者自身を表すともいわれる | |
| 96 | 変則的な駒銘として横組もあり | |
| 97 | 駒銘専用の道具もある | |
| 98 | 道具としての駒には力強さがある | |
| 99 | 「使われてこそ名駒」を肝に銘じる | |
| 100 | 「駒知識百か条」を読み返す |
|
以上が「駒知識百か条」です。駒を選ぶときの参考にしてください。駒には将棋を指す側面のほかに、芸術的な美しさもある。ことに虎斑の盛り上げ駒など何十万円もするような高額なものは、使えば傷がつくので、鑑賞用に飾っておくだけのマニアも多い。ただしそれだけは、なんとなく駒がかわいそうな気がする。
|