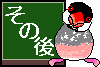
| 文鳥問題. |
「桜文鳥の『桜』とは何ぞや」と質問されれば、「胸の白い差し毛のぼかし模様が桜の花びらのようだから」と答えるのが正解のはず。ところが一般には白文鳥でないもの全部を桜文鳥と表現してしまい、それが当然のことのようになっているから不思議である。いったい、胸のぼかしが桜の花びらのようでなければ、本来桜文鳥と呼ぶのはおかしいのではないだろうか?『桜』のない桜文鳥では語義に矛盾すると言わざるを得ないではないか。
最近『桜文鳥』とされている文鳥は、白文鳥ではない混色のもの(『パイド』)の総称のように使う人もいる。『桜』模様は色彩として固定されておらず、さまざまのパターン(『羽装変化』)があるのは当然、というわけだ。しかし、固定されていないのと、固定できないのとは全く違う。それは、桜模様のぼかしのある本当の意味での桜文鳥を固定化しようと努力を払った上での結論であろうか。私はその点はなはだ怪しいと思っている。
例えば、畜産の指導書である『畜産全書』は、文鳥の生産繁殖では桜文鳥と白文鳥の組み合わせにした方が良いとしている。つまりい品種間繁殖を推奨しているのだが、その理由は、白と白では繁殖率が下がる交配結果が得られたので、経済性からその方が利益率が良いというものである。ようするに、ここでは文鳥を農作物並に扱っており、いかに効率の良い『生産』が可能であるかがテーマで、種を固定化しようといった思想はない。
こうした生産性のみを掲げ、固定化の努力もなしに、適当に白との交雑をして白化の激しい個体を市場に流しているのだとしたら、日本の繁殖家は、シナモンやシルバーを固定化した外国の繁殖家に後ろめたさを感じた方が良いかもしれない。「品種は固定しているのではなく人為的に固定するものである」などと繁殖の専門家に申し上げるのは、釈迦に説法の類だろうが、ペットショップで売られている『桜文鳥』を見ていると、どうしてもそう言いたくなってきてしまう。
もしも、胸のぼかし模様程度にしか白い差し毛がない文鳥を選択して繁殖していったのであれば、はてさて、これほどの混乱状況となっただろうか?
とりあえず、現在『桜文鳥』の範疇に入ってしまう『羽装変化』なるものを、胸のぼかしの部分で見てみよう。
| その胸のぼかし模様 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
上は我が家の例、左から4番目までは桜模様と言って良いかも知れないが、5番目あたりから怪しくなり、右端の2羽を『桜』と称して販売したら、もはや不当表示になると私は思うが、いかがだろうか。
こういった白い差し毛の混在の度合いが実にさまざまで、固定されていない現状では、むしろ『桜』などとは言わずに『パイド』(英語の「pied」混色、まだらの意味)とした方が良いという議論も成り立ちうるだろう。さらに、この議論の延長上には、純白の白文鳥も『パイド』に含むべきとの見解まで存在している。
なぜ純白のものがパイドなのか、不審に思われるだろうが、これは白文鳥と白文鳥の間にも『桜』が産まれるところから、外見とは別に遺伝的には同じものと、ごく単純に判断している結果なのである。玄人的な人間が、そのようなことを言えば、そんなものかと思えてくるが、私はこの解釈にも賛同出来ない。なぜなら、この解釈は下に掲げる農事試験場の試験結果(『畜産全書』と同じ)を部分的に理解したもので、正しくないと考えられるのだ。
| 親の種類(遺伝子型) | 子供の種類(遺伝子型)比率 | 実験結果(数字は大まかにそろえた) | |
| 白(○●)×白(○●) | 1致死(○○)・2白(○●)・1桜(●●) | 孵化率60% | 白250羽:桜120羽 |
| 白(○●)×桜(●●) | 2白(○●)・2桜(●●) | 孵化率80% | 白200羽:桜200羽 |
| 桜(●●)×桜(●●) | すべて桜(●●) | 孵化率80% | 桜400羽 |
つまり、純粋の白文鳥はいないので(いわゆる白ホモは致死遺伝で孵化以前に死んでしまう)、その基本的に実在しない白と野生文鳥の間のそれは、すべて混色、と見なせそうな気がする。しかし、この実験は「白文鳥もパイド」説の根拠とはなりえない。何しろ、この試験結果は明らかに桜と白を別の遺伝子型で表現しており、この結果から導き出されるのは、純粋の白文鳥(ホモ)は卵段階で死んでしまい存在しない、言いかえれば、白文鳥は実は純粋な白と桜の雑種であるということ以外ではない。ようするに桜を『パイド』と考えないことを前提とした実験なのである。
また、桜と桜から産まれるのは100%桜だったという結果にも注意しなければならない。白が生まれる事はまるでなかった結果を踏まえれば、両種を同種と包括するのは、もはや、まったく不可能なのである。
第一、桜と白の色彩遺伝が優性遺伝の法則に従うものとするのなら、桜と白は絶対的に別ものと扱わざるを得ないはずであり(○や●といった対立遺伝子が設定されている)、これを同種とするのは矛盾でなくて何であろう。そうした根本的な部分を、しっかり踏まえないで、単純に『羽装変化』だとか『パイド』などと見なすのは、いかがなものかと思う。
それでも、白や桜の色彩が優性遺伝によるものではないとすれば、桜と白を同種とする事に論理性を保つ事は出来るように思うかもしれない。しかしそうであったとすれば、『パイド』に白い差し毛の入る度合いは、胸のぼかし程度から純白まで偶然的(もしくは非優性遺伝的)な羽装変化に過ぎないのだから、上のような優性遺伝の存在を示すような繁殖実験は、すべて偶然によるものと強弁しなければならなくなる。どうしても論理矛盾がでてきてしまうのである。
※この点白の起源をめぐる話と同じだろう。白が桜の白の差し毛の多いものを人為選択して作られたものなら、農事試験場の結論である優性遺伝の法則を真っ向から否定しなければならない。
しかし、桜と桜からは白文鳥は産まれないという実験結果に疑問を持つ人も多いかもしれない。白も産まれるのではないか・・・。この点について、私は『桜文鳥』の幅が広すぎる事からくる混乱だと思っている。白が産まれたとしたら、それは親鳥が『桜』であって桜文鳥ではなかったのかもしれない。
そこで私は、『文鳥学講座』において白の遺伝因子は優性遺伝として機能するものと、優性とはならないものの二種類があるものと考えてみた(『文鳥学講座』)。桜と白の合いの子として『ゴマ塩』が遺伝的に存在するものと仮定し、我が家の右の二羽は中間雑種の『ゴマ塩』であって、桜文鳥ではないと想定したわけだ。
以上は明らかに素人考えだが、別に優性遺伝の法則などにこだわらずとも、もっと素朴に桜の理想形を明確にした上で、それに近づける努力は可能であろうし、その必要は大きいのではないかと思う。ようするに、理想形に近い者同士を交配していけば良いだけの話なのだ。何やら種の固定とは無縁な繁殖実験をした挙句に、純白でないものは『桜』だ『パイド』だと一括して市場に流すようでは、「桜文鳥」が、たんなるいい加減な繁殖の、隠れ蓑になってしまう気がしてならない。
弥富の文鳥の場合は、白と桜に生み分けられるようだから良いものの、「白と桜の組み合わせがベスト」という結論を他の地域で適用すると『ゴマ塩』ばかりで生み分けが起こらず、結局桜ならぬ『ゴマ塩』が『桜』として市場に出てくる結果になったような気がしている。また、おそらく並文鳥をベースにしたと思われるシナモンなどと交雑で生じた原種配色の文鳥まで、『桜』としていたら、品種の混乱はさらにひどいことになりはしないかと心配してしまう。
私は桜文鳥が好きだが、店先のその姿に、なんと白羽の多い『ゴマ塩』が多いことだろう。『ゴマ塩』は『ゴマ塩』で楽しいし個人的に好きだが、どう考えても桜文鳥ではない。シナモンやシルバーといった海外で固定された品種がもてはやされる現在、いい加減に桜文鳥も固定化の道を探るべきではないかと思うのだが、いかがであろうか。
純白でない文鳥をすべて桜文鳥などとする事はやめる。。
問題は桜とゴマ塩の区切りが難しい点だが、桜の理想形に近づける努力をおこなえば、市場にあいまいなものやゴマ塩はいなくなるものと思う。 |
||||||||||||||||||||||||||||