 河合メンタルクリニック
河合メンタルクリニック 河合メンタルクリニック
河合メンタルクリニック
『鳴ること・響くこと・癒すこと』〜ある音楽療法の背景〜
高橋 直伸
本書の著者河合氏が二十歳から始めたバイオリンを器用に弾きこなしていたら、今日の彼の音楽療法は成立していなかったような気がする。
かつて、私は彼のバイオリンに取り組む姿勢を、「音楽でなく音苦だ」と評したことがある。その意味するところは、既にその時、河合氏自身が「セロ弾きゴーシュ」であることの証しでもあった。
音楽合宿の真の目的は、河合氏自身はもとより、周囲の関係者がそのことに気づくためだったともいえる。
合宿の朝は谷川のせせらぎでも、風の騒めく音でも、鳥のさえずりでもなく、まだ暗いうちから始める、沈黙の世界に眠るあらゆる音を突き破るような、かつ、か細いバイオリンの開放弦の練習の音で目覚めることから始まった。
私は一音楽療法家として必要な背景の一つとして重要なことは、過去に深い傷を負い、そのことをずっと忘れず面と向かい合い続ける沈黙の叫びだと思っている。
合宿を始めた頃の河合氏のバイオリンの音は、まさに、か細い叫びだった。我々もそれぞれ傷を負っていたが、まず河合氏自身が癒されなくてはならなかった。
合宿を重ねるうちに、彼のバイオリンは力強く鳴り始めた。《音》に目覚めたと言っても良いだろう。楽曲以前にバイオリンの持つ音が《鳴る》ことの重要性は、音楽家なら当然経験し、永遠のテーマであることを知っているだろう。
比喩的に言えば、河合氏が音楽家になった‥‥、その瞬間から、我々の心の中に大きな変化が現われた。彼のバイオリンの練習に苦笑していた我々がごく自然に素直になってきたのだ。まさに、我々の心の中で、河合氏のバイオリンの《音》は鳴り始め、響き始めていたのだ。彼自身が癒され始めていたのだろう。
老人フィルのために作曲していた伊東氏を始め、周囲の関係者がそれぞれのプロフェッショナルの領域で寄与したことは事実だが、合宿において伊東氏も私もほとんど音楽の話をしなかった。勝手に釣りをしたり、散歩しながら山菜を採ったりしていた。その間、河合氏は論文を読んだりしていた。そして時折、》の淋しい音が遠くから聞こえていた。それぞれが自由に自然と会話し、耳を澄ましていた。この一瞬、一瞬が癒し始めの時だった。
河台氏から、フランス音楽に背を向け孤独に自分の世界を貫いたエリック・サテイのジムノぺディを練習していると聞いた時、私は数年前に彼から聞いたパリでの工ピソードを思い出していた。ひとりの大道芸人の少女がただひたすら、ひたむきな芸を演じても人が集まらず、他の芸人の所ばかりに人が集まり、所を変え続けても同じで、少女はバイオリンケースの中に貯まった僅かなコインの一枚を取り出し、客の集まっている芸人のひとりの傍らにそっと置いて去って行った、と。その話を聞きながら私にはその少女と河合氏が重なっていた。そんな少女を追い続けた河合氏。きっと彼はその少女に心の中で工ールを送りたかったに違いない。
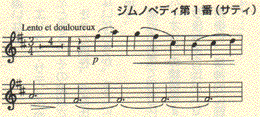
エリック・サティの曲は現在の環境音楽とはまったく違った、まさに当時のパリを背景とした癒しの音楽だと思う。その深淵さは現代人の心にも響き続けている。
きっと現在、河合氏は一暖一暖を豊かに、老人さんたちとともに鳴らし、響き、癒し合っているのではないだろうか。そこには医師も患者もいない。音楽療法はこんな背景があって初めて成立するものだろうと思う。
最近の合宿で河合氏はバイオリンに初めて触れなかった。「伊東さんと(私)と一緒に合宿していることは、バイオリンの練習をすることと同義だ」と。
今後も河合氏が「セロ弾きゴーシュ」であり続けることを期待している。
最後に、精神的に弱っている時、打楽器の音を聴くのは苦痛だが、自分が叩くと元気になるのは不思議だ‥‥。