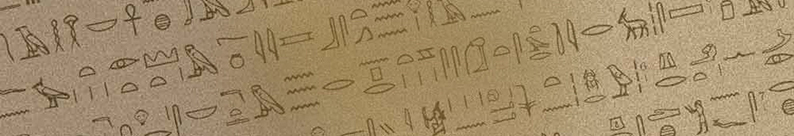
科学図書館
科
学的知識は万人のもの
(2023/07/02改訂)
科学的知識は万人によって 共有されるべきものであります。
過去においても、現在においても、科学的知識を共有する有用な手段として、本という形がとられてきました。
しかし、過去に出版された書籍は少数の例外を除いて、今日ほとんど目にすること はありません。
このサイトでは、こうしたうずもれた過去の科学的知識を万人に無償で提供するた めに、
電子的文書として提供します。さらにまた、新しい科学的知識を発表する場も提供 します。
特定の発表場所を持たない方々の発表の場でもあります。
共有されるべき科学的知識を持つ方々が、その科学的知識をこの場によって発表さ れることを望みます。
ここでいう「科学」とは、けっして自然科学に限定するものではありません。
社会科学も人文科学も当然含まれます。ただし、いわゆる文学は、含まれません。
| 『パリからの手紙』 | 1972年から2年間、科学史研究のためフランンス・パリに滞在中、筑摩書房刊行中の「数学講座」第18巻『数学史』執筆の際、編集者に送った手紙。 |
| 『雑纂』 | 村田先生が色々な媒体にかかれた小論を収録。収録作品。「芥川龍之介の弱さについて」「忙しさについて」教わることと自ら学ぶこと」「泥くささ」「学問としての数学史」「連句へのお誘い」「廣瀬健君のこと」「連句へのお誘い」 |
| 『19-20世紀の数学』(改訂版) | 筑摩書房刊『数学講座』第18巻「数学史」より、村田先生執筆の「19-20世紀の数学」部分を1冊にまとめました |
| 『数学の思想――その底に流れるもの――」 |
NHKブックス『数学の思想』(茂木勇との共著)より、村田先生が執筆された「第一部数学の思想」部分をPDF化しました |
| 「広瀬健君のこと」 | 1993年に逝去した、立教大学数学科出身の基礎論学者・広瀬健を偲んで出版された、恩師・学友たちによる追悼文集からの引用。 |
| 「ブルバキ 数学史・訳者覚えがき」 | 『ブルバキ 数学史』(東京図書、1975年6月)所収の村田全による「訳者覚えがき」。古代史に関しては、ブルバキが言及しなかった、サボーの諸説に触れている。 |
| 『論証的学問の成立』(新装版) |
版型をA5判に改めました。『科学史のすすめ』(筑摩書房刊『学問のすすめ』第18巻)所収の「論証的学問の成立」の全文。「数学」という論証的学問がいかにして成立してきたかを歴史的に説く。 |
| 『数学史散策」(増補版) | 『数理科学』(ダイヤモンド社)に連載され好評を博した「数学史散策」
を増補して同社から出版された『数学史散策』(1974年)の全文をPDF化したもの。 古代ギリシアから20世紀までの数学の歴史を概観する形で著者の数学史観を展開しながら、数学史を研究するための史料・研究論文などを著者の透徹した史観 と哲学に裏打ちされた眼力によって紹介する名著。今回誤植を訂正し、あらたに「文獻一覧」(13ページ)および「索引」(16ページ)を増補しました。 |
| 数 学基礎論の歴史――その一つの断面―― | 日本数学史学会主催「数学史講座」の講演。数学基礎論の歴史を簡潔に述べる |
| 日本固有の数学――和算 | 下記"Indigenous Japanese Mathematics, Wasan"を村田先生自ら飜訳されたもの |
| "Indigenous Japanese Mathematics, Wasan" | 「国際経済交流財団」の外国向け英文誌に掲載された、「和算」に関する論考 |
| 広 瀬君のこと | 数学基礎論学者にしてコンピュータサイエンスに造詣深かった広瀬健氏の
追悼文集に寄稿されたもの |
| 「ラ
ジオ」がむつかしい話 |
ラジオ少年だったころに感じた疑問を数学者の視点から眺めたもの。 |
| 忙しさについて |
フランスの科学史研究所に滞在して研究していたころのスケッチ |
| ギリシア数学史におけるゼノン |
ゼノンに代表されるエレア派の再評価をファン・デア・ワルデンとサボー
を中心に論じる。 |
| 数学の単一性と多様性をめぐる試論 |
ギリシアに端を発する西欧数学が唯一の数学であるかどうかの考察――
『思想』1972年4月号所収の論文、 |
| 歴史学としての数学史・科学史 |
数学史・科学史もまた歴史学の一分野である。――『思想』1977年1
月号所収の論文。 |
| 集合論史のひとこま――カントルとデデキント | 『数学セミナー』1968年12月号掲載論文に、補注をつ
けた決定版。 |
| 数学的創造の底流 |
西洋の数学的創造の底流には哲学があるが、和算にはそれがない。雑誌
『思想』513号発表原稿の増補改訂版 |
| 漁書雑録 |
若き日の村田先生が京都・神戸の書店をめぐって書籍を求めたはなし。
(単行本未収録) |
| 連続論――連続性の問題へのこだわ
り(遺稿) |
村田先生の遺稿。晩年の最大の関心事であった「連続」についての考察の
途中経過報告。遂に未完に終わりました。 |
| 数学と哲学のはざまで | 『学問の中の私』所収。立教大学理学部から桃山学院大学文学部に移った 理由を研究歴とともに述べる。 |
| 虚学のすすめ |
『学問の中の私』所収。実学でなく「虚学」こと大切だと説く。 |
| 「広重徹君のこと」 | 『数学と哲学との間』所収。旧制中学時代からお互いに切磋琢磨しあい、科学史研究の同志とも言うべきでありながら、47歳で逝った広重徹氏に対する哀惜にみちた思い出。 |
| 「フランス経験主義の数学思想」 | 『数学と哲学との間』所収。フランスの数学者、ボレル、ベール、ルベーグたちのヒルベルトの公理主義のアンチテーゼとしての経験主義を解明する。 |
| 「連続論覚え書き」 | 『数学と哲学との間』所収。数学における原子論的連続観と非原子論的連続観についてそれぞれの論者の説を対比して解説。 |
| 数学における存在 | 『数学と哲学との間』所収。数学における存在とはいかなるものかを論じる。 |
| パスカル私記 |
『数学と哲学との間』所収。集合論の歴史から見るとパスカルはどう見え るか。 |
| 来しかた行くすえ――数
学史研究の途上にて ― |
『数学と哲学との間』所収。哲学か数学か迷った末に数学を選び基礎論研
究から数学史研究にいたるまでの軌跡。, |
| 数学史における逆説の役割 |
『数学と哲学との間』所収。ギリシアのゼノンの逆理と集合論の逆理が数 学に及ぼした影響を数学史の観点から考察 |
| 数学における無限と有限の弁証法 |
『数学と哲学との間』所収。竹内啓編『東京大学教養講座1 無限と有 限』所収のものを全面的に改稿したもの。 |
| ボレルのエフェクチフ概念の形成 |
『数学と哲学との間』所収。著者最初の論文。原論文は「高崎論叢』
(1953年)に発表されたものを加筆。 |
| カントルにおける数学と哲学 |
『数学と哲学との間」に収録された中で唯一の書き下ろし。カントルの集
合
論の背景をなす哲学を論じる。 |
| カントルの集合論形成のスケッチ |
『数学と哲学との間』所収。カントルが集合論を作り上げるまでの簡明な
解説 |
| 連句へのお誘い |
村田全先生が、当時入居していた老人ホームの居住者向けに書かれた連句
へのお誘い。 |
| 数学における存在――その歴史的考察―― |
図形,数,量,集合など数学における存在とはいったい何なのかを歴史的
に論じる。 |
| 純粋数学と応用数学――その謎に関するメモ―― |
『数学と哲学の間』所収。純粋数学と応用数学についての哲学的側面に関
するメモ。 |
| 日本の数学 西洋の数学――比較数学史の試み | 初版をPDF化したもの。縦組みに改めました。なお村田先生が生前に手を入れられた改訂版は「ちくま学芸
文庫」に収録されています。 和算と西洋数学の歴史の比較を通じて,和算の特性とその限界,西洋数学 の論証的性格の由来を探求。 |
| 建部賢弘の数学とその思想 |
関孝和の弟子にして,もっとも独創的な数学者・建部賢弘の『綴術
算経』を,建部独自の数学観ないし哲学観の表出と見る著者が詳しく建部の数学思想を検討する.(数
学セミナー所載) |
| 「数
学」の
概念と数学史への視点 |
『数学と哲学との間』所収「『数
学』の概念と数学史への視
点」の全文. 数学と数学史との関係を論じて、いわゆる趣味としての「数学史」研究家や、数学を数学教育の方便と考えている数学教育者への頂門の一針. |
| 集合論史のひとこま――カントルとデデキント |
集合論のカントル、イデアル論、無理数論、自然数論のデデキントとの接
点と、カントルに及ぼしたデデキントの影響を論じながら、カントルの集合論の核心をなす概念の形成過程を論究する.「数学セミナー」掲載.のち『数学史の
世界』(玉川大学出版部)所収. |
| 集合論の背景 |
カントルの前半生における代表的論文「直線状の無限点集合について」を
種に、カントルの集合論の背後にある思想的契機をさぐる.「数学セミナー」掲載.のち『数学史の世界』(玉川大学出版部)所収. |
| 『ブルバキ 数学史』について |
邦訳『ブルバキ 数学史』の「訳者覚えがき」を大幅に加筆訂正し、あら
たに参考文献も付け加えた.ブルバキの数学史を批判的に紹介しながら、随所に著者の独自の数学史観を展開している. |
| 「中国数学の特殊性」 | 『数学史研究第二輯』所収。西洋数学、和算と比較して特殊な形態をとった中国数学の特殊性を論じる |
| 科学発達史上に於ける民主主義 | 敗戦直後、民主主義国家に生まれ変わった日本において、いかに民主主義が科学の発展に重要であるかをフランス。イギリスを例に解説 |
| 「科学史の意義」 | 教育に於ける安易な科学史の使用をいましめ、真の科学史研究は、社会・経済との関連に注目すべきだと論じる |
| 「算術に於ける実用問題の意義」 | 小学校の算数教材として、社会・経済の実態を反映した実用的なものを採用すべきと主張する |
| 『家計の数学』 | 簡単な統計の解説から初めて、物価指数、利息、定期預金、年金、生命保険など、一般家庭での数学的な問題をやさしく解説した名著 |
| 「自然科学者の任務 | ファシズムの跫音が近づいてきつつある時期に、自然科学者は戦争に協力すべきでないという勇気ある提言を述べる |
| 「数学と民族性」 | 「ナチスの数学」を提唱した、ドイツの数学者・ビーベルバッハを批判
し、日本での同様な傾向に警鐘をならした。『科学的精神と数学教育』所収。 |
| 「独 立心について」 | 「自由民権思想」、「明治政府の卑屈性」、「生活とたたかう人を」、 「林鶴一博士の独立心」を収録 |
| 「資本主義時代の科学」 | 明治から太平洋戦争に至るまでの、日本の資本主義成立から成熟までの社
会の中で、科学がいかに国策に翻弄されたかを説く |
| 「われ科学者たるを恥づ」 | 日本における近代科学の批判精神は、明治の絶対主義体制によって抑圧さ
れ、それがアジア太平洋戦争後も続いていることに対する痛切な反省の辞 |
| 「封
建数学の滅亡」 |
『数学史研究 第二輯』所収。和算は滅びるべくして滅びた理由を解明 |
| 「科学教育の歴史的基礎」 | 『数学史研究 第二輯』所収。主としてイギリス・フランスなどの西洋に おける科学教育の歴史を解説 |
| 物理学 と数学 | 『数学史研究 第二輯』所収。西洋数学と物理学の緊密な連携を説くとと
もに、日本数学=和算が、「芸の芸」として物理学とは無縁であったことも説く |
| イデオロギーの発生(数学) | 『数学史研究 第一輯』所収。数学の発展史を社会的・経済学的な背景と の関連付けで解明した歴史的論文 |
| 算 術の社会性(16世紀のイギリス算術) | 『数学史研究 第一輯』所収。「階級社会の算術」の先駆をなす論文。 |
| 階 級社会の算術 その一――文芸復興時代の算術に関する一考察―― | 『数学史研究 第一輯』所収。雑誌[思想「」に発表されるや一大セン セー ションを巻き起こした論考 |
| 階 級社会の算術その二――植民時代における南北アメリカの算術に関する一考察 | 『数学史研究 第一輯』所収。アメリカと英国の算術書の比較を通して新 大 陸アメリカの革新性と英国の保守性を描く |
| 階 級社会の数学――フランス数学史に関する一考察―― | 『数学史研究 第一輯』所収。16世紀末から18世紀初頭にかけての波 乱 万丈のフランスにおける数学の姿を描く |
| 支 那数学の社会性 | 『数学史研究 第一輯』所収。「九章算術」を通して、古代中国の社会・ 経 済状況をあきらかにする |
| 極東に於ける数学の国際化と産業革命 | 『数学史研究 第一輯』所収。日本及び中国における数学の国際化が産業 革命と結びついていることを論証する |
| 近代日本数学史概観 | 『数学史研究 第一輯』所収。江戸時代末期から、1930年代にいたる までの近代日本の数学に於ける和算の滅亡と西洋数学の興隆を社会的背景とともに説く |
| 「日本数学教育の歴史性」 | 『数学史研究 第一輯』所収。江戸時代から明治に掛けての日本の数学教 育の発展を社会と関連付けて説く |
| 「アジア的数学に就いて」 | 『数学史研究 第一輯』所収。日本・中国の数学史を研究するに当っての 小倉金之助の基本的立場を述べた小論 |
| ウィッ トフォーゲルの支那数学観に就いて | 『数学史研究 第一輯』所収。アジア的生産様式の概念を利用して中国を 「アジア的専制政治」と規定したウイットフォーゲルの主著に対して疑問を呈示 |
| 明治十年代の数学界と海軍 |
『数学史研究 第一輯』所収。明治の数学の洋算化に貢献した海軍の人々 の貢獻を説く。 |
| 数学奇談 | 『数学史研究 第一1輯』所収。数学周辺の肩のこらない三つの話題、
「ドル記号の起源」「幕末の国防のための数学」「ナンセンス書「算法珍書』」 |
| 数学者の回
想・回想の半世紀【改訂】 |
小倉金之助の二大回想記『数学者の回想」と『回想の半世紀』を一つに収 録。 |
| 日 本数学の特殊性【改訂】 | 中国に生まれ日本で独自に発展した「和算」は「学」でなく「芸」であっ
た |
| 数 学教育進展の為めに | 日本の明治以来の数学教育の歴史を通観しながら、真の民主的な数学教育
のありかたをのべる |
| 数 学教育の精神 | 数学教育の目的は、科学的精神の開発である。 |
| 数 学の大衆化 | 数学を大衆化するためにはなにをなすべきか |
| 数 学教育の意義 | 数学教育の意義は科学的精神の養成にある |
| 理 論数学と実用数学との交渉 | 中等教育に応用(実用)数学を導入することの必要性を論じる |
| 素 人文学談義 | 「マノン・レスコウ』ほか、感銘を受けた小説について語る |
| 女 性文化の歩み | 与謝野晶子から宮本百合子まで、日本の女性文化の歩みを語る、フェニニ
スト小倉の一面を示す |
| 啄 木・牧水・白秋 | 石川啄木、若山牧水、北原白秋の3人に対する忌憚のない感想 |
| ヴォル テールの恋人 | ヴォルテールの恋人にして、ニュートンの『プリンキピア』を仏訳した女
性科学者シャトゥレーの生涯と科学的業績の解説 |
| 三 上義夫博士とその業績 | 三上義夫の伝記とその業績の解説。「ある科学者の生涯」とあい補い合う |
| 林 鶴一先生のことども | 林鶴一の一周忌にあたり林鶴一を追想した記事 |
| あ る科学者の生涯 | 数学史家・三上義夫に対する愛情あふれる追悼 |
| 資 本主義時代の科学 | 明治からアジア・太平洋戦争の勃発までの要領のよい数学史 |
| 語り つぐ日本の数学 | 「数学者の回想」「回想の半世紀」とは違い、数学書の側面から小倉の生
きた時代を語る |
| 読 書の思い出 | 『数学者の回想』を補完する回想 |
| 黒板はどこ から来たのか | 教室で使われる黒板がフランスのモンジュの考案にかかり,お雇い外国人によって日本にもたらされた |
| 『科学概論』 | 科学の対象は、独自のアプリオリにより科学的認識が構成され、そのアプリオリが直観に於て統一されたものが科学である。 |
| 『科
学の価値』 | ポアンカレ著の田邊元による飜訳 |
| 最 近の自然科学 | 量子論および相対論による物理学革命を哲学者がどう解釈したかを論じる |
| 常 識、哲学、科学 | 禅の概念を媒介として、常識、哲学、科学の関係を論じる |
| 科 学政策の矛盾 | 戦前の科学政策を批判する。小倉金之助がこの論文を評価している。 |
| 科学 性の成立 | 科学性はとらわれるところのない現実即自己の実現に成立する |
| 古 代哲学の質料概念と現代物理学 | 古代哲学の質量と形相が,量子力学にどのように影響しているか |
| 世界観 と世界像 | 世界像は客観的,世界観は主観的なものとして,物理学における世界像と世界観についての論考 |
| 量子 論の哲学的意味 | ボーアの相補性原理の「田邊哲学」による解釈 |
| 大杉栄「丘博士の生物学的人生社会観を論ず」 | アナーキスト大杉栄が丘浅次郎の忠実な弟子の立場から、丘浅次郎を批判
した小論 |
| 生 物学講話 | 『進化論講話』と並ぶ古典的名著。生物の本質は「食って・産んで・死
ぬ」と喝破したことで有名 |
| 進 化論講話(増補第12版) | 名著『進化論講話』増補第12版に初版の「はしがき」と有精堂「丘浅次
郎著作集」で省略された「附録」をくわえた |
| 煩 悶の時代 | 下り坂を下っている人類には煩悶はいつまでも続く |
| 題 字、序文、校閲 | 肩書きにこだわる人は、思想上の奴隷である |
| 新 人と旧人 | 奴隷根性のある旧人とそれの無い新人。将来は新人が支配的になるだろう
という |
| 自 由平等の由来 | 自由と平等の出現を進化論的見地から説明 |
| 触 らぬ神の崇り | 権力者が自分に都合のよい信仰箇条を国民に押し付けると自然から復讐さ
れる |
| 教 育と博物学 | 学校教育における博物学の有用性を論じる |
| 落 第と退校 | 大学予備門で落第し退校した丘によるユ ニークな教育論 |
| 固 形の論理 | 固形の論理は模型にあてはまるが、自然の 実物にはあてはまらない |
| 所 謂自然の美と自然の愛 | 自然は美でも醜でもなく、また自然を愛し ても、それはごく狭い範囲にとどまる |
| 自 然の復讐 | 人類の進化につれて自然も復讐する |
| 人 類の将来 | 1世紀以前に書かれたとは思えないほど現在の状況を活写したもの |
| 芸 術としての哲学 | 経験に裏打ちされない思弁哲学は芸術と同じ |
| 人類の誇大狂 | 科学的ならざる誇大妄想的な考えを批判する |
| 境 界なき差別 | 季節の春と夏のようにあきらかに差別はできるがその境界がさだかでな い。境界は便宜上のもの |
| 所謂偉 人 | 偉人とは人間の奴隷根性がよってたかって築き上げたものと喝破した「偉 人論」 |
| 猿の群れから共和国まで | 猿の群れがいかにして共和国まで発展したかを進化論的に考察する |
| 理 科教育の根柢 | 理科教育は少人数でしかも疑いを持たせるように教育すべきという提言 |
| 疑 いの教育 | 「進化論講話」の丘浅次郎による「疑い」を基調とする教育論 |
| 三浦梅園 | 『敢語』 | 梅園の『玄語』「贅語」につぐ『~語』三部作の最後のもの。 |
| 三浦梅園 | 梅園詩集 | 三浦梅園の漢詩集。P.187~195に吉雄耕牛の訪問記あり。西洋の文物の紹介記事は科学史的に貴重な記述。 |
| 三浦梅園 |
「五月雨抄」 | いわゆる切支丹の弾圧について、諸史料を元に解説したもの。 |
| 三浦梅園 |
『東遊草』 | 三浦梅園の伊勢神宮への旅行記 |
| 三浦梅園 |
「愉婉録」 | 三浦梅園が子女を教えるために、忠臣・孝子・節婦・義僕、計38名の美談を記したもの。 |
| 三浦梅園 |
「梅園後拾葉」 | 「梅園拾葉」の続編。「追腹考」は、主君の死に追随して切腹をする制度に対する批判として注目される |
| 三浦梅園 |
「養生訓」 | 杵築藩の荒巻氏の族の夭逝にあたり遺児の為に説いた養生法。梅園曰く「これを受用すれば煩瑣なれども人を寿域に上らしむることを得ん」と。 |
| 三浦梅園 |
梅園拾葉 | 「答多賀墨卿」「再答多賀墨卿」「三答多賀墨卿」ほか、桜島噴火の記など長短取り混ぜた15編を収録 |
| 三浦梅園 |
「死生譚」 | 来客があり、たまたま死生に話が及び、「玄語」「「贅語」で論じたものをあらためて和語にて説明したもの |
| 三浦梅園 |
「梅園叢書」 | 人情世態に関する三浦梅園の所感及び訓言をやさしく書いたもの。梅園の弁証法的な考え方が垣間見られる |
| 三浦梅園 |
「帰山録」 |
三枝博音校註。三浦梅園が長崎に旅行した時の記録。宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島での決闘の模様など興味深い。なお岩波文庫「帰山録草稿」とは内容が異なる。 |
| 三枝博音 | 『梅園哲学入門』(改訂版) | 梅園を理解するうえの最上の入門書 |
| 三浦梅園 | 多賀墨郷君にこたふる書(三枝博音による現代語への書き直し) | 「多 賀墨郷君にこたふる書」の三枝博音による現代語への書き直し |
| 三浦梅園 |
元煕論 | 「自然」(おのずから、しかる)と「使然」(しからしむる)との区別を
論じた、『玄語』を理解するうえでの参考文献 |
| 三枝博音 |
三浦梅園の哲学 | 三浦梅園の哲学を、東西の哲学者の言説と対比して、日本独自の弁証法哲
学であることを解明した力作。 |
| 三浦梅園 |
三たび多賀墨卿に答ふ | 『玄語』中の「神気・本気」について、人体の構造を利用して説明する |
| 三浦梅園 |
再び多賀墨卿に答ふ | 陰陽五行説による内臓説に対して、三浦梅園の哲学的立場からの批判 |
| 三浦梅園 |
価原 | 経済学者河上肇,福田徳三が注目した,三浦梅園の「貨幣論」 |
| 矢野 弘 |
條理餘譚 | 梅園の高弟・矢野弘による「條理」についての解説 |
| 三浦梅園 |
高 伯起に復するの書 | 梅園が高伯起の質問に対して送った返答書簡。梅園哲学の本質を簡潔に説
明 |
| 三枝博音 |
梅
園の理故の哲学 |
梅園独特の「理」と「故」の概念を説く |
| 三浦梅園 |
多 賀墨郷君にこたふる書 | 三浦梅園が門弟多賀墨郷にこたえるかたちで、梅園思想の真髄を解説した 短編の原文。 |
| 三枝博音 |
梅 園の論理思想 | 三浦梅園の論理学が弁証法であることを論述 |
| 三枝博音 | 梅 園の哲学 | 三浦梅園の哲学をやや詳しく解説 |
| 三枝博音 | 梅 園の言う真実の学問 | 三浦梅園の学問論のやさしい解説 |
| 三枝博音 | 梅園哲学についての対話 | 三浦梅園への入門 |
| 三枝博音 | 三 浦梅園の自然哲学 | 三浦梅園の自然哲学者としての側面を論じる |
| 三枝博音 | 日 本人の自然解釈 | 日本人の自然哲学理解の進展と三浦梅園について |
| 三枝博音 | 日 本の科学を育てた人としての梅園 |
| 喜田貞吉 | 法 隆寺再建非再建論の回顧〔改訂版〕 | 再建論者による再建・非再建論争の回顧 |
| 関野 貞 | 法
隆寺金堂・塔婆および中門非再建論 〔改訂版〕 |
建築学者関野貞による法隆寺は再建されたものではないという有名な論考 |
| 喜田貞吉 |
関野平子二氏の法隆寺非再建論を駁す〔改訂版〕 |
歴史学者喜田貞吉による関野の非再建論に対する論駁 |
| 関野 貞 |
飛
鳥時代の建築の起原とその特質〔改訂版〕 |
飛鳥時代の建造物が、高麗尺をもって建築されていることを論証。 |
| 関野 貞 |
法
起寺・法輪寺両三重塔の建築年代を論ず〔改訂版〕 |
法隆寺非再建論で有名な関野貞が、法隆寺と関連する二つの寺院の建築年 代を論じて、法隆寺非再建論を補強する。 |
| 関野 貞 |
薬
師寺東塔考〔改訂版〕 |
薬師寺の東塔が白鳳期に建造されたことを論証。 |
| 橋本増吉 |
詩 経春秋の暦法 | 飯島・新城の春秋暦法論に対する批判。独自の説を述べる。 |
| 飯島忠夫 |
支 那古代の暦法 | 古代中国の暦法の概説。持論である西洋伝来説の根拠を簡潔に述べる |
| 新城新蔵 |
二十八宿の伝来 | 二十八宿がどこから伝来したのか、それとも古代中国で成立したものかを
論じる |
| 飯島忠夫 |
再 び左伝著作の時代を論ず | 新城新蔵「歳星の記事によりて…」に反論したもの |
| 飯島忠夫 |
漢 代の暦法より見たる左伝の偽作 | 春秋左伝の暦は三統暦をもとにしたものと論じる |
| 飯島忠夫 |
三国史記の日食記事に就いて | 古代朝鮮の正史『三国史記』の日食記事を検討する |
| 新城新蔵 |
東洋天文学史大綱 |
『東洋天文学史』巻頭をなす中国天文学史の概説 |
| 新城新蔵 |
漢
代に見えたる諸種の暦法を論ず |
『東洋天文学史』所収。漢代のさまざまな歴法についての考察 |
| 新城新蔵 | 歳星の記事によりて左伝国語の製作年代と干支紀年法の発達とを論ず | (改訂)『東洋天文学史』所収。飯島忠夫との論争と なった、中国天文学の独自 発展説を論じる |
| 新城新蔵 |
再び左伝国語の製作年代を論ず |
(改訂)『東洋天文学史』所収。「歳星の記事により て…」の続編。飯島忠夫の 批判に答える |
| 飯島忠夫 |
支那古代史と占星術 |
殷などの中国上古の年代は漢代に発達した占星術によって決められたとす る。 |
| 飯島忠夫 |
支那上古史の紀年に就いて |
戦国時代以前の上古史の年数は信用しがたいと説く。 |
| 飯島忠夫 |
支
那天文学の成立について |
新城新蔵の「歳星の記事によりて左伝国語の製作年代と干支紀念法の発達 とを論ず」に対する反論 |
| 飯島忠夫 |
支
那天文学の組織及び其起源 |
中国天文学の組織とその起源を論じたもの。殷代の存在に疑問を呈してい る。 |
| 飯島忠夫 |
支
那印度の木星紀年法の起源 |
木星紀年法はバビロニアに起源するとして,新城の中国自生説を論駁す る。 |
| 山本宣治 |
『結婚 三角関係 離婚』 | 生物学者・性科学者としての結婚はかくあるべきという提言 |
| 山本宣冶 | 『生物・人類』 | 労働者のための労働学校での生物の進化論の講義をまとめたもの。生物学者であり社会主義者である著者による生物学と社会科学との関係も記述 |
| ハーヴェイ | 『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』 | 暉峻義等訳。はじめて血液の循環を証明した著名な著書の飜訳。訳者による30ページ以上のハーヴェイの生涯及び著作文獻解説付き。 |
| 奥村鶴吉編 | 『野口英世』 | 野口英世と親しい著者が、野口の書簡その他関係者への聞き書きを元に書いた、もっとも信頼の置ける野口英世伝 |
| ルグロ | 『科学の詩人――ファーブルの生涯』 | 「昆虫記」で著名なファーブルの生涯を、親しい友人が心をこめて書いたファーブルの伝記 |
| 山本宣冶 |
「産児調整問答」 | 生物学者で、日本最初の性科学者で国会議員でありながら、右翼によって命を失った著者による労働者向けの避妊法の解説 |
| マりー・ストープス |
『結婚愛』 | イギリスの生物学者である著者が自己の体験を踏まえて、若い男女に向けて書いて世界的ベストセラーになった、性のガイドブック |
| 山本宣冶 | 「サ ンガー女史家族制限法批判』 | アメリカの産児制限運動の提唱者サンガーの産児制限に対する労働者向け パンフレットの紹介とその批判 |
| マリー・ストープス |
『結婚愛』 | 約1世紀前に出版され世界的ベストセラーになった画期的性科学書。既婚 者はもとより未婚者にも有益なバイブル |
| 山本 宣冶 | 「生 物界に於ける多角関係」――生物の諸々の行動は我々人間の模範であるか | 生物学者にして性科学者・山本宣治が、動物のさまざまな生殖の仕方をの べる |
| 山本宣治 | 『メ ンデルの一生』 | 生物学者にして性科学者・山本宣治が生物学者としての立場から著した、 奇才メンデルの伝記 |
| 小泉 丹 |
『野口英世』 | 野口と同郷の医学者小泉丹による、単なる偉人伝でない、野口の人となり と業績を冷静に評価した好著 |
| ダーウィン | 人 及び動物 の表情について〔改訂版〕 | 表情に関する多数の観察例をもとに動物から人間までを進化論的に論じた 画期的著作 |
| 大杉 栄 |
丘博士の生物学的人生社会観を論ず | アナーキスト大杉栄が丘浅次郎の忠実な弟子の立場から、丘浅次郎を批判 した小論 |
| T・H・ハックスリ | 『科学談義』 | 詩人であり小説家でもあるオルダス・ハックスレーの祖父に当たるT・
H・ハックスレーの科学に関する6本の著作を収録 |
| パストゥール | 自 然発生説の検討/自然発生について | 「自然発生説」を根柢からくつがえしたパストゥールの画期的論文と、 「自然発生説」を批判した講演録「自然発生について」を一冊に収録 |
| 加藤弘之 |
進
化学より見たる哲学 |
井上哲次郎の「哲学より見たる進化学」に反対して,科学的な立場から哲
学的理解を批判する |
| 鈴木梅太郎 |
ヴィ
タミン研究の回顧 |
ビタミンBの発見者・鈴木梅太郎の発見にまつわる苦労話 |
| 田中祐吉 |
学
問上に於ける大学派と北里派との衝突史 |
大学派と北里派との論争史。脚気菌、赤痢菌、コレラ血清問題、ペスト 菌、竹内菌、伝染病研究所移管問題、古賀液問題を扱う。 |
| 北里柴三郎 |
「ペ
スト」と蚤の関係に就て |
ペストは鼠に付いた蚤が媒介することを優しく解説。講演筆記。 |
| 志賀 潔 |
エールリッヒ伝【改訂版】 | エールリッヒの愛情あふれる伝記。エールリッヒの日常が垣間見られる。 |
| 岡田武松 |
『測候瑣談』 | 気象関係の同人が刊行していた『海と空』に掲載した、気象に関する随筆180編を収めたもの。明治から昭和に掛けての気象関係の記事が豊富。 |
| 本居宣長、 |
「新暦不審考辨」 | 宣長の「新暦考」に対する名古屋の学者による反論に対して、これを論破したもの |
| 岡田武松 |
『欧洲気象台巡回談』 | 中央気象台長・岡田武松が藤原咲平とともに、1926年にスイス・オーストリア・ドイツ・イギリス・イタリアの各気象台を訪問した訪問記 |
| 藤原咲平 |
室戸颱風と其の教訓 | 1934年四国室戸岬に上陸し、四国・近畿地方に甚大な被害をもたらし た「室戸颱風」に関する気象学者藤原咲平による簡潔な解説 |
| 西川如見 | 天文議論 | 西川如見による中国天文学および西洋の天動説の解説 |
| 小川清彦 |
谷 家天球儀の調査 | 渋川春海作の天球儀の調査記録 |
| 小川清彦 |
古 暦断見 | 上田穣の批判にこたえる形で、「古暦管見」の手法をさらに簡約にした手
法を説明 |
| 小川清彦 |
古 暦管見 | 具注暦などの暦の断簡に記載された干支などを基にいかにしてその年代を
確定するかの方法を論じる |
| 本居宣長 |
新 暦考 | 宣長の古代の暦に関する考察。日本書紀の暦日に関する考察は、小川清彦
も引用する |
| 小川清彦 |
日 本書紀の暦日の正体 | 「日本書紀の暦日について」の姉妹編。 |
| 明 治五年改暦に関する太政官布告 | 明治五年(1872年)太陰暦から太陽暦に切り替えるにあたりだされた
布告 |
|
| 小川清彦 |
日 本書紀の暦日について | 『日本書紀』の暦日が、元嘉暦と儀鳳暦によって推算されたことを明らか
にする。 |
| 小川清彦 |
宣 明暦行用時代における推算と暦日 | 日本で一番長く使われた宣明暦と渋川春海「日本長暦」、中根元圭「皇和
通暦」との異同を検証 |
| 平山清次 |
支 那暦とギリシヤ暦 | 中国の暦法のうち「太初暦」「四分暦」「元嘉暦」の定数をギリシアの暦
法と比較する |
| 平山清次 | 太 陰暦 | 世界各地の太陰暦の解説。中国と日本の暦に紙幅がさかれている |
| 平山清次 |
太 陽暦 | 太陽暦法の解説 |
| 平山清次 |
日 本に行われたる時刻法 | 江戸時代まで行われていた時刻法の解説 |
| 小川清彦 |
続 支那星座管見 | 「支那星座管見」の続編。さらにたくさんの星の同定を行う |
| 小川清彦 | 去8 月31日の新月観測 | 「新月の早見…」末尾に書かれた8月31日の新月の観測報告とその解説 |
| 小川清彦 | 新 月の早見に関するフォザリンガム限界線について | 新月が何時見えるかについてのフォザリンガムの限界曲線を東洋の記録に
基づいて修正するこころみ |
| 小川清彦 | 支 那星座管見 | 中国・日本独自のいくつかの星座を西洋の星座と同定する |
| 小川清彦 | 授 時暦の消長法と春海のいわゆる再消法について | 元の授時歴に使われた消長法と渋川春海が使ったいわゆる再消法について
の考察 |
| 小川清彦 | 哭星の同 定について | 日本および中国の歴史書に現れる「哭星」を同定する |
| 小川清彦 | 「辰 星早没夜初長」について( | 漢詩の一句「辰星早没夜初長」についての考察 |
| 小川清彦 | 『看 聞御記』に見えた新月の観測と『三正綜覧』の1誤謬 | 『三正綜覧』に見られた日付の誤りの原因を新月の日付から推理する。 |
| 小川清彦 | 新 月の見られるための条件と我邦の古記録に見えた2、3の観測 | フォンザリンガム、ショッホ、マイモニデスの新月が見られるための条件
を検討し、日本の古記録にみえた新月の記述を検討する |
| 小川清彦 | 『ユ リウス日の起日について』 | ユリウス日がなぜ紀元前4713 年1 月1 日から始まるのかの解説 |
| 小川清彦 | 『吾 妻鏡』に見えた錯簡の2天文記事 | 『吾妻鏡』に見られる天文記事の検証 |
| 小川清彦 | 「ワ レンシュタイン」の1節について | シラーの詩「ワレンシュタイン」に書かれた天文現象についての考察 |
| 小川清彦 | 右 京太夫の見た星について | 建礼門院右京大夫の和歌に現れた星についての考察 |
| 小川清彦 |
『太 平記』「稲村ヶ崎長干のこと」の話 | 『太平記』に記された新田義貞が稲村ケ崎の狭い砂浜道を渡って鎌倉幕府
を攻撃した記事の論証 |
| アーレニウス著 |
史 的に見たる科学的宇宙観の変遷〔改訂版〕 | 寺田寅彦訳。化学者アーレニウスが古代からの宇宙観の変遷を概括したも
の |
| 木村 栄 |
緯
度変化に就て |
z項で有名な木村栄(きむら・ひさし)が自身の発見になるz項を含めて 緯度変化を解説 |
| 一戸直蔵 |
誰 にも分かる暦の話〔改訂版〕 | 暦の歴史と旧暦の迷信的な暦註について説明する。 |
| 三澤勝衞 |
太陽黒点とその観測 | 太陽黒点観測の先駆者・三澤勝衞が語る太陽黒点観測法。 |
| オストヴァルト |
エネルギー | エネルギー論者・オストヴァルトの名著 |
| プランク |
エ ネルギー恒存の原理 | (石原純訳)1884年ゲッチンゲン大学の懸賞に応募し銀賞を獲得した
エネルギー恒存についての論文 |
| プランク | 量 子論の成立と従来の発展 | (石原純訳)1920年ノーベル賞受賞記念講演 |
| プランク | 理 論相互の関係 | (石原純訳)力学、電磁気学、熱力学の相互関係を論じる |
| プランク |
最 小作用の原理 | (石原純訳)最小作用の原理を歴史的にたどりながら、その意義を説明す
る |
| アインシュタイン |
研 究の動機 | (石原純訳)科学研究の動機をプランクを例に説く |
| アインシュタイン |
場 の旧及び新理論 | (石原純訳)ニュートン的「場」の考えかたと新しい「場」の考え方とを
対比する |
| アインシュタイン | 幾 何学と経験 | (石原純訳)1921年に行われた講演。ユークリッド幾何学と物理学と
の関係を述べる |
| アインシュタイン |
エー テルと相対性理論 | (石原純訳)1920年に行われた講演。エーテルの相対性理論における 意義を論じる |
| プランク |
光 の本質 | (石原純訳)1919年に行われた講演。光の光量子論の出現による新し
い光の見かたを解説する。 |
| アインシュタイン |
相 対性理論 | (石原純訳)1911年チューリッヒ自然科学会席上の講演 |
| プランク |
力 学的及び統計学的法則性 | 量子力学及び統計力学における統計学的法則性を論じる |
| プランク |
物理学 的認識の新軌道 | 古典的な力学的認識が量子論によって新しい軌道にはいった |
| プランク |
力学的自 然観に対する近代物理学の立場 | 古典的な力学的自然観が,相対論及び量子力学によって変革をせまられる
ことを論ずる |
| プランク |
物 理学的世界形像の単一性 | 物理学的世界形像(Weltbild)の単一なることを述べ,マッハを
批判する |
| 仁科芳雄 |
量 子論に於ける客観と因果律 | 量子力学における不確定性原理と因果性の関係 |
| 愛知敬一 | 電 気学の泰斗ファラデーの伝 | ファラディの伝記および業績。 |
| 仁科芳雄 |
Niels Bohr | ニールス・ボーアの学問に重点を置いた伝記。 |
| オストワルド |
エネ
ルギー |
全面改訂版。以前の横組みを縦組みに代え、誤植訂正しました。 |
| 佐藤勝造 | 「原論第I巻の目標はピュタゴラスの定理であるのか」 | ユークリッド『原論第I巻」の目標ピュタゴラスの定理であるという定説に対する反論(著作権者許諾済) |
| 梅田宗宏 |
「九章算術『圭田』考」 | 古代中国の算術書『九章算術』中の「圭田」は通説のように「二等辺三角形」ではなく、一般の三角形であることの論証。著作権lはフリーです。 |
| 建部賢弘 |
『綴術算経』 | 和算書の傑作。独自の数学方法論を説いたものとして有名 |
| 藤原松三郎 |
和算――『文部時報』所収―― | 和算の歴史と、その長所・短所を簡潔に論じた和算の解説。「文部時報」
所収 |
| 林 鶴一 | 関 孝和の事蹟に就いて | 関孝和の生涯と事跡についての簡単な解説 |
| 林 鶴一 |
三 上義夫君の論文に就て | 三上義夫の円理に関する論文に対する反論 |
| 藤原松三郎 |
支 那数学 | 古代中国の数学概説の講演。 |
| 三上義夫 |
日
本数学史【改訂】 |
和算の簡潔な歴史。三上ならではの創見がある |
| 藤原松三郎 |
和 算史の研究 I〔誤植訂正〕 | 藤原が和算を本格的に研究しはじめてからの最初の論文 |
| 藤原松三郎 |
余 の和算史研究 | 藤原松三郎の和算研究の10年にわたる道程 |
| 藤原松三郎 |
和
算――東北帝国大学学士試験合格証授賞式記念講演 |
1945年9月、東北帝国大学卒業式での記念講演。和算の概説と西洋と
の比較を論じる |
| 藤原松三郎 | 和 算に現われたる我が国民の帰納力 | 和算における帰納法の利用のしかたを建部賢明を例に説明する |
| 三上義夫 |
和 算の社会的・芸術的特性について | 和算は科学ではなくて,芸術であった |
| 三上義夫 |
芸 術と数学及び科学 | 芸術と数学との関係を東西の文化について論じる |
| 三上義夫 |
数 学史の研究に就きて | 三上義夫の数学史研究の遍歴 |
| 三上義夫 |
東西数学史【改訂版】 |
和算・中国数学史に詳しく,インド・アラビア・西洋については,カジョ
リによって記述されている。 |
| 三上義夫 |
文 化史上より見たる日本の数学 | 江戸時代に特異な発展をした「和算」は「学」ではなく「芸術」だった |
| 討
論について |
石原辰郎からの反に対する短いコメント |
| 科学としての哲学 |
唯物論は哲学でなく、思考の法則の科学こそ哲学である |
| 自然科学的世界像の問題 | 『科学』1937年4月号「自然科学的世界像」特集号掲載の田辺元、石
原純の論考に対する考察 |
| 唯
物論の貫徹のために |
加藤の主観性論に対する川西、石原、森の批判に対する反批判 |
| 『ブルジョア的制限』と誤訳 | 自身の誤訳を種に、当時の党派的な恣意的誤訳を指弾する |
| 注目すべき一論文 | 経済学者による一般法則と特殊法則についてのコメント |
| 歴史概念論議について | 石原辰郎と森宏一の論争についてのコメント |
| 哲学の対象 | 哲学の対象は純粋思惟の法則=認識論。 |
| 主観性の問題 |
「主観」と「主体」についての論争を呼んだ論文。 |
| 『フォイエルバッハについて』第一 テーゼの一解釈 | マルクスの「フォイエルバッハに関するテーゼ」の1に関する解釈。当時
物議をかもした。 |
| 「自然弁証法と形式論理学」の問題 | 岡邦雄「自然弁証法と形式論理学」に対する批判。 |
| エンゲルスと自然科学研究 | 党派性批判をして、唯物論研究会内部で激しい批判を引き起こした問題の
もの。 |
| 批判に答えて | 「わが弁証法的唯物論の回顧と展望」の批判に対する反批判 |
| 理論の党派性について梯氏に | 弁証法的唯物論の理論には党派性があるかどうかについての梯明秀氏との
論争 |
| わが弁証法的唯物論の回顧と展望 | 唯物論研究会発足にむけて、弁証法的唯物論とは何かを説く。 |
| 『自然弁証法』邦訳書への序言 |
エンゲルス著『自然弁証法』の翻訳書につけた弁証法的唯物論の的確な解
説。 |
| 弁証法的唯物論への道 |
弁証法的唯物論にいたる歴史を概観する |
| 三木哲学に対する覚書 | 「異端」の唯物論者、加藤正の処女論 文。三木を批判する舌鋒は鋭い。 |
| 『自然弁証法』下巻所収「訳者よ り」 | 『自然弁証法』下巻につけた自然の弁証法の意義を説いたもの。 |
| 理論の党派性の問題並に党派性イデ オロギーに就て | 加藤正が、治安維持法違反で逮捕された際に、東京地方裁判所検事局宛て に提出した手記。理論に党派性があるのか、客観的なものがについて、加藤の立場を詳述する。 |
| 唯物論の立場 | 思考の弁証法を唯物論的認識のあらゆる方面に適用することが大切だ |
| 唯物論における哲学の問題 | 唯物論的弁証法での哲学の位置につてい論じる |
| デートン・ミラー『火花・稲妻・宇 宙線』訳者のことば | 加藤正の科学論ともいうべきもの |
| ダンネマン『大自然科学史』第6巻 訳序 | 19世紀初頭の科学史概説 |
| 三百年祭と四百年祭 | ガリレイの400年祭とニュートンの300年祭にかこつけた、ガリレオ とニュートンに関する小話 |
| 自 然弁証法の研究の発展史 | 大正末から昭和の初めにかけて,主として日本で行われた自然弁証法の解
釈に関する論争を展望しながら,加藤の自然弁証法観をのべる |
| ダンネマン『大自然科学史』改訂版 はしがき | 『大自然科学史』改訂版発刊に際しての「はしがき」 |
| レッシングと合理的精神 | 加藤正の死後発表された合理主義者レッシング論 |
| ダンネマンのことども | 大著『大自然科学史』の著者ダンネマン小伝 |
| マルクス主義の定義 | マルクス主義の定義に関する小論 |
| 合理主義の立場 | 非合理的なものは存在しない。現実の一限定、問題と見て解決を合理的な ものに見るのが合理主義である |
| デー
トン・ミラー『火花・稲妻・宇宙線』訳注より |
科学解説者としての加藤正の一面がよくわかる。1930年代,40年代
の科学の現状についての適確な解説。 |
| 「社会事情と科学的精神」 | 1932年の五・一五事件、1936年の二・二六事件など、迫りくるファッショ化の傾向に対する科学者の抵抗をあらわす文章 |
| 『自然科学的世界像』 |
下記の『自然科学的世界像」と記載のある論文を1冊にまとめた書籍そのままの体裁にしてあります。新字・新かな・割注付:内容::序// 第一部(現代物理学上の諸成果//アインシュタインの字宙論と思惟の究極/アインシュタインの理諭に対するその後の状勢/宇宙の大きさ/量子論の起原/量 子力学への理解//不確定性原理について/原子核の秘密/エディントン著『陽子及び電子の相対性理論』/物理学的世界像)//第二部(一般的諸問題/数学 に於ける具象性/自然科学に於ける物質概念/自然科学的知識の限界/自然科学としての医学/自然科学のルネッサンス}//第三部(認識論に関する問題/ 物質と空間時間との必然的関係/現代物理学に於ける時間空間概念及び実在の本質/自然の偶然性/自然の因果性と認識論/時間の非可逆性について/認識と説 明/物理学上の概念に対する唯物性の意味について/自然科学の方法としての観察、実験等について) |
| 相 対性原理〔改訂版〕 | 相対性理論(特殊・一般)を数式を最小限にした、わかりやすい解説。 |
| 物 理学概論(改訂・増補版) | 物理学者でありながら、哲学にも造詣 の深い石原純による物理学概論。量子力学誕生直後の物理学の認識論的危機を踏まえて哲学的に論じる。このたび,『岩波講座・物理学及び化学』の増 補版により第4章を追加した。 |
| 認 識と説明 | 『自然科学的世界像』所収。説明は物理学的理論においての目的ではない |
| 時 間の非可逆性について | 『自然科学的世界像』所収。物理学において空間は可逆であるのにどうし
て時間は不可逆なのかを考察する |
| 自然の因果性と認識論 | 『自然科学的世界像』所収。量子力学によって因果性は確率論的になった |
| 自然科学のルネッサンス | 『自然科学的世界像』所収。20世紀のルネッサンスである、相対論と量
子論について述べる |
| 自然科学に於ける物質概念 | 『自然科学的世界像」所収。相対論によって質量とエレルギーが統一され
るまでの概史 |
| 物理学的世界像 | 『自然科学的世界像』所収。相対論および量子力学のよって古典的力学像
の変更を解説 |
| エディントン著『陽子及び電子の相対性理論』 | 『自然科学的世界像』所収。エディントンの著書の紹介 |
| 原子核の秘密 | 『自然科学的世界像」所収。原子核の発見についての丁寧な解説 |
| 不確定性原理について | 『自然科学的世界像』所収。不確定性原理についての解説 |
| 『自然科学的世界像』序 | 『自然科学的世界像』所収。 |
| 『科学のために』序言 | 『科学のために』の序言。この書の編まれた理由をのべる。太平洋戦争直
前に刊行された意義はおおきい |
| 科学的技術の国家管理 | 『科学のために』所収。科学技術の発展は科学者・技術者の自由な発想に
まかせるべきで,管理は好ましくない |
| 自然科学の趨勢 | 『科学のために』所収。相対論,量子論などの当時最新の理論の解説とド
イツや日本における科学政策の批判 |
| 自然科学研究の態度 | 『科学のために』所収。自然科学の研究には,実用主義と理想主義が必要
である |
| 現時局と純正科学の問題 | 『科学のために』所収。戦時には純正科学は無用だとする論に対する理路
整然とした反論 |
| 前大戦と科学者 | 『科学のために』所収。戦争に翻弄された科学者の話。戦死したシュバル
ツシルド,ナチスの心酔したシュタルクなど |
| 科学用語の問題 | 『科学のために』所収。「磁界」と「磁場」,「電界」と「電場」など,
同一事象に対する用語の統一をうながす |
| 『神風』と日本文化 | 『科学のために』所収。飛行機『神風』がヨーロッパ往復の偉業をなしと
げたが,手放しで喜べない理由がある |
| 欧洲動乱と我国の科学界 | 『科学のために』所収。第二次大戦直前に,戦争による科学研究の影響を
憂える |
| 科学的精神の問題 | 『科学のために』所収。合理的に思考することが科学的精神を養う |
| 科学と人生 | 『科学のために』所収。科学の限界を見極めるとともに非科学的なものに
対する見る目をつけることを説く |
| 満洲に於ける科学教育の現状 | 『科学のために』所収。日本が建国した「満洲国」における教育について
の提言 |
| 教育制度の革新 | 『科学のために』所収。戦時体制に合う教育制度の改定に対する提言 |
| 技 術に於ける独創性 | 『科学のために』所収。技術の独創性を保証すべき |
| 科学と技術との関係について | 『科学のために』所収。技術は社会体制によって規制される |
| 科 学的技術に関する現時の諸問題 | 『科学のために』所収。いわゆる「支那事変」以後の科学と技術はどうあ
るべきか |
| 技 術の国家的意義 | 『科学のために』所収。科学技術の振興に対する政治の役割を考える |
| 科学理論とその応用 | 『科学のために』所収。科学を応用するためには,基礎的な研究がかかせ
ない |
| 科学と思想との交渉 | 『科学のために』所収。自然科学と思想との相互作用を説く |
| 日本に於ける科学の将来 | 『科学のために』所収。「日本的科学」ではなく,自然科学的な思考方法
の普及こそ大切と説く |
| 科学時評 |
科学予算の配分,研究の統制に対する批判 |
| 科学振興論について | 『科学のために』所収。いわゆる「日本的科学」に対する批判 |
| 文化政策へ望む | 『科学のために』所収。文化統制特に科学に関する統制への要望 |
| 科学研究統制の問題 | 『科学のために』所収。太平洋戦争直前,国家による科学研究の統制に反
対する |
| 科学政策の革新 | 『科学のために』所収。基礎科学振興の重要性を説く |
| 科
学教育の原理的認識 |
『科学のために』所収。科学教育はどうあるべきかを論じる。いななおその価値を失わないだろ
う。 |
| 科
学的精神とその養成 |
『科学のために』所収。戦争前夜、科学を軽視する世相に対する頂門の一針。 |
| ア
インシュタインの宇宙論と思惟の究極 |
『自然科学的世界像』所収。アインシュタインの宇宙論を解説し,この論文発表時点における問題点を述べる。 |
| ア
インシュタインの理論に対するその後の状勢 |
『自然科学的世界像』所収。アインシュタインの相対論発表以後のさまざまな検証についてのべる |
| 宇
宙の大きさ |
『自然科学的世界像』所収。アインシュタインの相対論発表以後,ハッブルの膨張宇宙の発見によりう宇宙大きさが拡大した |
| 現
代物理学に於ける時間空間概念及び実在の本質 |
『自然科学的世界像』所収。時間と空間は物理学的理論のなかにのみ存在する。 |
| 自
然の偶然性 |
『自然科学的世界像』所収。自然の法則性又は因果律なるものは、それの根本的要素としての量子現象に於ては認められない |
| 自
然科学としての医学 |
『自然科学的世界像』所収。量子論の不確定原理を引き合いにだしながら,医学の科学性を論じる |
| 自
然科学の方法としての観察、実験等について |
『自然科学的世界像』所収。戸坂潤『科学論』に対する批判。 |
| 自
然科学的知識の限界 |
『自然科学的世界像』所収。量子論および宇宙論によれば自然科学の知識
は有限であるとする |
| 「数
学と弁証法」の問題 |
『自然科学的世界像』所収。俗流唯物論者の微積分に数学の弁証法を見る のを批判し、変分法に弁証法 があると論じる。 |
| 数
学に於ける具象性 |
『自然科学的世界像』所収。数学は抽象的な部分だけでなく、具象性も大 切だと説く。 |
| 物
質と空間時間との必然的関係 |
『自然科学的世界像』所収。空間と時間は物理学においては観念ではなく
て実在である |
| 物
理学の概念に対する唯物性の意味について |
『自然科学的世界像』所収。俗流唯物論者の浅薄な物理学の唯物論的解釈 に対する頂門の一針 |
| 量
子力学への理解 |
『自然科学的世界像』所収。量子力学が因果性を否定したという俗論に対
する反論 |
| 量
子論の起源 |
ハイゼンベルク・シュレーディンガーによる量子力学の成立にいたる量子
論の歴史 |
| 力
学的自然観に対する近代物理学の立場 (マックス・プランク著・石原純訳) |
マックス・プランクが1910年9月23日にドイツ自然科学者及び医学者 年会で行った講演 |
| ニュー
トン200年祭に対するアインシュタイン教授の感想(アインシュタイン著・石原純訳) |
アインシュタインがニュートン力学の功績と限界を論じた講演 |
| 科学史 |
明治から大正にいたる日本の科学の歩みを文献にそくして記述したもの。 通史というよりは文獻案内として有用。 |
| 『科学史考』 | 下記に『科学史考』所収とある論文を、単行本と同じ順序に並べて1冊にしたもの。注釈と振り仮名を増補しました。 |
| 『物理学と認識』 | 下記にある『物理学と認識』所収の作品を1冊にまとめたもの。 |
| アインシュタイン伝 |
アインシュタインを訪問したアインシュタインと同時代の桑木が、アイン シュタインの人となり、業績、及びローレン、プランクなど面会した物理学者の素顔を活写する。 |
| 速 度加速度の話・運動の分解・振動 | 雑誌『中等教育』に掲載された、力学のやさしい解説 |
| 説 明と記載 | 説明と記載の違いについて論じる |
| 我 が国科学界の発達 | 名古屋における講演。明治前の日本における科学の発達を概観したもの |
| 〔『物理学と認識』〕序 | 『物理学と認識』所収。序文 |
| 九州に於ける理学の先駆 | 『物理学と認識』所収。九州ゆかりの江戸時代の科学者のスケッチ |
| ダランベールの力学 | 『物理学と認識』所収。ダランベールの力学についての解説 |
| (桑 木彧雄著『黎明期の日本科学』)序 | 『黎明期の日本科学』所収。桑木彧雄の実兄・桑木厳翼が『科学史考』か
ら抜粋した 『黎明期の日本科学』に寄せた序文 |
| 貝原益軒の大疑録 | 『科学史考』所収。貝原益軒の「大疑録」の諸版についての考察 |
| プリンシピア英訳書の飜刻其他 | 『科学史考』所収。ニュートンの『プリンキピア』の英訳にまつわる話 |
| フランシス・ベーコンに就て | 『科学史考』所収。帰納論理の先駆者フランシス・ベーコンをめぐる諸説
を紹介する |
| ガリレイに就て附、海潮古説 | 『科学史考』所収。ガリレオ・ガリレイと潮汐についての古今の説の紹介 |
| 欧洲古本屋の思出 | 『科学史考』所収。桑木が訪問したヨーロッパの古書店についての雑談。
古書店でA.コイレに出会った話など |
| 科学雑誌について | 『科学史考』所収。内外の科学雑誌についての簡明な解説 |
| 筆 蹟の蒐集 | 『科学史考』所収。著名な科学者・文学者などの筆跡の蒐集にまつわる話 |
| 師・友・書籍 | 『科学史考』所収。巡り合った師と友人、書籍などについての随想 |
| ラザフォード卿への追憶 | 『科学史考』所収。ラザフォードと日本の科学者との交流が記されている |
| 山川先生 | 『科学史考』所収。物理学者で東大総長、九大学長、京大総長を歴任した
山川健次郎への追悼文2編 |
| 「科 学と気分」 | 『科学史考』所収。シュレージンガーの表題の随筆集の紹介 |
| 「科学と文学」(寺田寅彦博士著随筆) | 『科学史考』所収。寺田寅彦の「科学と文学」のなかに、寺田の実証主義
の傾向を見ている |
| 中村清二博士著「田中舘愛橘先生」 | 『科学史考』所収。中村清二『田中館愛橘先生』の簡潔な紹介 |
| ギッブス全集の集註二巻 | 『科学史考』所収。ギッブスの論文集に対する註釈が刊行されたことの解
説とギッブスの簡単な伝記 |
| 「アリストテレスの物理学」 | 『科学史考』所収。物理学の理論にもプラトン派とアリストテレス派があ
る |
| 最近六十年間の物理学の発達 | 『科学史考』所収。1936年から干支一巡前の1876年からの物理学
の発達を概観する |
| 雑記 | 『科学史考』所収。――「ダンテの宇宙観」「ヘルムホルツの誕生百年」
「ビザ斜塔の実験の結果」「ロシヤの科学者」「エミール・ブートルーの偶然の哲学」「フランスの大学とアメリカの学者」「フランスの理学」「科学者と政
治」「マッハと相対性原理」 |
| 自然哲学界(1936年) | 『科学史考』所収。相対性理論および量子力学成立以後の科学哲学の潮流
の概観 |
| メイエルソン氏の科学哲学 | 『科学史考』所収。メイエルソンの科学哲学を解説する |
| メイエルソン氏の認識論 | 『科学史考』所収。化学者から科学哲学家に転じたメイエルソンの認識論
を解説する |
| ポアンカレの追憶 | 『科学史考』所収。アンリ・ポアンカレの追憶。ポアンカレと会ったと
き、フランス語ではなくドイツ語で会話した挿話などある |
| マッハの世界観 | 『科学史考』所収。マッハの哲学的主義は「ポジティビズム」である。 |
| ファラデー及びマクスウェルに依る物理学の変革 | 『科学史考』所収。ファラディとマックスウエルによる場の理論によって
従来の物理学が変革されたことを論じる。 |
| レ オナルド・ダ・ヴィンチの力学、其他 | 『科学史考』所収。ダ・ヴィンチの力学的考察、とくに天秤のつり合いに
ついてアルキメデスとの対比で論じる |
| 文化と科学 | 『科学史考』所収。ヨーロッパにおける科学の発達についての文化史的考
察 |
| アリストテレスとアルキメデス | 『科学史考』所収。アリストテレスとアルキメデスの事跡についての論
考。文獻案内も兼ねる |
| 力学の原則に就て(1) | 『科学史考』所収。力学の原則の発展史をギリシャから量子力学まで展望
する |
| 力 学の原則に就て(2) | 『科学史考』所収。「力学の原則に就て(1)」の簡約版。発表媒体の違
いによる |
| ギリシャに於ける物理的科学の発生 | 『科学史考』所収。ギリシャにおける物理的思考を考察する |
| 磁石及琥珀に関する東洋科学雑史 | 『科学史考』所収。磁石と琥珀に関する古代中国から日本に至る論考 |
| エ
レキテル物語――平賀源内と橋本曇斎 |
『科学史考』所収。エレキテルに関する歴史 |
| 学
術史の断面――西暦一六〇〇年の東洋及西洋―― |
『科学史考』所収。1600年前後の西洋と東洋に於ける科学的な動きを比較する。 |
| 博
多独楽 |
『科学史考』所収。博多こまに関する考察 |
| 帆
足万里 |
『科学史考』所収。「窮理通」で有名な帆足万里の事績の解説 |
| 科
学史の研究 |
『科学史考』所収。科学史学会創設に当って,科学史の研究とはいかなるものかを論じたも の |
| カ
ントの最初の論文に就て |
『科学史考』所収。デカルト、ニュートン流の運動の概念とライプニッツ流の運動の概念につ いてカントがいかに考察したかの解説 |
| 「毛
抜」其他 |
『科学史考』所収。歌舞伎一八番「毛抜」に使われている磁石の話 から電磁気の歴史に及ぶ |
| 本
木仁太夫良永の事績――長崎の阿蘭陀通詞、地動説の我国最初の解説者―― |
『科学史考』所収。長崎のオランダ通詞にして、地動説の我国最初の解説者、本木良永の業績 の解説 |
| 長
岡半太郎博士著「随筆」 |
『科学史考』所収。長岡半太郎『随筆』の紹介 |
| ニュー
トン |
『科学史考』所収。ニュートンの小伝 |
| 新
日本史物理学篇 |
『科学史考』所収。明治期からの日本の物理学の歩みを概説 |
| 泰
西科学の摂取と其の展開 |
『科学史考』所収。江戸期にいかにして西洋科学が受容されたかを論じる |
| 寺
田博士の手紙 |
『科学史考』所収。寺田寅彦の手紙を紹介しながら、在りし日の寺田を偲ぶ |
| 指
南車及羅針盤史雑考 |
『科学史考』所収。古今東西の指南車に関する史料を駆使して、その歴史を明らかにする |
| 文
芸上の描写論と科学 |
『物理学と認識』所収。文芸の運動としての描写論と科学上のマッハ主 義、ラッセルの論理主義との関係を論じる。 |
| 物
理学と認識 |
物理学においては、マッハ流の経験論 は成り立たないと論じる。『物理学と認識』(大正11年)の トップを飾る論考。 |
| 力
の観念の歴史的発達 |
『物理学と認識』所収。力の概念の歴史的発展をのべる。 |
| ア
インスタインの哲学〔改訂版〕 |
『物理学と認識』所収。相対性理論と当時の哲学との関係を解説する。 |
| 研
究と科学教育 |
『物理学と認識』所収。「研究所の三種」「研究所の組織」「独逸流の大学」「英仏学者の評」 「学会の覇王」「科学の人道化」を収める。 |
| 熱
力学の方法 |
『物理学と認識』所収。エネルギティークと熱輻射論者との論争を解説する。 |
| 物
理学上の認識の問題 |
『物理学と認識』所収。マッハ流の認識論と実在論的認識論とを論じる。 |
| 絶
対運動論 |
『物理学と認識』所収。絶対運動の概念を歴史的に解説する。 |
| 『量
子力学史」(改訂版) |
天 野の主著。量子力学の形成過程を豊富な資料をもとに描く。版型をA5に改ため、著者写真、略歴を追加 |
| 自 然哲学と人間文化 | ボーアが1938年コペンハーゲンで開催された人類学および人種学国際
会議で行なった溝演 |
| 熱輻射論と量子論の起源(改訂版) |
『量子力学史』と双璧をなす名著.。改訂版では、新しく組み直し、漢字のふりがなを増補した。 |
| 熱 輻射史 | 熱輻射の発展史 |
| Heinrich
Hertz の生涯と業績 |
電磁波を発見したヘルツの伝記 |
| ウェ
ツジウッド |
イギリスの陶器製造家ウエッジウッドについての小論 |
| エ
ネルゲティーク前史 |
オストワルドのエネルギー一元論に到るまでと,その批判のスケッチ |
| 光
と生命(N・ボーア著) |
光の相補性から初めて生物の相補性,光と生物との関係を述べる |
| 古
典力学の展開と不可逆性 |
古典力学から,熱力学,統計力学への発展過程を展望する。 |
| 国
立物理工学研究所設立の歴史 |
ジーメンスの尽力によって設立されたドイツの国立物理工学研究所の業績
を述べる |
| 世
界観と物理世界の存在構造 |
古典力学的世界観とカント・ヘーゲルなどの古典哲学との関係を論ずる |
| 物
理学の現実的基礎 |
不確定原理,光の粒子説と波動説など物理学の根本にかかわる問題を論じ る。 |
| 物
理学と数学に関する覚書 |
量子力学を例にとり,物理学と数学とのかかわりを論じる |
| 不
確定関係の直観的導き方への注意 |
ハイゼンベルクの不確定性理論を直感的に導く場合の注意 |
| 物
理学者ウィーンの回想記 |
ウィーンの回想記を中心に第一次世界大戦前後のウィーンの生活と研究を 描く。 |
| 理
論と実際 |
理論の限界をわきまえれば、実際の現象をよく 説明できると説く。 |
| 科
学を修める道 |
開成中学校での講演。身近な現象を科学することを通じて科学の研究法を 述べる |
| 精
確さの必要限度 |
一見必要以上の精度と見えるものも、実はそれによって科学が進歩する |
| 太
陽の黒点は果たして地球上の気候に影響するか |
太陽研究の第一人者が,古くて新しい問題である,太陽黒点と気候との関 係について述べたもの |
| 天
界現象の予報 |
天文現象の予報は、統計的予報から力学に基づく予報に変ることによって 精確にった。 |
| 日食回顧〔改訂版〕 |
大正15年の日食によせて、古今東西の日食についての物語 |
| 北
見日食の思出〔改訂版〕 |
1936年北海道北見近郊で起きた皆既日食の様子を伝える |
| 迷 信 | 陰陽五行・九星など、暦にまつわる迷信を徹底的に批判 |
| 科 学と迷信 | 暦にまつわる迷信を科学的見地からその誤りを解説 |
| 東洋天文学史大綱 | 『東洋天文学史』巻頭をなす中国天文学史の概説 |
| 漢 代に見えたる諸種の暦法を論ず | 『東洋天文学史』所収。漢代のさまざまな歴法についての考察 |
| 再び左伝国語の製作年代を論ず | (改訂)『東洋天文学史』所収。「歳星の記事により て…」の続編。飯島忠夫の 批判に答える |
| 歳星の記事によりて左伝国語の製作年代と干支紀年法の発達とを論ず | (改訂)『東洋天文学史』所収。飯島忠夫との論争と
なった、左伝の製作年代を
論じた論文。『東洋天文学史研究』所載のもの |
| 月 |
『宇宙大観』所収。月にまつわる基本的な知識を解説 |
| 宇
宙と人生 |
『天文大観』所収。宇宙と人生という問題を天文学の分野で科学的に考察 する。 |
| 宇
宙の大法 |
『天文大観』所収。宇宙の大法=万有引力についての随想 |
| 七
夕の宇宙観 |
『宇宙大観』所収。七夕の星を題材に現代天文学の知見を語る |
| 秋
の夜の月に対して |
『天文大観』所収。月見の季節に新聞に掲載された、和歌や漢詩を引用し た月に関する随想。 |
| 初
日の出 |
『天文大観』所収。初日の出によせて、古今東西の太陽にまつわる逸話と 太陽の天文学的意義を説く |
| 法
華と天文 |
『天文大観』所収。法華経を天文学的に解釈するという、ユ ニークな論考 |
| 天
文大観 |
『天文大観』所収。天文学と人間とのかかわりを古代から現代までに亘っ て説 く。 |
| 宇
宙の大を見よ |
『宇宙大観』所収。内容:星祭/天行健/惑えるは星か人か/百億の太陽 /火星と人/流星/渦巻/七夕物語 |
| 夏
の夕の天文 |
『宇宙大観』所収。七夕に関連して、牽牛織女のはなし、さそり座のアン タレスと星の進化な どを論じる。 |
| 火
星と人 |
『宇宙大観』所収。火星人はいるかどうか、火星とはどんな星かなどを解 説 |
| 真
如の月 |
『宇宙大観』所収。月にまつわる基本的な知識を解説 |
| 太
陽と流星 |
『宇宙大観』所収。太陽の自転も地球の自転も流星の落下が原因とし、流 星団が星を形成したとする。 |
| 大
文字 |
『宇宙大観』所収。京都の大文字焼きによせて、天文・地文の意味を読み 取る意義を説く |
| 地
球進化論 |
『宇宙大観』所収。太陽系の成立から初め地球における水の役割を論じ, 生物の誕生におよぶ |
| 天
地初発の時〔改訂版」 |
『宇宙大観』所収。星と惑星は、原始流星団が凝集して生成されたとい う、新城流「宇宙生成論」の解説 |
| 富
士山頂太陽観測所 |
『宇宙大観』所収。富士山頂に太陽観測所を設置せよという提言。これが 後の乗鞍のコロナ観 測所になったか。 |
| 彗
星 |
『宇宙大観』所収。彗星を解説し、彗星は「流星団」から生まれたとと く。 |
| 七
夕物語 |
『宇宙大観』所収。七夕の起源を中国の古典を引用して解説。『宇宙大 観』所収。 |
| 牽
牛織女 |
『天文大観』所収。七夕の伝説によせて、日本および中国の文学作品を縦 横に引用しな がら、宇宙の初期に無数に存在した流星が凝集して星ができたという、新城独自の宇宙論をも展開する。 |
| 『伝記・憶い出』 |
科学者の伝記と想い出を綴ったもの。収録人名:キルヒフォッフ、ヘルム
ホルツ、ワイエルシュトラス、ポアンカレ、フランツ・ノイマン、ストークス、ラグランジュ、ライプニッツ、ファラデー、ニュートン、ロジャー・ベーコン、
ギルバート、ネーピア、ドルトン、ヤング、ジュール、W.トムソン、マックスウェル、ボルツマン、バルフォア、J.J.トムソン、佐藤秀也、キュリー夫
人、 |
| 理 学史に現われたるイギリスの十哲 | イギリスの科学者:Roger Bacon; Gilbert;
John napier; Isaac Newton; John Dalton; Thomas Young; Michael Faraday;
James P. Joule; William thomson; J.C. Maxwellの業績を解説 |
| 一 週間の剣橋大学寄宿舎生活 | 学会出席のためにイギリスのケンブリッジ大学の学生寮に滞在したときの
話 |
| 総 長就業と廃業 | 理研にいた著者が大阪帝国大学初代総長になるまでの顛末 |
| ポアンカレ小伝 | アンリ・ポアンカレの簡潔な伝記。桑木彧雄「ポアンカレの追憶」にこの
小伝についての言及がある |
| キ
ルヒホッフ略伝 |
偉大な実験物理学者キルヒホッフの略伝 |
| マ
イケール・ファラデーの事跡 |
ファラディの伝記と業績の紹介 |
| ヘ
ルマン・フオン・ヘルムホルツ先生小伝 |
ヘルムホルツ葬儀の日にミュンヘンにて記したヘルムホルツの簡潔な伝記 |
| 数
理物理学の趨勢に関するボルツマン先生の意見 |
1899年9月22日、ミュンヘンの「万有学会」でアトミズティークの ボルツマンがエネルゲティークと現象論者を批判した講演の要旨の紹介。 |
| ラ
イブニッツを弔う |
1916年,ライプニッツ没後200年祭にあたり,ライプニッツの小伝
を書いたもの |
| 科
学者としてのライブニッツ |
ライプニッツの科学者としての側面を伝記的に述べる。ライプニッツ没後 200年を記念しての哲学会での講演 |
| シ
ベリアの風物〔改訂版〕 |
シベリア横断鉄道でシベリアを横断したときの随想。明治人の漢学の素養 が伺われる。 |
| 族
日記より |
1935(昭和10)年アメリカを経てフランスに旅した紀行。 |
| 研
究の自立 |
研究は研究者自身で経済的基盤を作って行うべしというユニークな論 |
| 物
理学者の苦み |
相対論、量子論の誕生にと まどう物理学者に的確な批評の必要性を説く。 |
| 物
理学革新の一つの尖端 |
原子核の内部構造が解明される前夜の物理学界のすがた。まだ中性子とい う語はない。 |
| 大
震雑感 |
関東大震災に遭遇した科学者の生々しい貴重な記録と震災予防への提案 |
| 大
阪は何を学ぶに適するか |
大阪は商業と工業を学ぶに適する |
| 物
理学を学ぶ青年諸子に告ぐ |
物理の重要性を実例を挙げて説く。 |
| 「空間概念の分析」 |
空間的世界は主観として理解されるべきではなくて、客観として理解されるべきである |
| 「範疇としての空間に就いて」 | 空間そのものは眼には見えないけれども、たしかに存在する。では空間は範疇(存在の基本的なありかた)であろうか。この問いに対する答えとして書かれた「空間論シリーズ」の一編 |
| 幾何学と空間」 | 空間を扱う数学の一分化である「幾何学」では、どのように「空間」を認識すべきかを論じる。 |
| 『技術の哲学』 |
「技術とイデオロギー」「技術とインテリゲンチャ」との関連という特異な視点からの技術論として注目にあたいする |
| 『現 代唯物論講話』 | 現代唯物論の扱う分野――物質論、認識論、科学論、文化論を詳細に論じ
た大部な書籍 |
| 自然科学者と生活意識 | 自然科学者の生活意識もまたその特権的な地位に規定されていて、けっし
て自由ではありえないことを論ずる |
| 『科学方法論』 | 『科学論』と対をなす論述。主としてリッケルトの科学論を批判しなが
ら、カントその他の観念論哲学者の科学方法論を批判する[ |
| 『科学論』 |
マルクス主義の立場から、過去の科学論を批判し、科学とはなにかを説く |
| 日本の頭脳調べ | 文化勲章受章者の批評の形をとりながら,日本の科学者の立場と,思想を
批評する |
| 最
近日本の科学論 |
田辺元などの観念論的科学論の隆盛に対して唯物論的科学論をとく |
| 物
理的空間の成立まで |
戸坂の初期論文。カントの空間論を批判的に検討している。 |
| 物
理的空間の実現 |
戸坂の初期論文。「物理的空間の成立まで」の続編。アインシュタインの 相対論との関係で物理空間を論じる。 |
| 科
学的精神とは何か |
日本的精神主義に対抗して、真の科学的精神を説く。 |
| 科
学と科学の観念 |
科学は物質的生産の一つの型であり,認識はその産物である。 |
| 技
術と科学との概念 |
技術は物の生産の力の水準である。 |
| 再
び科学的精神とは何か |
最近日本の科学論続編 |
| 現
代科学教育論 |
科学教育の目的は科学的精神の教育である。 |
| 技
術的精神とは何か |
技術は単なる「労働手段の体系」ではないと説く。 |
| ひ
と吾を公式主義者と呼ぶ |
「科学的精神について」の一篇。悪しき意味の「公式主義」に対する頂門 の一針 |
| 科
学の大衆性 |
科学の大衆性は、科学の階級性の一つの実質である。 |
| 科
学の歴史的社会的制約 |
科学の階級性には4つの階梯があると説く。「イデオロギーの論理学」所 収の一篇 |
| 生
産を目標とする科学 |
科学は認識を目標とするのでなく,生産を目標とする。 |
| 技術へ行く問題 | キュリー夫妻のラジウム精製法の特許をめぐる話から科学の目標はどうし ても物の生産に行くことを論じる。 |
| 『科学と文学』 |
科学と文学について論じた小品(新字・新かな、註付)内容:緒言/言葉としての文学と科学/実験としての文学と科学/記録としての文学と科学/芸術としての文学と科学/文学とと科学の国境/随筆と科学/広義の「学」としての文学と科学/通俗科学と文学/ジャーナリスムと科学/文章と科学/結語 |
| 物理
学序説〔改訂版〕 |
物理学の哲学的考察を目指しながら、惜しくも 未完に終わった論考。附録として「自然現象の予報」をつけた |
| ア
インシュタイン |
アインシュタインの簡明な伝記 |
| ア
インシュタインの教育観〔改訂版〕 |
モスコフスキー『アインシュタイン』中のアインシュタインの教育観を紹
介する |
| ラ
ジオ雑感〔改訂版〕 |
ラジオにまつわるあれこれ。物理学者がラジオを修理しない理由がおも しろい。 |
| 方
則について〔改訂版〕 |
自然科学の法則とは如何なるものかを 論じ、厳密な法則は存在しないと説く。 |
| 時
の観念とエントロピー並びにプロバビリティc |
時間の概念はエントロピーの概念によって明確になった。 |
| 連句雑俎〔改訂版〕 |
物理学者の連句論。音楽との対比,フロイトの精神分析学との関連など、 ユニークな論考 |
| 相
対性原理側面観 |
アインシュタインの相対論発表からほどなく書かれた寺田の相対論観 |
| 太
陽面の変動と地球上の天気〔改訂版〕 |
太陽黒点の変動と天気との関係に関する論文の紹介 |
| 安
藤昌益〔改訂版〕 |
安藤昌益を世にだした狩野亨吉の記念碑的小論 |
| 志筑忠雄の星気説〔改訂版〕 |
『歴 象新書』の著者志筑忠雄の宇宙論が、西洋の影響ではなく、独自のものであることをはじめて論じ、志筑 の名を知らしめた名論文。 |
| 記憶すべき関流の数学家〔改訂版〕 |
関孝和の弟子のうち、主に、中根元圭と本多利明について論じた佳作。 |
| 天津教古文書の批判〔改訂版〕 | 今なお一部で信じられている竹内文書 (天津教)の「神代文字」と称するものが、明治以降の偽作であ ることを科学的に論証した画期的な論文。 |
| ラ プラスの伝 | 『48人の天文家』所収。偉大な数学者であり,天文学者でもあるラプラ スの小伝 |
| ア ダムスの伝 | 『48人の天文家』所収。ルベリエと独立に海王星の存在を預言したアダ ムスの小伝 |
| ガ レの伝 | 『48人の天文家』所収。ルベリエによる海王星の位置予報によって海王 星を発見したガレの小伝 |
| ル ベリエの伝 | 『48人の天文家』所収。ガレによって発見された天王星の存在を理論的 に預言した,ルベリエの小伝 |
| 偉 大なアマチュア・オルバース | 『48人の天文家』所収。ガウスとベッセルを育て、軌道計算法に名を残 すオルバースの小伝 |
| カ ロリーネ・ハーシェル | 『48人の天文家』所収。W.ハーシェルの妹・助手・女性天文学者であ るカロリーネ・ハーシェルの小伝 |
| 大 空の壁を突破したW・ハーシェル | 『48人の天文家』所収。大望遠鏡を製作し土星の衛星を発見し、宇宙の 構造をはじめてあきらかにしたハーシェル小伝 |
| ア ルゲランダーの伝 | 『48人の天文家』所収。ボン掃天星表で有名なアルゲランダーの小伝 |
| 天 文学上のフラウンホーファー | 『48人の天文家』所収。光学機器製作者にして分光学の先駆者フラウン ホーファーの伝記 |
| コ ペルニクの小伝 | 『48人の天文家』所収。太陽中心説の提唱者コペルニクスの小伝 |
| フ ラムスチード小伝 | 『48人の天文家』所収。初代グリニッジ天文台長にして『天球図譜』の 作成者フラムスチードの小伝 |
| バー ナード | 『48人の天文家』所収。天体写真術の開拓者。観測天文学の巨匠バー ナードの小伝 |
| バー ナード先生のこと | 『48人の天文家』所収。ヤーキス天文台でのバーナードとの短い邂逅を 記す |
| シュ ワルツシルドと日本の天文学統 | 『48人の天文家』所収。天体物理学者シュワルツシルドと京都大学天文
学との関係を論じる |
| 新 城新蔵博士 | 『48人の天文家』所収。伊能の天文学者新城新蔵小伝 |
| 中 村要君の死 | 『48人の天文家』所収。卓越した望遠鏡製作者にして優れた観測者でも
あり夭逝した中村要への愛情あふれる惜別の辞 |
| 平 山清次博士 | 『48 人の天文家』所収。平山清次と山本一清との確執もかかれた小伝 |
| 黒 点観測家三沢勝衛 | 『48人の天文家』所収。黒点観測の先駆者三沢勝衛の観測中止のやむな きに至った事情を示す手紙を中心に記述 |
| Z 項の木村栄博士 | 『48人の天文家』所収。Z項の発見者木村栄の小伝 |
| 『科学者と詩人』 |
下記の「科学者と詩人」収録の作品を1冊にまとめたものです。 |
| 『科 学の価値』 | 田邊元訳。科学的事実を知ることが科学の価値をしること |
| 『科学者と詩人』訳者序 | 『科学者と詩人』訳者平林初之輔の訳者序文 |
| 『科学者と詩人』序論 | 『科学者と詩人』巻頭に置かれた序論 |
| プリュウドム | 『科学者と詩人』所収。詩人プリュウドムのやや長い追悼文 |
| 砲工学校校友 | 『科学者と詩人』所収。エコール・ポリテクニク(砲工学校)校友大会で
のあいさつ |
| ベルトラン | 『科学者と詩人』所収。ベルトランの金婚式の際のあいさつ |
| チスラン | 『科学者と詩人』所収。彗星・小惑星の同定に使われるチスランの判定式
で有名なチスランの追悼文 |
| アルファン | 『科学者と詩人』所収。軍人・数学者であったアルファンの業績の紹介 |
| コルニュ | 『科学者と詩人』所収。コルニュの螺旋で有名なコルニュの業績の紹介 |
| ラゲエル | 『科学者と詩人』所収。ラゲールの業績を紹介 |
| ベルトロオ | 『科学者と詩人』所収。化学者ベルトローの業績の紹介 |
| フェ イ | 『科学者と詩人』所収。文部大臣、経度局長を歴任した天文学者フェイの 事績 |
| ケルヴィン卿 | 『科学者と詩人』所収。ケルビン卿ことウィリアム・トムソンの物理学上 の広汎な活躍の紹介 |
| ワイヤストラス | 『科学者と詩人』所収。ワイエルショトラスの人物像と業績 |
| キュリイ 及びブルアルデル | 『科学者と詩人』所収。ピエール・キュリーその他1906年に物故した
人達の追悼 |
| エル ミート | 『科学者と詩人』所収。数学者エルミートの生誕70年記念のあいさつ |
| 伊丹万作 | 「戦争責任の問題」 | 戦後「だまされた」と発言している事に対して「だまされた」ということで、自己の戦争責任を帳消しにしようとする人に対して、そうではなくて、「だまされた」本人の責任でもあることを論じた | |
| 本居宣長 | 「国号考」 | 魏志「倭人伝」にかかれた、「倭」が「大和」をへて「日本」になった過程を豊富な史料によって論証する。 |
|
| 葛洪 | 『抱朴子内篇』 | 仙人や不老不死を説いた著名な道教の教典の飜訳 |
|
| 穂積陳重 | 『復讐と法律』 | 個人的復讐がいかにして禁止され、法体系に組み込まれたかの歴史 |
|
| 高群逸枝 | 『女性の歴史・続』 | 明治からの労働婦人の歩みを概括し、第二次大戦後の日本の歩みの中での女性解放運動を取り扱い、最後に新しい世界を展望する最終巻 |
|
| 高群逸枝 |
『女性の歴史・下』 | 開国・明治維新から、アジア・太平洋戦争の敗戦を経て新憲法による男女同権が実現したまでを扱う |
|
| 高群逸枝 |
『女性の歴史・中』 | 室町時代から江戸時代まで。女性を「性の牢獄」に閉じ込めた社会のからくりを根源にまでさかのぼって解明する |
|
| 高群逸枝 | 『女性の歴史・上』 | 原始時代から昭和まで、女性の社会における状態を記した、全4巻にわたる膨大な女性史の第一冊にあたる、「上巻」 |
|
| 三枝博音 | 『日本の唯物論者』 | 貝原益軒・荻生徂徠・富永仲基・三浦梅園・皆川淇園・鎌田柳泓・山方蟠桃・安藤昌益・福沢諭吉・森有礼・中江兆民・幸徳秋水・井上哲次郎・井上円了・河上肇・戸坂潤:付録「唯物論史」 |
|
| 高群逸枝 | 『日本婚姻史』 | 著者畢生の大著『招壻婚の研究』を仕上げた著者が、日本の婚姻の歴史についてコンパクトにまとめた著書。 |
|
| 久米邦武 |
「太平記は史学に益なし」 | 楠正成のイメージを作り上げるのに大いに貢献した「太平記」は、史実に基づかない「歴史物語」にすぎないと論破した論考。 |
|
| ディーツゲン | 『哲学の成果』 | 『一労働者の観たる人間頭脳の働きの本質』に継ぐ、ディーツゲンの著書。 |
|
| 穂積陳重 | 「法の起原に関する私力公権化の作用」 | 法律が不備な時代に大いに称揚された復讐が、刑法が整備されるにつれて、禁止されるにいたる経緯を説明。「刑法進化の話」とほぼ同じ。(『復讐と法律』所収) | |
| 新井白石 | 『讀史餘論』 | 新井白石が当時の将軍・徳川家宣のために、古代から豊臣秀吉にいたる日本の歴史を独特の史観により講義したものの草稿。「大日本史」や「本朝通鑑」とは違う新しい史観を述べる。 |
|
| 穂積陳重 | 「刑法進化の話」 | 古代の復讐が、次第に刑法に進化するという、法律進化の観点から、刑法の成立を論じる。(『復讐と法律』所収) |
|
| 三浦梅園 |
「帰山録」 |
三枝博音校註による『日本哲学全書』第8巻「天文・物理学家の自然観」を定本とし、『梅園全集』を参照した。武蔵・小次郎の巌流島の決闘に始末は興味深い。 |
|
| 沖野岩三郎 | 『迷信の話』 | 年中行事から新興宗教、暦にまつわる迷信、八百屋お七の話から、犬公方綱吉の「生類憐れみの令」まで、およそ迷信に類することを資料を博捜して解説 |
|
| 那珂通世 | 「上世年紀考」 | 『古事記』「日本書紀』記載の神武天皇から応神天皇までの寿命が異常に長いことは、江戸時代から問題にされてきた。その問題に対する一つの解答。 |
|
| 小泉三申 | 「新版 由比正雪」 | 歌舞伎や講談でおなじみの由比正雪・丸橋忠彌らによる未遂に終わった「慶安事変」とは何であったかを解き明かす。 |
|
| 三枝博音 |
『技術の哲学』 | 東西の哲学者・技術史家の諸説を幅広く渉猟して、技術とは何かを解説する。日本の代表的な技術論として相川春喜とともに、武谷三男を論じている。、 |
|
| 三木 清 |
『構想力の論理』 |
「形の論理」の考究の立場から、「神話」「制度」「技術」「経験」を論じた。とくに「技術」は『技術哲学』と併せ読まれることがのぞましい。 |
|
| 三木 清 |
『技術哲学』 | 「技術=労働手段の体系」説を批判し、自然科学的技術のみならず「社会科学的技術」の存在を主張する | |
| 九鬼周造 | 『偶然性の問題』 | 「いきの構造」で著名な、独創的な哲学者・九鬼周造の哲学の中核をなす「偶然性」について論じた主論文 |
|
| 内藤虎次郎 | 「卑弥呼考」 | 邪馬台国大和説の基本文献(旧字・旧かな) |
|
| 白鳥庫吉 | 「倭女王卑彌呼考」 | 邪馬台国九州説の基本文献(旧字・旧かな) | |
| 三上参次 | 「歴史より観たる自殺特に情死」 | いわゆる男女の心中である「情死」が江戸時代に急増したのは、近松門左衛門が浄瑠璃で積極的に取り上げたことによることを論証する歴史論 |
|
| 高群逸枝 |
『恋愛論』 | 古今東西の文獻を渉猟して、恋愛感の変遷を歴史的に考証した、女性史研
究家高群逸枝の異色の一冊 |
|
| 服部之総 |
『歴史記述の理論』 | 明治維新史研究で有名な服部之總による「歴史を記述するとはいかなるこ とか」について諸説を批判的に検討した小著。唯物論全書『歴史論』の第一編をなす。 | |
| 井上円了 | 『迷 信解』 | 哲学者にして迷信や妖怪を否定する立場からの科学的研究を志した、哲学 者にして「妖怪博士」と呼ばれた井上円了による、やさしい迷信の話 | |
| 高群逸枝 |
古事記――妻問時代の女性生活 | 『古事記』『日本書紀』『
風土記』などの史料を元に、古代における婚姻形態を解明したもの |
|
| 高群逸枝 |
児童と道徳 | 道徳教育の欺瞞性を鋭く突いた評論。現代にも通用するものであろう |
|
| 高群逸枝 |
女 性史研究の立場から | 女性史研究に一生をささげた高群逸枝が、自己の研究の立場をかたる |
|
| 三枝博音 | 多賀墨郷君にこたふる書」(三枝博音による現代語への書き直し) | 「多 賀墨郷君にこたふる書」の三枝博音による現代語への書き直し | |
| 「唯物論研究會」創立前後の書簡 三通 附 :唯物論研究會創立記念講演會プログラム |
1932(昭和7)年に、三木清、三枝博音、戸坂潤などの哲学者、歴史
学者・服部之総、科学者の小泉丹、岡邦雄、ジャーナリスト・長谷川如是閑などのそうそうたる 人たちが、日本に迫りくる軍国主義に対抗して、マルクス主義の立場から、広く科学的な思考を考究し、普及を目指した研究会の創立前後の一個人にあてた手 紙。 |
||
| 三枝博音 |
三浦梅園の哲学 | 三浦梅園の哲学を、東西の哲学者の言説と対比して、日本独自の弁証法哲 学であることを解明した力作。 | |
| 三枝博音 |
梅 園の論理思想 | 三浦梅園の論理学が弁証法であることを論述 |
|
| 三枝博音 |
梅 園の哲学 | 三浦梅園の哲学をやや詳しく解説 |
|
| 三枝博音 |
梅 園の言う真実の学問 | 三浦梅園の学問論のやさしい解説 |
|
| 三枝博音 |
梅園哲学についての対話 | 三浦梅園への入門 |
|
| 愛知敬一 | ファラデーの伝 |
『ろうそくの科学』で有名なマイケル・ファラデーの伝記 |
|
| 三浦梅園 |
多 賀墨郷君にこたふる書 | 三浦梅園が門弟多賀墨郷にこたえるかたちで、梅園思想の真髄を解説した 短編の原文。 | |
| 三枝博音 |
日 本人の自然解釈 | 日本人の自然哲学理解の進展と三浦梅園について |
|
| 三枝博音 | 三 浦梅園の自然哲学 | 三浦梅園の自然哲学者としての側面を論じる |
|
| 三枝博音 |
日 本の科学を育てた人としての梅園 | 三浦梅園の研究者でもあった三枝博音が科学者としての三浦梅園を論じる |
|
| 林 鶴一 |
初等幾何学の体裁 | ユークリッド幾何学の公理系および非ユークリッド幾何学についての解
説。教員向けの講義録 |
|
| 九鬼周造 |
偶然化の論理〔改訂版〕 |
「偶然」になるための論理を論ずる。 |
|
| 九鬼周造 |
偶然性(講演)〔改訂版〕 |
「いきの構造」の九鬼周造はまた、「偶然性」の哲学者でもあった。 | |
| 久米邦武 |
神道は祭天の古俗〔改訂版〕 |
|
|
| ディーツゲン著 山川 均訳 |
一労働者の観たる人間頭脳の働らきの性質 〔改訂版〕 |
マルクス・エンゲルス、レーニンが称賛した、一皮革工ディーツゲンの哲
学論文。 |