 丂偲偙傠偱丄峕屗枛婜偵栱晉挰側偳偱帞堢丒斏怋偝傟偰偄偨暥捁偼丄尨庬乮暲暥捁乯偲梕巔偼偁傑傝曄傢傜側偐偭偨偼偢偱偁傞丅
丂偲偙傠偱丄峕屗枛婜偵栱晉挰側偳偱帞堢丒斏怋偝傟偰偄偨暥捁偼丄尨庬乮暲暥捁乯偲梕巔偼偁傑傝曄傢傜側偐偭偨偼偢偱偁傞丅仚敀暥捁偺弌尰乲恑壔偐曄堎偐乴
 丂偲偙傠偱丄峕屗枛婜偵栱晉挰側偳偱帞堢丒斏怋偝傟偰偄偨暥捁偼丄尨庬乮暲暥捁乯偲梕巔偼偁傑傝曄傢傜側偐偭偨偼偢偱偁傞丅
丂偲偙傠偱丄峕屗枛婜偵栱晉挰側偳偱帞堢丒斏怋偝傟偰偄偨暥捁偼丄尨庬乮暲暥捁乯偲梕巔偼偁傑傝曄傢傜側偐偭偨偼偢偱偁傞丅
丂偙傟偐傜偄偐偵偟偰敀傗嶗偑抋惗偟偨偺偐丄幚偼偙傟傑偨彅愢偁傝敊慠偲偟偰偄傞丅
丂偲傝偁偊偢敀暥捁偺敪惗抧偼栱晉挰偱偁傞偲偄偆揰偱偼丄堎榑偼彮側偄丅栤戣偼丄帞堢偝傟偰偄偨暲暥捁偑彊乆偵敀壔偟偰偄偒敀暥捁偑弌棃偨丄偮傑傝丄暲偐傜嶗丄嶗偐傜敀偵恑壔偟偨偲偡傞峫偊乮恑壔愢乯偲丄偼偠傔偵弮敀偺撍慠曄堎屄懱偑弌尰偟丄偦偺屻丄敀偲暲偺崿寣偵傛偭偰嶗偑抋惗偡傞偲偄偆偺峫偊乮曄堎愢乯偺丄憡斀偡傞傛偆側擇愢偺懚嵼偱偁傞丅
丂堦尒偡傞偲丄慺杙側恑壔愢偺傎偆偑擺摼偟傗偡偄偐傕偟傟側偄偑丄尰嵼偱偼丄惗暔偺恑壔偼撍慠媫寖偵恑峴偡傞傎偆偑傓偟傠晛捠偲偝傟偰偄傞丅椺偊偽僉儕儞偺庱側偳偼彊乆偵挿偔側傞偲偄偆恑壔偑偁偭偨偲偝傟偰偄偨偑丄幚嵺偵偼丄僉儕儞偺慶愭偱庱偑傑傞偱挿偔側偄摦暔偺壔愇偲丄僉儕儞媺偺挿偝偵側偭偨摦暔偺壔愇偟偐敪尒偝傟偢丄恑壔搑忋偺庱偺挿偝偺摦暔偺懚嵼偼棤晅偗傞偙偲偑弌棃側偄偲偄偭偨晄巚媍側尰徾偼丄寢峔偁傝傆傟偨傕偺傜偟偄乮撈傝尵乧妘棧偝傟偨彮悢僌儖乕僾撪偱偺恑壔偲偄偆僌乕儖僪偺愢柧偺曽偑丄僂僀儖僗姶愼側偳傪帩偪弌偡傛傝傢偐傝傗偡偄偲屄恖揑偵偼巚偭偰偄傞偑丄偙偙偱恑壔榑偵偮偄偰棫偪擖傞傂傑偼側偄偺偩偭偨乯丅暥捁偵偮偄偰傕丄偙偺愢柧偵偍偗傞拞娫庬偱偁傞偼偢偺嶗暥捁偺弌尰偑丄敀暥捁偵愭棫偮徹嫆偑側偄偺偱偁傞丅
仸丂峕屗拞屻婜偵昤偐傟傞暥捁偼丄偡傋偰尨庬偺巔傪偟偰偍傝丄1847擭姧峴偺亀昐昳峫亁傕摢偲旜偑崟偔丄杍偑敀丄懱偼奃怓偱偁傞偺偑晛捠偲愢柧偟偰偄傞丅偨偩亀昐昳峫亁偵偼丄乽懘懠庬庬怓曄儕傾儗僪儌媝僥娤徿僫儔僘乿偲傕偁傝丄偙偺怓曄傢傝偼丄敀怓曄壔傪堄枴偡傞壜擻惈傕偁傞丅偟偐偟枹尒偺偆傢偝榖偱偁傝丄怓曄傢傝偼杍崟傗屻弎偡傞傛偆偵丄敀暥捁抋惗偲偼娭學側偄儊儔僯儞怓慺宍惉晄慡偵傛傞拑壔丄敀壔偱偁偭偨偲傕峫偊傜傟傞丅
丂偝傜偵暥壔恖椶妛揑側尒抧偱尵偊偽乮偦傫側妛栤傪巹偼曌嫮偟偨偙偲偼側偄偑乯丄懱偺偛偔堦晹偑敀壔偟偨暥捁傪尒偨晛捠偺擔杮偺擾柉偑丄偦傟傪戙廳偹偱奼戝偝偣偰偄偗偽弮敀偵側傞側偳偲憐憸偱偒傞偲偼丄偲偰傕怣偠傜傟側偄偺偱偁傞丅偦傟偼杚抺偑堦斒揑側惣梞偺嬤戙揑側昳庬夵椙偺巚峫偑側偄尷傝丄擄偟偄榖偱偁傠偆丅傎偲傫偳擾峩柉懓偱丄擏怘偺廗姷傕嬌傔偰尷掕偝傟偰偄偨擔杮偵偼丄昳庬夵椙偺楌巎偑奆柍偵嬤偄偙偲傪朰傟偰偼側傜側偄丅
仸丂椻寣摦暔偱偁傞嬥嫑傪暿偵偡傟偽丄峕屗帪戙偵昳庬夵椙偝傟偨傕偺偲偟偰丄捤杮妛偝傫偼亀峕屗帪戙恖偲摦暔亁偺拞偱僴僣僇僱僘儈傪偁偘傜傟偰偄傞丅偟偐偟偦偺崻嫆偱偁傞1787擭姧偺嶜巕亀捒娿憀堢憪亁偼怓偑傢傝偺條巕傪偁傞庯枴恖偑斏怋幚尡偟偨傕偺偱丄昳庬夵椙偲偼栚揑偑彮偟堘偆傛偆偩乮偮傑傝曄傢傝幰偺庯枴峴堊乯丅
丂側偍亀嬥嫑偲擔杮恖亁偵傛傞偲丄嬥嫑偵偟偰傕丄峕屗帪戙偵偼愊嬌揑側恖堊搼懣偵傛傞昳庬夵椙傪峴偭偰偄偨偲偼尒側偣側偄傜偟偄乮栱晉挰偼嬥嫑偺嶻抧偲偟偰桳柤乯丅
丂傑偨偙偺暥捁恑壔愢偵廬偊偽丄晹暘敀壔偟偨嶗暥捁揑屄懱偼丄暥專巎椏偵傕丄奊夋巎椏偵傕尒傜傟側偄傕偺偺丄慖戰斏怋弌棃傞傎偳偵偁傝傆傟偨懚嵼偱偁偭偨偼偢偩偐傜乮戝搰敧廳偝傫偑栱晉挰偵帩嶲偟偨偺偼丄偡偱偵嶗暥捁偱偁偭偨偲偡傞愢柧偝偊偁傞)丄枩堦昳庬夵椙偺抦幆偑晛媦偟偰偄傞側傜丄栱晉挰偵尷傜偢偳偙偺暥捁斏怋抧偱傕弮敀傪栚巜偟偰偄偰傕椙偄偼偢偱偁傞丅偝傜偵丄昐曕忳偭偰栱晉挰偑偼偠傔偰敀暥捁偺昳庬夵椙偵惉岟偟偨偺偩偲偟偰傕丄懠偺抧堟傕偡偖偵捛悘弌棃傞偼偢偱偼側偐傠偆偐丅偲偙傠偑丄尰幚偵敀暥捁敪徦抧偱暥捁惗嶻抧偲偟偰柤傪巆偟偨偺偼栱晉偩偗側偺偱偁傞丅
丂堦曽丄暥捁曄堎愢偵傛傞愢柧偵偼柍棟偑惗偠側偄丅偦傕偦傕弮敀屄懱偺曄堎偼捒偟偄傕偺偱偼偁偭偰傕婲偙傜側偄傕偺偱偼側偄丅敀偄僇儔僗側偳傕偨傑偵僯儏乕僗偵偁傜傢傟傞偔傜偄偩丅傗偼傝丄崀偭偰傢偄偨傛偆偵撍慠弮敀偺暥捁偑惗傑傟丄恖娫偼崢偑敳偗傞傎偳嬃偒丄壗偲偐偦偺婏愓揑側弮敀傪巆偦偆偲偄偆堦擮偱丄慺杙偵嬤恊岎攝側偳傪偔傝偐偊偟丄屌掕偝偣偰偄偭偨偺偑帠幚偵嬤偄偺偱偼側偐傠偆偐丅
仸丂偄偐側傞惗暔偵傕崟怓怓慺(儊儔僲僒僀僩丄儊儔僯儞乯傪寚偔屄懱丄敀巕乮albino)偼惗傑傟傞偑丄敀暥捁偺応崌偼丄栚偺怓偑敄偔側傜側偄偐傜丄偙偺敀巕徢(敀壔徢丄傾儖價僯僘儉乯偱偼側偄乮乽傾儖價僲乿偲偟偰攧傜傟傞偙偲傕偁傞栚偺愒偄敀暥捁偑敀巕徢偵傛傞昳庬乯丅傛偔傢偐傜側偄偑丄敀暥捁偺敀怓偼怓慺偑側偔側偭偨寢壥偺傕偺偱偼側偔丄敀偵側傞梫慺偑堚揱巕儗儀儖偱弌尰偟偨寢壥偲丄暥宯偱偁傞巹偼棟夝偟偰偟傑偆偙偲偵偡傞丅
仸丂捁偵偼晹暘揑敀壔尰徾偼傢傝偵昿斏偵婲偙傞偙偲偐傜丄愱栧揑偵側傟偽側傞傎偳柍斸敾偵恑壔愢傪庴偗擖傟偰偟傑偄偑偪偺傛偆偱偡偑丄崱偺偲偙傠擔杮偱暥捁偺昳庬夵椙偑峴傢傟偨徹嫆偼壗堦偮側偔丄媡偵偙偙偱帵偟偰偄傞忬嫷徹嫆偐傜偼丄幚偼撍慠曄堎偲峫偊傞埲忋偵擄偟偄榖偲峫偊偞傞傪偊側偄傢偗偱偡丅側偍丄偙偺審偵娭怱偺偁傞曽偼亀暥捁栤戣亁乽敀偺婲尮乿傕偛嶲徠壓偝偄丅
丂敀壔偺撍慠曄堎偑婲偒丄堦塇偺敀暥捁乮僔儘僽儞僠儑僂丒僴僋僽儞僠儑僂)偑弌尰偡傞丅偙傟偼傑偝偵婏愓偲偄偭偰傛偄偑丄偙偺曄堎庬偼偔偪偽偟側偳偺愒(偙傟偼寣怓)偑塮偊傞偨傔丄桪夒偱旤偟偔丄偲偐偔弮敀惔寜偺戝岲偒側擔杮恖偺怱傪傢偟偯偐傒偵偟丄昳庬偲偟偰屌掕偝傟丄暥捁偺恖婥傪戝偄偵崅傔傞偙偲偵側傝丄偙偺壜楓側怴庬偑慜戙枹暦偺廀梫偺奼戝傪彽偄偨丒丒丒丄偦偺傛偆偵峫偊傟偽丄暥捁惉嬥偑弌尰偟偨偲偄偭偨榖偑巆傞傎偳丄懠偵姤愨偟偰栱晉挰偺暥捁嶻嬈偑怳嫽偟偨棟桼傕棟夝偱偒傞偺偱偁傞丅
丂偮傑傝杮摉偼敧廳偝傫偵巒傑傞栱晉挰埲奜偵傕丄暥捁偺恖岺斏怋傪峴偭偰偄偨抧堟偼偁偭偨偑丄堦塇偺敀暥捁偑嬼慠偵傕栱晉挰偵抋惗偟偨帠偱丄摉弶敀暥捁偺斏怋傪撈愯偱偒偨栱晉挰偼丄懠傪埑搢偟偰暥捁惗嶻抧偲側偭偨偲尒側偣傛偆丅
仸丂柧帯婜偺暥崑丄愮墌嶥偺壞栚燍愇偺亀暥捁亁偲偄偆悘昅偺拞偵弌偰偔傞暥捁偼廃抦偺傛偆偵敀暥捁偱偁偭偨丅傑偨戝惓弶擭偺崰偵偼丄偦偺燍愇偵掜巕偺撪揷昐偑庤忔傝暥捁傪尒偣偰帺枬偟偰偄傞乮乽燍愇嶳朳偺栭偺暥捁乿)偑丄偙偺乽暥捁乿傕乽傑偩奃怓傪偟偨彫偝側暥捁偺悧苽爞閭虃艁A攚拞偵桳怓塇栄傪巆偡敀暥捁偺傛偆偱偁傞丅
丂燍愇傕昐傕摿偵敀暥捁偱偁傞偲偄偆拲婰傪偣偢乽暥捁乿偱嵪傑偟偰偍傝丄柧帯戝惓婜偵乽暥捁乿偲尵偊偽敀暥捁傪巜偡偔傜偄偵丄敀暥捁偺廀梫偑埑搢揑偩偭偨條巕偑偆偐偑偊傞丅
丂偦傟偱偼丄敀暥捁偺屄懱偑栱晉挰偵弌尰偟偨帪婜偼偄偮偱偁傠偆偐丅幚偼偙傟傕椙偔傢偐傜側偄丅偨偩燍愇偺亀暥捁亁偑彂偐傟傞柧帯41擭乮1908乯偵愭棫偮偙偲20擭埲忋丄柧帯18擭乮1885乯偺亀搶嫗墶昹枅擔亁偵丄捁壆偺榖偲偟偰墷暷傊偺彫捁桝弌偺婰帠偑嵹偭偰偄傞乮亀柧帯僯儏乕僗帠揟亁戞嶰姫乯偺偼嶲峫偵側傝偦偆偩丅
丂乽僽儞僠儑僂偼敀柍抧埥偄偼憀柍抧乮偹偢傓偠乯偺偛偲偒姺傝暔傪媂偟偲偡丅乿
丂憀柍抧乮亖奃怓堦怓?乯偼壗傪巜偟偰偄傞偺偐傢偐傜側偄偑乮乽敀柍抧乿偵懳偡傞堦庬偺岅楥偁傢偣偺廋忺偺傛偆側婥偑偡傞乯丄敀柍抧偼敀暥捁偺偙偲偵堘偄側偄偐傜丄偙偺帪偵偼偡偱偵懚嵼偟丄桝弌昳偵傑偱側偭偰偄偨偙偲偑偆偐偑偊傞丅偦偟偰丄偙偙偵偼乽姺傢傝暔乿偲偁傞偐傜丄曄傝庬偲偟偰傑偩堦斒壔偟偰偄側偐偭偨偲傕巚傢傟丄偦傟傎偳敀暥捁偺弌尰婜傪偝偐偺傏傞昁梫偼側偄偲尒側偣傞偐傕偟傟側偄丅
丂偙偙偱偼丄偲傝偁偊偢柧帯10擭戙偺弶傔偁偨傝偲悇掕偟偰偍偒偨偄丅
乲晅婰2005丒4乴栱晉偵偍偗傞揱彸偵埶嫆偟偨傕偺偐丄乽尦帯尦擭旜挘斔偺晲壠壆晘偵彈拞曭岞偟偰偄偨乽敧廳彈乿偲偄偆恖偑丄栱晉挰偵壟擖傝偟偨帪丄擔崰帞堢偺悽榖傪偟偰偒偨暲暥捁傪搚嶻偱栣偭偰帩嶲偟偨偺偑栱晉挰偱偺暥捁帞堢偺巒傑傝丄偦偺屻丄暥捁帞堢偑擾壠偺暃嬈偲偟偰惙傫偵側傝丄峕屗帪戙枛婜偵偼撍慠曄堎偵傛傝乽敀暥捁乿偑抋惗偟丄偙傟傪嬯怱帞堢偺枛夵椙傪廳偹偰丄尰嵼偺傛偆側敀暥捁偲側偭偨乿側偳偲愢柧偡傞傕偺傪尒偐偗傞偑丄偙傟偼偮偠偮傑偑崌傢側偄丅
丂側偤側傜丄1868擭偐傜柧帯帪戙側偺偱丄敧廳偝傫偑壟擖傝偟偰俁擭庛偱丄乽峕屗帪戙枛婜乿偼廔傢偭偰偟傑偆偺偩丅
仚嶗暥捁偺埵抲偯偗
丂偝偰丄撍慠曄堎偱慡恎偑敀壔偟偨堦屄懱傪丄昳庬偲偟偰妋棫偡傞偨傔偵偼丄偐側傝柍棟側嬤恊岎攝傕峴傢偹偽側傜側偐偭偨偼偢偩偑丄偦偺傛偆側偙偲傪懕偗傞偲丄懱幙偑庛偔側偭偨傝丄婏宍偑惗偠偨傝丄斏怋擻椡偑棊偪偨傝丄偝傑偞傑側埆塭嬁偺婋尟偑崅傑偭偰偟傑偆丅
丂偦偺偨傔丄帪乆丄敀暥捁偵暲暥捁傪岎攝偡傞昁梫偑惗偠偰偒偨帠偼憐憸偵偐偨偔側偄丅偙偺丄偄傢偽敀暥捁偺懱幙楎壔傪杊偖偨傔偺崿寣偺寢壥弌棃偨偺偑丄嶗暥捁乮僒僋儔僽儞僠儑僂)偲偄偆帠偵側傞偺偱偼側偐傠偆偐丅戞堦丄嵟弶偺撍慠曄堎懱偺岎攝憡庤偼丄暲暥捁埲奜偵偼偄側偄偺偩偐傜丄偦偺娫偵偼嶗揑側屄懱傕昁慠揑偵嶻傑傟偞傞傪摼側偐偭偨偼偢偱偁傞丅
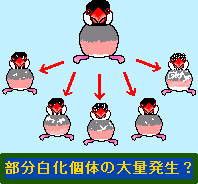 丂嶗暥捁偺婲尮偵偮偄偰偼敀傪憂傝弌偡夁掱偱弌棃偨偲偐丄敀偑愭慶偺怓偵栠傠偆偲偡傞尰徾偵傛偭偰抋惗偟偨偲偄偆愢柧傕偁傞丅偟偐偟丄偙傟傜偺愢傪庡挘偡傞恖偨偪偼丄暥捁偑儁僢僩摦暔偱丄恖娫偵傛偭偰岎攝憡庤偑慖偽傟傞帠傪朰傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅側偤昳庬夵椙偺亀夁掱亁偵偁傞拞搑敿抂側傕偺傪丄弮敀傪栚巜偟偰偄偨偲偄偆昳庬夵椙偺揤嵥偱偁傞朸巵乮幚嵼偟偨偲偼巚偊側偄偑乯偑昳庬偲偟偰屌掕偟側偗傟偽側傜側偄偺偐丅
丂嶗暥捁偺婲尮偵偮偄偰偼敀傪憂傝弌偡夁掱偱弌棃偨偲偐丄敀偑愭慶偺怓偵栠傠偆偲偡傞尰徾偵傛偭偰抋惗偟偨偲偄偆愢柧傕偁傞丅偟偐偟丄偙傟傜偺愢傪庡挘偡傞恖偨偪偼丄暥捁偑儁僢僩摦暔偱丄恖娫偵傛偭偰岎攝憡庤偑慖偽傟傞帠傪朰傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅側偤昳庬夵椙偺亀夁掱亁偵偁傞拞搑敿抂側傕偺傪丄弮敀傪栚巜偟偰偄偨偲偄偆昳庬夵椙偺揤嵥偱偁傞朸巵乮幚嵼偟偨偲偼巚偊側偄偑乯偑昳庬偲偟偰屌掕偟側偗傟偽側傜側偄偺偐丅
丂傑偨丄側偤愭慶偑偊傝偟偮偮偁傞暥捁丄弮敀傪椙偟偲偡傟偽乽墭傟偰偒偰偄傞乿偦偺屄懱傪丄帞堢幰偼傢偞傢偞斏怋偵梡偄偰丄弮敀偱側偔側偭偰偄偔偺傪懀恑偟側偗傟偽偄偗側偄偺偐丅偦傟偵丄偳偆偟偰偦偺愭慶偑偊傝偲偄偆偺偑丄嫻偺傏偐偟柾條傪巆偟偨抜奒偱巭傑偭偰偟傑偆偺偱偁傠偆丅
丂埲忋偺彅揰偵丄崌棟揑側愢柧偑弌棃傞偱偁傠偆偐丅寢嬊丄偙傟傜偺愢柧偼偢偄傇傫柕弬傪娷傫偱偄傞傕偺偱偁傝丄幚徹揑側榖偑壗傕側偄晜愢偲抐偠偞傞傪摼側偄丅
仸丂彮側偔偲傕丄晹暘敀壔偟偨屄懱摨巑偺恖堊搼懣偺枛偵敀暥捁偑憂傜傟偨偲偡傞側傜丄暲暥捁偑昿斏偵晹暘敀壔傪婲偙偡偙偲偔傜偄偼丄幚徹偟側偗傟偽側傜側偄丅尨庬傪曔傑偊偰戙廳偹偟偰娤嶡偡傟偽椙偄偺偩偐傜丄尋媶娐嫬偝偊惍偭偰偄傟偽娙扨側偼偢偱偁傞丅
丂傗偼傝嶗暥捁偼丄敀暥捁傪宲懕偝偣傞乮偄傢備傞懱幙楎壔偺杊巭慬抲乯偨傔偺昁梫埆偲偟偰惗偠偨傕偺偲峫偊傞埲奜偵側偄偱偁傠偆丅斏怋偲偄偆揰偺傒偱昡壙偡傟偽丄摉弶偺嶗偺懚嵼偼敀傪曗姰偡傞傕偺偲偟偰偺傒堄枴傪帩偭偰偄偨傢偗偱偁傞丅
丂偟偐偟丄敀傪堐帩偡傞偨傔偺昁梫埆偵夁偓側偄偦偺嶨庬偺嫻偺敀偄柾條偵嶗偺壴傃傜傪憐偄丄偦偺旤揰傪尒弌偟丄嬋偑傝側傝偵傕昳庬偲屇傫偱偟傑偆偺偩偐傜丄戝偟偨傕偺偱偁傞丅杮棃嶨庬偩偐傜丄嶗偺攝怓偼屌掕偣偢丄嫻偺傏偐偟傕傢偢偐側傕偺傕偄傟偽丄層杻墫摢偺傕偺傕偍傝丄尰嵼偱傕昳庬偲偄偊傞偺偐夦偟偄偲偡傞尒曽偡傜偁傞偑乮巹偼昳庬娫岎嶨偑側偗傟偽丄儊儞僨儖偺堚揱朄懃偺忋偱傕丄偁傞掱搙堦掕偟偨攝怓偵側傞偲峫偊偰偄傞乯偦偺偁偄傑偄偝傕擔杮揑偱丄嶗偺枺椡偲偄偊傞偐傕偟傟側偄乮
仸丂傕偭偲傕丄柧帯婜偵惗傑傟偨栱晉挰偺敀暥捁宯摑偼愨柵偟丄戝惓婜偵傑偨尰傟偨偺偑崱偺敀暥捁偺捈愙偺愭慶偲偡傞愢傕偁傞丅偦偺傛偆偵搒崌椙偔摨偠撍慠曄堎偑婲偙傞偲偼巚偊側偄偺偱丄偙偺榖帺懱偼怣偠偑偨偄偑丄壗傜偐偺尨場偱堦帪婜柧帯婜偺敀暥捁偺捈宯偼慡柵偟偨傕偺偺丄巆偝傟偨嶗暥捁乮暲偲敀偺崿寣乯偺敀偑懡偄傕偺傪慖戰偟偮偮戙傪廳偹傞帠偵傛傝丄戝惓婜偵敀暥捁傪暅尦偟偨偲偄偭偨帠懺偼戝偄偵偁傝偊偦偆偩乮傕偲傕偲柍偐偭偨弮敀傪憂弌偡傞偲偄偆敪憐偼擄偟偄偑丄懚嵼偟偨弮敀偵栠偡偲偄偆敪憐偼梕堈偱偁傠偆乯丅
丂傓偟傠偙偺傛偆偵峫偊傟偽丄敀暥捁偺抜奒惉棫愢傕丄戝惓婜偺暅尦偺夁掱傪愢柧偟偨傕偺偲偟偰惓偟偄偲偄偊傛偆丅乮亅曗懌2003擭亅嶗暥捁偲偄偆傛傝僑儅墫摢傪偟偨暥捁摨巑偐傜偼敀暥捁偑惗傑傟傞傕偺偲巚傢傟傞丅
丂埲忋丄柺搢偙偺忋側偄峫嶡傪懕偗偰偒偨偑丄敀傕嶗傕姰慡偵擔杮恖偺搘椡偲旤揑姶妎偵傛偭偰惗傒弌偝傟偨彫捁偱偁傞帠偩偗偼媈偄傛偆傕側偄帠幚偲尵偊傛偆丅