■
2015年 8月1日



 2番果はちょうど10㎝くらいです。
2番果はちょうど10㎝くらいです。
 3番果は9㎝くらい。
3番果は9㎝くらい。
 4番果は8.5㎝と後がどんどん続いています。
4番果は8.5㎝と後がどんどん続いています。


 こちらは葉が1枚もない悲惨な株です。
こちらは葉が1枚もない悲惨な株です。
 こちらの2株は元気な部類で、生長点からは若葉が出ています。
こちらの2株は元気な部類で、生長点からは若葉が出ています。
 こらがその若葉です。
こらがその若葉です。
サビダニの生命力とレジナの生命力のデスマッチです。


2015年 8月1日



ネットメロンの証しです!!
2号機で栽培中のアニバーサリーメロンはマスクメロンのような本格的なネットが 張るのが特徴です。
メロンのネットは自然にできるヒビ割れから果汁が染み出て固まったものです。 1番果の左半分にまずは横方向のヒビ割れが出来てきました。
大きさは10㎝を少し超えました。 今のところ至って順調に生長しています。 もっとハードルが高いのかと思っていましたがうれしい誤算です。
2号機で栽培中のアニバーサリーメロンはマスクメロンのような本格的なネットが 張るのが特徴です。
メロンのネットは自然にできるヒビ割れから果汁が染み出て固まったものです。 1番果の左半分にまずは横方向のヒビ割れが出来てきました。
大きさは10㎝を少し超えました。 今のところ至って順調に生長しています。 もっとハードルが高いのかと思っていましたがうれしい誤算です。
 2番果はちょうど10㎝くらいです。
2番果はちょうど10㎝くらいです。
 3番果は9㎝くらい。
3番果は9㎝くらい。
 4番果は8.5㎝と後がどんどん続いています。
4番果は8.5㎝と後がどんどん続いています。

アニバーサリーメロン6株の全景です。
各株2個づつの合計12個を着果させました。
親ヅルの生長点を摘心するとどんどん脇芽が出てきます。
この脇芽をこまめに欠いてやらないと一気にジャングルになってしまいます。
この脇芽カキのときに間違って着果させた子ヅルを切ってしまうと大ショックです。
実は、1度やってしまいました。切ってしまうと元には戻らないので 違う子ヅルにもう一度着果させて今に至っています。
親ヅルの生長点を摘心するとどんどん脇芽が出てきます。
この脇芽をこまめに欠いてやらないと一気にジャングルになってしまいます。
この脇芽カキのときに間違って着果させた子ヅルを切ってしまうと大ショックです。
実は、1度やってしまいました。切ってしまうと元には戻らないので 違う子ヅルにもう一度着果させて今に至っています。

一方、トマトサビダニにやられた3号機のその後です。
まだ完全に退治したわけではありませんが、枯れるスピードが相当遅くなりました。
緑の葉が残っている株では健康な若葉が出てきています。 そんな株が6株くらいはあります。
葉が1枚もない株でもミニトマトが色付いてきました。
若葉が出てくるのを待っているのですがなかなか出てきません。 コロマイトも効いたような効かないような結果で耐性が出来てしまったようです。
まだ完全に退治したわけではありませんが、枯れるスピードが相当遅くなりました。
緑の葉が残っている株では健康な若葉が出てきています。 そんな株が6株くらいはあります。
葉が1枚もない株でもミニトマトが色付いてきました。
若葉が出てくるのを待っているのですがなかなか出てきません。 コロマイトも効いたような効かないような結果で耐性が出来てしまったようです。
 こちらは葉が1枚もない悲惨な株です。
こちらは葉が1枚もない悲惨な株です。
 こちらの2株は元気な部類で、生長点からは若葉が出ています。
こちらの2株は元気な部類で、生長点からは若葉が出ています。
 こらがその若葉です。
こらがその若葉です。サビダニの生命力とレジナの生命力のデスマッチです。

サビダニに薬に対する耐性をつけさせないように4種類の殺虫剤を揃えました。
それも化学薬品ではなく自然成分のものを揃えました。
左から順番に、まずはお馴染み ヤシ油とデンプンで出来た「カダンセーフ」です。
次が天然物由来の「コロマイト」。
次が食品成分から出来た「ベニカマイルドスプレー」。 最後が温泉に含まれる硫黄を使った「イオウフロアブル」。
この4種類を2日おきに順番に散布して、 明後日「イオウフロアブル」を散布したら2巡します。
これでもダメなら最後は化学薬品です。
左から順番に、まずはお馴染み ヤシ油とデンプンで出来た「カダンセーフ」です。
次が天然物由来の「コロマイト」。
次が食品成分から出来た「ベニカマイルドスプレー」。 最後が温泉に含まれる硫黄を使った「イオウフロアブル」。
この4種類を2日おきに順番に散布して、 明後日「イオウフロアブル」を散布したら2巡します。
これでもダメなら最後は化学薬品です。

■
2015年 8月7日



 生長点からはどんどん若葉が出てきています。
生長点からはどんどん若葉が出てきています。
 根っこも白い健康な根が外側を取り囲んでいます。
根っこも白い健康な根が外側を取り囲んでいます。
 今後の害虫による被害を未然に防ぐためにニームオイルを散布しました。
今後の害虫による被害を未然に防ぐためにニームオイルを散布しました。
これもニームの木からとれる自然成分で害虫が寄り付かないそうです。
果たして救世主となれるでしょうか。

 1番果です。 だいぶネットが密になってきました。
1番果です。 だいぶネットが密になってきました。
 2番果です。 1番果を追い越して11.5cmあります。
2番果です。 1番果を追い越して11.5cmあります。
 3番果です。 撮影のたびに転がして位置を変えてやります。
3番果です。 撮影のたびに転がして位置を変えてやります。
 4番果です。 この玉は裏返すと割れ目が粗くなっています。
4番果です。 この玉は裏返すと割れ目が粗くなっています。
 5番果です。 この玉は裏返すと白くなっています。
5番果です。 この玉は裏返すと白くなっています。
 6番果です。 この玉も裏返すと白っぽくなっています。
6番果です。 この玉も裏返すと白っぽくなっています。
 7番果です。こちらは西洋ナシのような形をしています。
7番果です。こちらは西洋ナシのような形をしています。
 8番果。 こちらはきれいな球の形です。 ネットはまだ出ていません。
8番果。 こちらはきれいな球の形です。 ネットはまだ出ていません。
 9番果です。 玉子のような形です。
割り箸にはぷくぷくで跳ね上がる養液が染み込んでいます。
9番果です。 玉子のような形です。
割り箸にはぷくぷくで跳ね上がる養液が染み込んでいます。
 10番果です。 玉が小さいときには形がいびつになりやすいです。
10番果です。 玉が小さいときには形がいびつになりやすいです。
 11番果です。 7月25日に交配していますがまだこんなに小さいです。
11番果です。 7月25日に交配していますがまだこんなに小さいです。
 これが最後の12番果です。 これも7月25日ですがもっと小さいです。
これが最後の12番果です。 これも7月25日ですがもっと小さいです。
大丈夫でしょうか。

2015年 8月7日



なんとか終息したようです。
3号機で猛威をふるったトマトサビダニが2週間もの攻防の末、 ようやく終息を迎えました。
サビダニ発生前 7月21日と比較するとそのすざましさが判ります。
4種類の自然成分殺虫剤を順番に使用したので どれが効いたのかはっきりはしませんが、 今回初めて使用した「イオウフロアブル」が効いたような気がします。
3号機で猛威をふるったトマトサビダニが2週間もの攻防の末、 ようやく終息を迎えました。
サビダニ発生前 7月21日と比較するとそのすざましさが判ります。
4種類の自然成分殺虫剤を順番に使用したので どれが効いたのかはっきりはしませんが、 今回初めて使用した「イオウフロアブル」が効いたような気がします。
 生長点からはどんどん若葉が出てきています。
生長点からはどんどん若葉が出てきています。
 根っこも白い健康な根が外側を取り囲んでいます。
根っこも白い健康な根が外側を取り囲んでいます。
 今後の害虫による被害を未然に防ぐためにニームオイルを散布しました。
今後の害虫による被害を未然に防ぐためにニームオイルを散布しました。これもニームの木からとれる自然成分で害虫が寄り付かないそうです。
果たして救世主となれるでしょうか。

一方、2号機で栽培中のアニバーサリーメロンですがすごぶる順調です。
脇芽カキの頻度も3日に1回くらいに落ちてきました。
こちらは局所的にうどん粉病が出たり、ハモグリバエが出たりしています。
トマトサビダニ用の4種類の殺虫剤をついでにこちらにも散布してきました。
今日3号機に使ったニームオイルもついでに散布してやりました。
自然成分なので気軽に散布できます。
こちらは局所的にうどん粉病が出たり、ハモグリバエが出たりしています。
トマトサビダニ用の4種類の殺虫剤をついでにこちらにも散布してきました。
今日3号機に使ったニームオイルもついでに散布してやりました。
自然成分なので気軽に散布できます。
 1番果です。 だいぶネットが密になってきました。
1番果です。 だいぶネットが密になってきました。
 2番果です。 1番果を追い越して11.5cmあります。
2番果です。 1番果を追い越して11.5cmあります。
 3番果です。 撮影のたびに転がして位置を変えてやります。
3番果です。 撮影のたびに転がして位置を変えてやります。
 4番果です。 この玉は裏返すと割れ目が粗くなっています。
4番果です。 この玉は裏返すと割れ目が粗くなっています。
 5番果です。 この玉は裏返すと白くなっています。
5番果です。 この玉は裏返すと白くなっています。
 6番果です。 この玉も裏返すと白っぽくなっています。
6番果です。 この玉も裏返すと白っぽくなっています。
 7番果です。こちらは西洋ナシのような形をしています。
7番果です。こちらは西洋ナシのような形をしています。
 8番果。 こちらはきれいな球の形です。 ネットはまだ出ていません。
8番果。 こちらはきれいな球の形です。 ネットはまだ出ていません。
 9番果です。 玉子のような形です。
割り箸にはぷくぷくで跳ね上がる養液が染み込んでいます。
9番果です。 玉子のような形です。
割り箸にはぷくぷくで跳ね上がる養液が染み込んでいます。
 10番果です。 玉が小さいときには形がいびつになりやすいです。
10番果です。 玉が小さいときには形がいびつになりやすいです。
 11番果です。 7月25日に交配していますがまだこんなに小さいです。
11番果です。 7月25日に交配していますがまだこんなに小さいです。
 これが最後の12番果です。 これも7月25日ですがもっと小さいです。
これが最後の12番果です。 これも7月25日ですがもっと小さいです。
大丈夫でしょうか。

■
2015年 8月17日




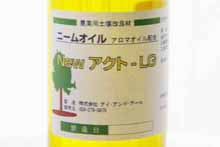 これがそのニームオイルです。
これがそのニームオイルです。
ニームオイル自体にはニンニク臭があるためレモングラスをブレンドして レモンの香りにしてあります。
 下段の左端の2株はずっとこのままで変化がありません。
なんとか若葉が出てくれるといいんですが...
下段の左端の2株はずっとこのままで変化がありません。
なんとか若葉が出てくれるといいんですが...
 それ以外の10株は若葉がでてきて息を吹き返しています。
それ以外の10株は若葉がでてきて息を吹き返しています。
結局4株が枯れて栽培穴が空き家になっています。
 これがその生長点です。 先端には蕾が幾つか見えています。
これがその生長点です。 先端には蕾が幾つか見えています。
 11日の収穫です。 久々の収穫で75gですがうれしい収穫です。
11日の収穫です。 久々の収穫で75gですがうれしい収穫です。
 昨日の収穫です。 少し増えて131gあります。
昨日の収穫です。 少し増えて131gあります。

2015年 8月17日



残暑対策です。
一時の連日連夜の猛暑日熱帯夜は一段落したもののまだまだ猛暑日が度々ある 関東平野です。 遅ればせながら1週間前から猛暑日対策として日光50%カットシートを かけてやっています。
トマトの原産地はアンデス高原で、日本の湿度の高い猛暑日とは真逆の環境です。 7月末から8月にかけての連続猛暑日にサビダニが猛威をふるったのは 暑さでミニトマトの体力が落ちていたのが原因だと思います。
一時の連日連夜の猛暑日熱帯夜は一段落したもののまだまだ猛暑日が度々ある 関東平野です。 遅ればせながら1週間前から猛暑日対策として日光50%カットシートを かけてやっています。
トマトの原産地はアンデス高原で、日本の湿度の高い猛暑日とは真逆の環境です。 7月末から8月にかけての連続猛暑日にサビダニが猛威をふるったのは 暑さでミニトマトの体力が落ちていたのが原因だと思います。

もっと早く猛暑対策をするべきでした。
この日光50%カットシートを小屋裏から降ろしてかけてやるだけだったのに。
直射日光が当たらなくなったら このようにシートをまくり上げて風通しを良くしてやります。
うちのベランダは真南から少し東を向いていますので、 ベランダ奥に置いてある3号機は午後には日陰になります。
その後、害虫が嫌う環境をつくるために定期的にニームオイルを散布してます。
直射日光が当たらなくなったら このようにシートをまくり上げて風通しを良くしてやります。
うちのベランダは真南から少し東を向いていますので、 ベランダ奥に置いてある3号機は午後には日陰になります。
その後、害虫が嫌う環境をつくるために定期的にニームオイルを散布してます。
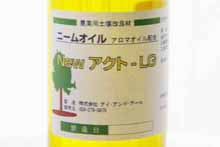 これがそのニームオイルです。
これがそのニームオイルです。ニームオイル自体にはニンニク臭があるためレモングラスをブレンドして レモンの香りにしてあります。
 下段の左端の2株はずっとこのままで変化がありません。
なんとか若葉が出てくれるといいんですが...
下段の左端の2株はずっとこのままで変化がありません。
なんとか若葉が出てくれるといいんですが...
 それ以外の10株は若葉がでてきて息を吹き返しています。
それ以外の10株は若葉がでてきて息を吹き返しています。結局4株が枯れて栽培穴が空き家になっています。
 これがその生長点です。 先端には蕾が幾つか見えています。
これがその生長点です。 先端には蕾が幾つか見えています。
 11日の収穫です。 久々の収穫で75gですがうれしい収穫です。
11日の収穫です。 久々の収穫で75gですがうれしい収穫です。
 昨日の収穫です。 少し増えて131gあります。
昨日の収穫です。 少し増えて131gあります。

■
2015年 8月20日





 1番果のその後です。
1番果のその後です。
直径が12cmくらいになっています。
他と比べて緑が濃いです。
 2番果です。
2番果です。
1番果を追い抜いて12cm超え。 特に左右の幅が増えています。
 3番果です。
3番果です。
これも1番果より生長が早いです。
 4番果です。
4番果です。
これも1番果を追い抜きました。 粗かったネットも密になってきました。
 5番果です。
5番果です。
これは生長がゆっくりです。
 6番果です。
6番果です。
これは一気に10cmを超えてきました。 ネットがまだ全面に広がっていないのに大きいです。
 7番果です。
7番果です。
これも生長が早いです。 一気にネットが張り直径もでかくなりました。
 ついにアオムシが出ちゃいました。 これが一番でかいやつです。
他に5匹の小さいやつを補殺しました。
ついにアオムシが出ちゃいました。 これが一番でかいやつです。
他に5匹の小さいやつを補殺しました。
 見つけられなかったアオムシもいるはずなので殺虫剤を散布します。
見つけられなかったアオムシもいるはずなので殺虫剤を散布します。
除虫菊を主成分とした天然成分殺虫剤、パイベニカVスプレーです。

2015年 8月20日



こちらは猛暑もヘッチャラです。
2号機で栽培中のアニバーサリーメロン6株です。 背面から見るとハンドボールくらいのメロンがゴロゴロ転がっています。
メロンの歴史は古く原産地は紀元前2000年のインドですが、 その後ヨーロッパで幾世紀にもわたって品種改良されて甘いメロンになったそうです。 そのためウリ科では珍しく高温多湿は苦手だそうですが、 うちのベランダでは2週間の連続猛暑も乗り越え元気に育っています。
2号機で栽培中のアニバーサリーメロン6株です。 背面から見るとハンドボールくらいのメロンがゴロゴロ転がっています。
メロンの歴史は古く原産地は紀元前2000年のインドですが、 その後ヨーロッパで幾世紀にもわたって品種改良されて甘いメロンになったそうです。 そのためウリ科では珍しく高温多湿は苦手だそうですが、 うちのベランダでは2週間の連続猛暑も乗り越え元気に育っています。

前面から見ると大きな葉が生い茂ってメロンの果実は見えません。
昼も夜もこのように温室ハッチをフルオープンにして風通しを良くしています。
メロンの生産量は夕張など涼しい北海道が1位かと思いきや、 茨城県がダントツの1位です。 埼玉県でも十分やっていけそうです。
3号機のミニトマトはまだ本調子ではないので水の補給もたまにですが、 2号機のメロンは3日で20リットルの補給が必要です。
肥料も週1くらいで補給します。
メロンの生産量は夕張など涼しい北海道が1位かと思いきや、 茨城県がダントツの1位です。 埼玉県でも十分やっていけそうです。
3号機のミニトマトはまだ本調子ではないので水の補給もたまにですが、 2号機のメロンは3日で20リットルの補給が必要です。
肥料も週1くらいで補給します。

連続猛暑日が終わってからはゲリラ雷雨が降ることが多くなりました。
川越市から大雨洪水注意報と竜巻注意報、ひょう注意報が発令されます。
その時は写真のように温室ハッチを少し隙間を開けて閉じてやり、
ひょうが降っても大丈夫なようにポリカーボ製の波板でできた雪崩ガードを
載せてやります。 竜巻が来たら吹き飛んでしまいますが
家の屋根も飛んでしまうくらいなので諦めるしかありません。
今のところ、お陰様で土砂降りの雨だけで済んでいます。
今のところ、お陰様で土砂降りの雨だけで済んでいます。
 1番果のその後です。
1番果のその後です。直径が12cmくらいになっています。
他と比べて緑が濃いです。
 2番果です。
2番果です。1番果を追い抜いて12cm超え。 特に左右の幅が増えています。
 3番果です。
3番果です。これも1番果より生長が早いです。
 4番果です。
4番果です。これも1番果を追い抜きました。 粗かったネットも密になってきました。
 5番果です。
5番果です。これは生長がゆっくりです。
 6番果です。
6番果です。これは一気に10cmを超えてきました。 ネットがまだ全面に広がっていないのに大きいです。
 7番果です。
7番果です。これも生長が早いです。 一気にネットが張り直径もでかくなりました。
 ついにアオムシが出ちゃいました。 これが一番でかいやつです。
他に5匹の小さいやつを補殺しました。
ついにアオムシが出ちゃいました。 これが一番でかいやつです。
他に5匹の小さいやつを補殺しました。
 見つけられなかったアオムシもいるはずなので殺虫剤を散布します。
見つけられなかったアオムシもいるはずなので殺虫剤を散布します。
除虫菊を主成分とした天然成分殺虫剤、パイベニカVスプレーです。

■
2015年 8月25日




 1番果です。
1番果です。
この様に地の緑が濃いです。
交配から50日経過しましたが、 まだ生長しているのでもう少し収穫を延ばします。
 2番果です。
2番果です。
5日前と比べてだいぶ地の緑が濃くなってきました。 直径は14cmに迫る勢いです。 これは交配から45日経過しています。
 一方、こちらは3号機で復活したミニトマト「レジナ」の収穫です。
一方、こちらは3号機で復活したミニトマト「レジナ」の収穫です。
いい色の完熟トマト119gを収穫しました。


2015年 8月25日



果実遮光やってみました。
アニバーサリーメロンの育て方ガイドには 「ソフトボール大になったら新聞紙で包んで遮光する」とあります。 ネットで調べると外観を日焼けから守り 糖度を1度くらい上げる効果があるそうです。
糖度が上がるのであればということで、 キッチンペーパーを使って包んでみました。 椅子の上に置いてあるのが台所から持ってきたキッチンペーパー。 1枚がメロンを包むのに丁度いい大きさです。
アニバーサリーメロンの育て方ガイドには 「ソフトボール大になったら新聞紙で包んで遮光する」とあります。 ネットで調べると外観を日焼けから守り 糖度を1度くらい上げる効果があるそうです。
糖度が上がるのであればということで、 キッチンペーパーを使って包んでみました。 椅子の上に置いてあるのが台所から持ってきたキッチンペーパー。 1枚がメロンを包むのに丁度いい大きさです。

背面から見るとこんな感じ。
キッチンペーパーは両手でメロンの玉に押し付けてやると、玉の形になじみます。 色も白いので反射効果があり見た目もきれいです。 なんかメロン専業農家みたいです。
もうハンドボールくらいになっているのでちょっと遅すぎですが、 5番果以降狙いです。
ネットでは葉で日陰をつくってやっても良いとあります。
結構、葉の下に隠れていたと思うんですが...
キッチンペーパーは両手でメロンの玉に押し付けてやると、玉の形になじみます。 色も白いので反射効果があり見た目もきれいです。 なんかメロン専業農家みたいです。
もうハンドボールくらいになっているのでちょっと遅すぎですが、 5番果以降狙いです。
ネットでは葉で日陰をつくってやっても良いとあります。
結構、葉の下に隠れていたと思うんですが...
アニバーサリーメロンは日焼けすると緑が濃くなってくるようです。
下の写真のように1番果はもう濃い緑になっています。 2番果もだいぶ濃くなってきました。
育て方ガイドにも「日焼けを抑えて白くする」とあります。 高級メロンのような薄い緑に仕上がるんだと思います。
下の写真のように1番果はもう濃い緑になっています。 2番果もだいぶ濃くなってきました。
育て方ガイドにも「日焼けを抑えて白くする」とあります。 高級メロンのような薄い緑に仕上がるんだと思います。
 1番果です。
1番果です。この様に地の緑が濃いです。
交配から50日経過しましたが、 まだ生長しているのでもう少し収穫を延ばします。
 2番果です。
2番果です。5日前と比べてだいぶ地の緑が濃くなってきました。 直径は14cmに迫る勢いです。 これは交配から45日経過しています。
 一方、こちらは3号機で復活したミニトマト「レジナ」の収穫です。
一方、こちらは3号機で復活したミニトマト「レジナ」の収穫です。いい色の完熟トマト119gを収穫しました。

同じく育て方ガイドに「交配後40日が経過したら水やりは控えましょう。」
とあるので水耕栽培の場合は水位を下げてやります。
上段のパイプで栽培中の2株は50日と40日なので、 中間水位(DFT)から最少水位(NFT)に切り替えてやりました。
2号機ではパイプ栽培槽の掃除ブタに排水口を取り付けてあるので、 栽培中でも掃除ブタを回転して水位を調節できます。
各パイプをつなぐホースには断熱材が巻き付けてあります。
上段のパイプで栽培中の2株は50日と40日なので、 中間水位(DFT)から最少水位(NFT)に切り替えてやりました。
2号機ではパイプ栽培槽の掃除ブタに排水口を取り付けてあるので、 栽培中でも掃除ブタを回転して水位を調節できます。
各パイプをつなぐホースには断熱材が巻き付けてあります。
写真では上段の掃除ブタは取手が水平近くになるまで回転してあります。
それに比べて下段の掃除ブタは今までの通りの中間水位で
取手の角度が45度くらいになっています。
なお、中段のパイプは掃除ブタが反対側に付いています。

■
2015年 8月29日



 8月17日の写真です。
8月17日の写真です。
枯れた葉をどんどん摘み取って もうひん死の状態です。
 今朝の写真です。
今朝の写真です。
ついに若葉が出てきました。 特に左の株に元気がでてきました。 奇跡の復活です。
 今朝の収穫は109gです。
今朝の収穫は109gです。
左の2株はずっと実を付けていますが全然熟しません。 でも今後に期待できそうです。




2015年 8月29日



「レジナ」復活です。
7月下旬に大発生したトマトサビダニ。 2週間に渡り猛威をふるって8月7日に終息したものの リハビリに時間がかかっています。
今朝は朝から雨ですが、 昨日の写真では葉の色艶も良く朝日を浴びて白く光っています。 ほとんどが若葉に取って代わり痛んだ葉は見えなくなっています。
前列左端の2株は葉がほとんどなくなって再起不能かと思っていましたが、 最近ついに新しい若葉が出始めました。
7月下旬に大発生したトマトサビダニ。 2週間に渡り猛威をふるって8月7日に終息したものの リハビリに時間がかかっています。
今朝は朝から雨ですが、 昨日の写真では葉の色艶も良く朝日を浴びて白く光っています。 ほとんどが若葉に取って代わり痛んだ葉は見えなくなっています。
前列左端の2株は葉がほとんどなくなって再起不能かと思っていましたが、 最近ついに新しい若葉が出始めました。
 8月17日の写真です。
8月17日の写真です。枯れた葉をどんどん摘み取って もうひん死の状態です。
 今朝の写真です。
今朝の写真です。ついに若葉が出てきました。 特に左の株に元気がでてきました。 奇跡の復活です。
 今朝の収穫は109gです。
今朝の収穫は109gです。左の2株はずっと実を付けていますが全然熟しません。 でも今後に期待できそうです。








