ペアリングの方法
愛鳥に嫁・婿を迎える場合、問題は相性です。何しろ文鳥は気が荒いので、性格の不一致によって血の雨が降る危険すらあります。そこで飼育している文鳥を鳥カゴに入れて、ペットショップに連れて行き、花嫁・花婿候補とお見合いさせる(鳥カゴを隣り合わせにしたり、同じ鳥カゴにいれて様子を見る)といった方法が、一般的に行われています。
※ 生後半年ほどで繁殖は可能とされますが、特にメスの方は1年程度待
った方が安全です。
※ はじめから、ペットショップ等でオス・メスのペアで買えば、おそら
く相性の問題は起こりませんが、そのオスとメスが近親である可能性
があるので、注意しなければいけません。
※ 動画は交尾の様子の一例。ともにダンスしつつ接近し、メスが尾羽を
振って交尾姿勢になり、オスが上に乗ります。
もし自分の文鳥が、せっかく連れてきた嫁・婿と仲良くしてくれなくても、飼い主自身が気に入った文鳥であれば、責任をもって飼い続け、次のような段階を踏みながら、長い目でペアリングにを成功させる気持ちになれるのではないかと思います。
|
【同居成功への段階的作戦】 |
| ステップ1 |
すぐには同居させない。
嫁、婿が新しい環境に慣れるまで2・3日以上同居を控えます。この時、お互いが見える位置に置くと互いを意識できて良いでしょう。なお、劣悪なペットショップなどで購入した文鳥には、病気やダニなど外部寄生虫がついている可能性もあるので、少し様子が変なら、離れたところに隔離して、1週間以上様子を見たほうが良いでしょう。 |
ステップ2
|
様子をじっくり観察する。
同居させると新参文鳥がいじめられる(まれに逆のケースあり)事がありますが、いじめられ、追い掛け回されながらも水やエサを食べられるようなら(水や餌入れを複数用意する)、そのまま同居させます。しかし、何時間も休みなくいじめられ、エサも食べられない様子であったり、いじめる側が指などを噛み千切ろうとする凶悪な行動をとる様子が見られた時は、いったん同居を中止しなければなりません。 |
ステップ3
|
優越感を逆転させる。
いじめる側の文鳥を、いじめられる側の鳥カゴに入れます。この時、もともとの2つの鳥カゴが離れた場所にあったほうが効果は大きく、また、あらかじめ2つの鳥カゴ内部のレイアウト(つぼ巣の位置など)を違ったものにしておくと良いでしょう。いじめる文鳥を慣れない環境でとまどわせるわけです。 |
最終手段
|
いじめる鳥の自信を喪失させる。
ここまでくると、かなり悪質な「意地悪文鳥」ですから、この際徹底的に性格の改善をはからねばなりません。成長編にあるように、段階的に風切羽を切って、自信を喪失させると良いでしょう。非常に悪質な文鳥には、ほとんどの風切り羽を切ってペンギン化します。この強硬処置によって、まずおとなしくなりますが、これはあくまでも最終手段と考えてください。 |
繁殖のためのエサ
九月になると繁殖の準備をはじめます。いつもの配合飼料とは別に、半月型などの容器に粟玉を入れ(ひんぱんに新しいものに取りかえる)、小松菜など青菜も頻繁に与えましょう(出来れば毎日)。
※ 日本での文鳥の一般的な繁殖期は、だいたい9〜5月(換羽が始まる
まで)で、この間であれば、いつでも繁殖をはじめます。
※ 粟玉はムキアワに玉子をまぶしたもので、特に繁殖期の文鳥は喜んで食べます。
万一見向きもしないようなら、その粟玉には十分に玉子が添加されていない可能
性があります。そういった場合は、他の製品に買い換えましょう。
 営巣場所を作る 営巣場所を作る
文鳥の繁殖には皿巣は不向きで、大きめのつぼ巣か文鳥用の箱巣が使われます。それぞれの長所と短所を踏まえて、どちらかを選びましょう。
つぼ巣の利点と難点
【利点】
・売っているところも多く容易に手に入ります。
・比較的小さいので、場所も取りません。
・普段は使用していない場合も、短期間で慣れます。
・外の様子をうかがうことが出来るので、手乗り文鳥では、安心して卵を温める
のに効果的とされています。
【難点】
・開口部からの、卵やヒナの取出しといった飼い主側の作業が困難です。
・ヒナが複数で成長してくると、巣から落ちてしまうことが多いです。
箱巣の利点と難点
【利点】
・上部がフタとなっているので、卵卵やヒナの取出しといった飼い主側の作業は
容易となります。
・文鳥自身の巣作りの余地が大きいため、オスに繁殖への自覚を促す効果が期待
できます。
【難点】
・売っているお店が少ないので、入手が困難かもしれません。
・見慣れない物のため、文鳥も警戒してなかなか中に入らないことがあります。
我が家では、卵の入れ替え作業等を容易にするため、箱巣を用いています
(つぼ巣使用の場合は、普段の飼育【成鳥編】と同じように設置してください)。
 ◎◎箱巣の設置方法◎◎ ◎◎箱巣の設置方法◎◎
巣材を用意する
発情したオスが中心となって、必死に巣作りをします。何でも利用しようとしますが、糸や輪ゴムなどは、脚などに引っかかり事故の原因になりますから、あらかじめ、飼い主が巣材を用意しておくべきです。
『巣草』として市販されているヤシの実の外繊維を、適当にほぐして、カゴに差し込み、後は文鳥の自主性に任せておきましょう。特にオスが懸命に巣作りする様子は、いささか滑稽ながら感動的なものです。
※ 市販されている『巣草』は長すぎる(30cmくらい)として、半分に切る人もいる
ようですが、文鳥自身は長い方を好みます。わずらわしそうに見えても、自分た
ちできれいに巣の形に整えるので心配はいりません(切ると断面が尖ってかえっ
て危険な気もします〉。 ≪資料映像≫ → 我が家の文鳥の作った巣
畳の材料のい草(水でふやかしほぐして乾燥したもの)や、ウサギなどのエサにもなる長い牧草(チモシー)なども巣材となります。手近なものでは、新聞紙を細長く手でちぎったもの(ハサミで切ると切り口が鋭角で危険)も喜びますが、紙は水分を吸ってしまい汚れやすいので、そればかりではない方が良いでしょう。また、やわらかい糸状のものも、脚にからまってしまうことがあるので、避けた方が良いでしょう。
卵を産んだら
メスがいつ卵を産んだかは、判断しにくいですが、羽をたれてくたびれた様子で、クチバシの色が薄いか青ざめて見えるのは、卵を産んだ時の外見的特徴といえます。
一日1個ずつ、4〜6個を産み、3・4個産んだ時点で温め始め(抱卵、誕生日をそろえるために本能的にこのようにします)、抱卵16、17日後に孵ります。この間、飼い主がいつまでものぞき見するようだと、親鳥は落ち着けず、抱卵をやめてしまうことがあります。なるべく無関心に、静かに見守ることを心掛けましょう。
産卵期間中はカルシウム不足とならないよう、特にボレー粉を切らさないように十分与え、アワ玉も小松菜も与えつづけ、十分に栄養をつけさせましょう。
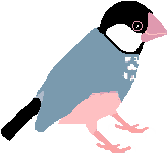 ※ メスはカルシウムが不足すると、軟卵などの異常な卵となり、お腹に卵が詰まって出てこなくなる事態が起きやすくなります。 ※ メスはカルシウムが不足すると、軟卵などの異常な卵となり、お腹に卵が詰まって出てこなくなる事態が起きやすくなります。
ボレー粉を食べないメスには、他にカルシウム分が取れるものを用意したり、場合によっては(私は安易な薬やサプリメントの常用には反対〉、この時期だけでも飲水に市販のカルシウム剤などを混ぜる事を考えた方が良いでしょう。
◎◎卵づまりの恐怖◎◎
【例】我が家のカルシウム対策
 |
←カトルボーン お薦め
 イカの甲を乾燥させた飼料です。 イカの甲を乾燥させた飼料です。
90%程度がカルシウムで出来ており、さらに自然の海産物なので、その他ミネラルも豊富ではないかと考えています。
そのままの形では、我が家の文鳥は食べないので、砕いた物を放鳥時に与えています。もろいので、少しトンカチでたたくだけで右のような状態になります
。 |
 |
←『バードカルシウム』
ハイペットという会社のペレット状の製品です。成分は不明ですが、「貝殻粉砕パウダー」やビール酵母などを原料としています。
産卵期間中に小さな容器に入れて、カゴの中に設置しています。
|
 |
←『ネクトン-MSA』
ネクトンというドイツの会社の栄養補助剤です。骨の形成に必要なミネラルとビタミンD3が含まれています。
少し産卵に問題が起りそうな時などに、飲み水に混ぜたり、配合飼料にまぶしたりして与えています。ミルクパウダーのような粉末です。 |
|
◎◎プロ的な技術(托卵・検卵)について◎◎
粟玉・水浴びの規制について
卵を産み終えたら(産卵開始から1週間後が目安)、発情を抑制するため粟玉は与えるのをやめます(青菜は普段どおり)。
抱卵中も育雛中も水浴びを規制する必要はありません。特に、ヒナが孵った後は、ぬれた体でヒナを冷やしてしまわないように中止するように説明する飼育書もありますが、ビショビショのままで巣に戻っていくような悪趣味な鳥はあまりいないので、親鳥の息抜きを取り上げる必要はないでしょう。
卵が孵ったら
普通は、抱卵開始から16日程度で孵化し、巣箱から「シイ・シイ」とか細い鳴き声が聞こえてきます。卵の殻を、親鳥が巣の外に捨て、それで孵化に気づくこともあります。気づいたら再び粟玉も与え、青菜やボレー粉も十分に与えましょう。
なお、抱卵から3週間(初卵産卵から約4週間)経過して孵らない卵は、無精卵(受精していなかった卵)か中止卵(成長が途中で止まってしまった卵)ですので、取り除きましょう。
| 産卵から孵化までのモデルケース |
|
1日目 |
産卵を始める |
卵1個 |
これ以降、順調にいけば毎日1個ずつ産卵していきます。
※冬の朝は冷え込みに注意です。 |
|
4日目 |
抱卵を始める |
卵4個 |
孵化の日にちをそろえるために、産み貯めてから温めます。
※まだ産卵が続く場合が多いです。 |
|
6日目 |
産卵終了 |
卵6個 |
8個くらい産む場合も、一日おきの産卵となる場合もあります。
※あまりのぞき見しないようにしましょう。 |
|
20日目 |
4羽誕生 |
卵2個 |
4個の卵はともに抱卵16日目なので、孵化はほぼ同日になります。
※親鳥を刺激しないように十分気をつけましょう。 |
|
21日目 |
5羽目誕生 |
卵1個 |
抱卵開始後に産卵した卵も、抱卵16日目で孵化します。 |
|
22日目 |
6羽目誕生 |
卵なし |
抱卵開始後に産卵した卵も、抱卵16日目で孵化します。 |
生まれたヒナを手乗りにする場合は、孵化2週間(14日)前後経過してから取り出します。その際、汚れているでしょうから、つぼ巣は取り替え箱巣も中を清掃して、次の産卵に備えましょう(ヒナの飼育については【ヒナ編】を参照ください)。
◎◎ヒナの成長度のめやす◎◎
孵化後も頻繁にのぞき見すると、親鳥が育児を放棄してしまう恐れがあるので、出来る限り静かに見守るのが無難です。
 孵化3週間くらいになると人間を恐れるようになり、手乗りにするのは難しくなります(不可能ではありませんが、慣れるまで、嫌がるヒナの口に無理矢理エサを入れる「強制給餌」をおこなう必要があります)。これは目が開いてくるに従い親を認識し、それ以外を拒絶する動物の本能的な反応が生じるためです。 孵化3週間くらいになると人間を恐れるようになり、手乗りにするのは難しくなります(不可能ではありませんが、慣れるまで、嫌がるヒナの口に無理矢理エサを入れる「強制給餌」をおこなう必要があります)。これは目が開いてくるに従い親を認識し、それ以外を拒絶する動物の本能的な反応が生じるためです。
文鳥は性格差が大きな小鳥なので、孵化1ヶ月ほど親鳥に育てられた後でも、あまり警戒心を持たず人間に順応するものもいれば、徹底的に拒絶するものもいます。警戒心の強い文鳥を無理に手なずけるのは、飼い主である人間にも文鳥自身にも、格別なストレスとなってしまうので、手乗りにするのであれば、物心つく以前に人間が親になりかわった方が「自然」と言えます。
参考−産卵の是非−
当然ながら、産卵は文鳥、特にメスにとって非常な負担となります。特に寒い時期は卵づまりなどの事態が起きやすく、落鳥(死んでしまう)危険もあり、出来れば必要以上の産卵は避けるべきだと思います。第一、無事に産卵し孵化しても、育児は親鳥にさらに負担となるわけですし、飼い主の人間もたくさん生まれると飼育に難渋します。
繁殖期間に産卵させないためには、『発情を抑制する』、『営巣場所を与えない』、ことが必要となります。つまり、粟玉などの栄養価の高いものを与えず、つぼ巣、箱巣も設置しないことが、最低必要となるわけです。
しかし、本来なら一年でもっとも栄養が必要な寒い時期に、寝床も与えず粗食というのも不自然であまり感心できません。鳥カゴが冷え込む場所にある場合は、気をつけないと生命の危険すら伴う行為ともなりかねません。
また、卵を産ませなかった鳥を途中から繁殖に用いると、かえって卵づまりを引き起こす危険が増大する傾向もあるようですし、そもそも夫婦で飼う以上は、絶対的に産卵を避けるのは無理かもしれません。
そこで今のところ我が家では、産むだけ産ませて、すべて擬卵(ギラン、偽物の卵)に替える方法をとっています。これなら親鳥は孵らぬ卵を三週間くらい温めつづけるので、その間の産卵は抑制出来(卵を取り上げるだけだと、すぐにまた産んでしまうので厳禁)、メスの体を休めることにもなると思います。三週間ほどして親鳥が抱卵をやめると粟玉などを与え、次の産卵に備えます。繁殖期間中これを数回繰り返すわけです。
この方法では、良心がとがめるという人もいるかもしれませんが(卵をつぶし、親鳥をだます)、飼い主の責任上、仕方がありません。
補足−独身手乗りメスの産卵−
手乗り文鳥の場合、オスと同居しなくとも産卵してしまう事があります。手の中で眠らせたり背中をなでると交尾と勘違いして、いわば想像妊娠してしまうのです。
これを避けるには、やはり栄養価の高いものは与えず、つぼ巣なども撤去し、スキンシップを控える必要があり、さらには室内で遊ぶ際に巣と見なせそうな場所を設けない(カーテンのたるみや洗濯物などなど)といった細心の注意が必要となるようです。
確かに無精卵で産卵障害の危険を犯すのは意味がなく、避けたいところです。しかし、上記の処置は100%の防止策ではないので、せっかく対処法をしても、産卵してしまうこともありえます。そうなってしまっては、栄養不足状態での産卵ですから、さらに危険度を増してしまう結果になりかねません。
従って、反対に産卵してしまうことを前提として、粟玉やボレー粉、場合によっては補助食品などで栄養が不足しないように留意して産卵障害の可能性を減らし、また産卵そのものをやめさせるのではなく、産卵回数を減らす努力をした方が、スキンシップなどもそのまま継続できて良い、との判断も成り立ちます。
つまり、問題はそれほど単純ではないのです。それぞれの飼い主の判断で、方法を選ぶ必要があります。今後、より良い第三の方法が見つかって欲しいものです。
|
戻る 表紙へ
|