文鳥飼育に必要なもの
文鳥を飼育するのに、特別な変わった機材は必要ではありませんが、鳥カゴなど必要なものもあります。我が家の様子を例に見てみましょう。(値段は参考までの目安)
| 品物 |
値段 |
用途 |
| 鳥カゴ① |
3000 |
文鳥の住居 |
| 止まり木 |
付属 |
― |
| エサ入れ② |
200 |
― |
| 水入れ③ |
100 |
― |
|
水浴び容器④ |
500 |
― |
| 小型エサ入れ⑤ |
50 |
副食用容器 |
| 菜さし⑥ |
50 |
小松菜用容器 |
| ブランコ⑦ |
150 |
遊び道具 |
| つぼ巣⑧ |
300 |
文鳥の寝床 |
|
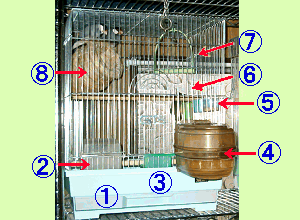 |
 鳥カゴは掃除が楽な底が引き出し式の中型(幅・奥行き約30~40cm、高さ約40~45cm)が一般的です。 鳥カゴは掃除が楽な底が引き出し式の中型(幅・奥行き約30~40cm、高さ約40~45cm)が一般的です。
写真はGB社の鳥カゴで、幅36.5㎝、奥行き29.7㎝、高さ44.5㎝です。これでペア飼育し繁殖させていますが、箱巣を設置すると少々せまい感じです。
◎◎市販鳥カゴの具体例◎◎
食べ散らかす文鳥が多いので、カバー付のものを付属品とは別に用意しています。
文鳥は水あびが大好きなので、水浴用の器(写真は『アウターバードバス』)を付属品とは別に用意しています。水の飛散りをある程度防いでくれます。
カゴを置く場所
・屋内で風通しが良く、少しは陽があたる場所。
※暑くなりすぎないように、日陰の部分もつくりましょう。
・人間の冷暖房具の影響がなるべく少ない場所。
※ストーブやエアコンの送風が直接あたらないようにしましょう。
・部屋の床よりも高い方が良いでしょう。
※飼い主の目線くらいに置ければ世話がしやすいと思います。
取り付けたい備品
つぼ巣
止まり木にとまったまま片脚でも文鳥は眠りますが、保温器を使わない場合、寒い時期には保温の意味でつぼ巣を入れましょう。特に1羽で飼う場合は、入れた方が良いと思います(止まり木で眠ることに運動効果は大してありません。運動不足を感じたら、つぼ巣の有無より、カゴの外で飛べる時間を作るのが肝心です)。
※ 今後繁殖の予定が無く、むしろ発情を避けたいと考え、ペットヒーターなどで防寒対策が行なえるのであれば、営巣場所となるつぼ巣の類は普段から設置しない方が良いでしょう。
市販されているワラ製のつぼ巣には、大中小の3種類がありますが、文鳥の場合、小では1羽でも少々手ぜま、中で2羽でちょうど良いくらいです。もし、文鳥には珍しいことですが、3、4羽で仲良く生活するようなら、つぼ巣よりも開口部の広い横巣と呼ばれるものを使用した方が良いでしょう。大は、繁殖の時に用いると良いです。
◎◎設置方法と管理◎◎
ブランコ
遊戯用ですので、絶対に必要なものではありませんが、活発な文鳥の様子を観察するには最も適した小道具です。また足を踏ん張るので運動にもなります。
ハシゴ状の遊戯用具は、習性の異なる(樹上での移動が得意)インコ向きのものなので、文鳥には避けたほうが良いでしょう。
※
文鳥とセキセイインコの違いについて興味のある方は『文鳥問題』をご参照下さい。
◎ 毎日の世話
エサと水を取り替えるだけなので簡単です。忘れないように、毎日決まった時間に取り替え、習慣にしてしまいましょう。
(我が家では、朝7:30までにエサを取り替え、夜8:30に水を取り替えています)
毎日少し残す程度の決まった量(環境や個体差によりますが、およそ1羽につき最大8gくらい)食べ残しのエサは、もったいないですが捨ててしまいます。
(我が家では、洗剤の計量器で7分目程度で2羽、と目分量で取り替えています)
→
定量・定時にエサを取り替えることによって、エサの残量を文鳥の健康管理の目安とすることができます。食べ残しを捨てることにより、殻をエサと誤認することによる事故も防げ(文鳥は1日エサを食べないだけでも衰弱してしまいます)、また古いエサによる病気の危険も減らすことが出来ます(エサに水がかかると腐りやすくなります)。
※
飼育書などでは、エサ箱にたまった種子殻を息を吹きかけて飛ばし、減った分を足すようなことが書かれています。しかし家の中で飼育する場合、盛大に殻を吹き飛ばす場所がまずありません。
また、大量にエサがある場合、文鳥は特定の穀物(配合飼料の中のカナリアシード)を選り分けて食べることが多く、偏食の原因ともなってしまいます。
日光浴について
毎日30分以内直射日光に当てることが、飼育書などでは推奨されています。しかし、①
飼い主の時間的労力的な制約(仕事を持つ人には不可能!!)
②
外に出すことによる事故の可能性(文鳥を逃がす危険、外敵に襲われる危険、夏の熱射・冬の寒風の危険など)③
オゾン層破壊による紫外線増加(=直射日光の有害性、具体的には白内障などを引き起こす)、④
野鳥との接触で病気になる可能性、といった問題もあります。
我が家の場合①②の理由で、1年中窓辺に鳥カゴを置いたままで、ガラスごしの採光しかしていません。しかし、薄ガラスのためかそれでも適当に日光浴になっているようです。元気に暮らし繁殖しています。
日光にあたることにより、体内で形成されるビタミンなども存在しますが、それは食べて摂取することも出来るので、一日中薄暗い部屋の中において置くのでもなければ、気にしすぎることもないのかもしれません。
|
主食について
文鳥やインコ類のエサとして、アワやヒエなど数種類の穀類が配合されたもの(配合飼料)が安く市販されており、文鳥はこれだけでもとりあえず普通に生活することが出来ます。
その配合飼料は、外穀の有無によって「殻付き」と「殻むき」(ムキエサ)に大別され、それぞれの長所と短所があります。
・ムキエサ
 |
長所 食べた後に、文鳥がクチバシでむいたエサの殻
が出ないので掃除が楽です。
短所 腐りやすく穀むきの際に種子のヌカ部分を失う
ことがあり、ビタミンB類などの栄養面で不足
が生じる可能性があります。
また、ムキエサばかり食べていると殻をむく必
要がなくなり、クチバシをあまり使わなくなる
ため、健康に良くないとも考えられています。
ちょうど柔らかいものばかり食べる人間のアゴが
弱くなるのと同じです。 |
・殻付エサ
 |
長所 長持ちします。鮮度が保たれ栄養分もほとんど
損なわれません。
文鳥は語りませんが、ムキエサよりうまいようです。
短所 食べた後、殻が散乱してしまいがちです。エサ
箱に残った殻を飼い主がエサと誤認して、エサ
を替えなかったために文鳥を餓死させてしまう
事故の元になります。
さらに、いちいち殻をむかないとエサが食べら
れないのは、文鳥も苦痛な時がありそうです。
うまくても、朝・昼・晩カニばかりでは、
人間でも殻をむくのはつらいかもしれません。 |
→
文鳥中心に考えれば、噛む力の衰えた老鳥などでない限り、殻付きエサを使用すべきでしょう。人間側の都合でムキエサを用いる場合は、栄養補助剤などの併用を考えたほうが良いと思われます。
我が家の主食
・使用するもの 一般的で安価な配合ムキエサ(800g300円ほど)
文鳥専用の殻付配合飼料(『カスタムラックス文鳥用』830g450円ほど)
(理由)
一般に市販されている配合エサは、文鳥以外も対象としているので、文鳥だけがよく食べる米(青米)が配合されていませんが、この文鳥専用の配合エサにはモミも含まれています。割高ですが見た目もつやつやしていてうまそうなので、使用していました(現在は通販のエサを使用)。
(配合)
この2つを混ぜ、さらに季節によっては殻付カナリアシード(スーパーなどでも200g150円ほどで小売りされている)を少々(30gほど)混ぜる。
※
カナリアシードは文鳥の好物ですが、与えすぎると太ると信じられてきま
した。しかし、実際には、それほど高脂肪な食べ物ではないので、大量に
与えなければ問題とはなりません。
|
※ 最近使用する人もいるペレットや食べ物については、
『文鳥問題』で考察しているので、興味のある方はご参照下さい。
副食のいろいろ
| 品目 |
値段 |
内容 |
おもな効用 |
与え方 |
| ボレー粉 |
100 |
カキ殻を砕いたもの |
カルシウムの補給 |
小型エサ入れで常時 |
| 小松菜 |
時価 |
文鳥が最も好きな野菜 |
体調の保持に効果あり |
菜さしに入れ週1・2回以上 |
| 塩土 |
100 |
塩分の入った鉱物飼料 |
消化活動を円滑にする |
小型エサ入れで随時 |
| その他 |
|
各種さまざま |
主に飼い主の自己満足 |
与え過ぎない程度に |
ボレー粉は週に1度くらいで取り替えてください。
繁殖期や成長途上の若鳥には、粟玉(卵黄をまぶしたアワ)も別に与えましょう。
◎◎野菜と塩土について◎◎
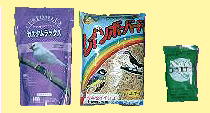
|
 |
※鳥が小松菜を引っ張り出さないように、小松菜をさした後菜さしに隙間があれば、余った茎やニンジンなどを詰め込みます。
青菜としては、他のHPお薦めのものとしてチンゲン菜やグリーンピースの苗である『豆苗』があります。我が家の文鳥も喜んで食べました。小松菜を1束買うと余ってしまうならこちらをメインの青菜にしても良いでしょう。特に『豆苗』は水につけ日に当てるとかなり再生するので、カゴの横に置くと手間いらずで重宝すると思います。
豆苗の自家栽培については→『文鳥屋』 |
◎◎我が家の文鳥が食べているもの◎◎
水浴びについて
 文鳥にとって水浴びは健康維持に不可欠で、文鳥たちも普通は大好きですから、体が入り、深さが5cm以下の容器を、水浴び用に常設しましょう。もちろん水は毎日取り替えます。 文鳥にとって水浴びは健康維持に不可欠で、文鳥たちも普通は大好きですから、体が入り、深さが5cm以下の容器を、水浴び用に常設しましょう。もちろん水は毎日取り替えます。
(我が家では、水浴び容器は一日中入れたままです。それぞれの文鳥が好きな時間に好きなだけ水浴びをしています。)
環境になれず、なかなか水浴びをしない場合は、1週間に1回程度鳥カゴの上から、ジョウロなどで水をかけてやっても良いでしょう。
ただし、霧吹きを使用すると、羽毛の中に水がしみこみ風邪を引いてしまうので、避けた方が良いでしょう。
 ※ 文鳥の羽毛の油分が取れてしまうので、お湯による水浴びは厳禁です。寒いからといって、人肌(37℃)以上のお湯で水浴びをさせると、かえって風邪をひいてしまうのです。 ※ 文鳥の羽毛の油分が取れてしまうので、お湯による水浴びは厳禁です。寒いからといって、人肌(37℃)以上のお湯で水浴びをさせると、かえって風邪をひいてしまうのです。
右図のような、
尾羽の付け根にあるイボ状の突起(尾脂腺)は、
毛繕いのための油脂分が出てくる大切な器官です。
異常ではないので触らないようにしましょう!
放鳥について
人間に餌付けされるなどして「手乗り」となった文鳥は、カゴの外に出して飼い主のそばで遊ばせる(これを放鳥と呼ぶ)必要があります。
放鳥の注意点
・1時間程度、なるべく毎日決まった時間帯に放すと良いでしょう。
→
長時間放鳥を続けると飼い主の注意もおろそかになりがちです。
放鳥の時間が不規則では、文鳥はいつも外に出たがり落ち着きがなくなります。
・窓や扉が閉まっているのを確認して放しましょう。
→
よく慣れた文鳥でも、窓が開いていれば飛び出してしまいます。昼間外に飛んで
いった文鳥を捕まえるのは至難です。
一方、文鳥は暗闇を行動出来ないので、夜間に放鳥した方が安全な面があります。
・部屋の中で遊んでいる文鳥から出来るだけ目を離さないようにしましょう。
→
飼い主の気づかぬうちに足元にいたり、飼い主の飲んでいるお茶などに首を突っ込もう
としたり、はなはだ危険です。
また、輪ゴムなどが落ちていると、遊んで首に巻きついてしまったりすることがありま
す。小さな危険物が落ちていないか気をつけましょう。
放鳥時は他の家事はやめて、文鳥の行動を観察しましょう!
放鳥タイム
 我が家では毎日夜の7時30分~9時30分くらいが放鳥時間です。本来日中に活動する文鳥が暗くなってから動き回るのは不自然として健康上の影響を指摘する声もあります。確かに早寝早起きが最高には違いありませんが、それでは朝起きて仕事に出かけ、夜となって帰宅する一般人は文鳥と遊ぶことが出来なくなることになります。 我が家では毎日夜の7時30分~9時30分くらいが放鳥時間です。本来日中に活動する文鳥が暗くなってから動き回るのは不自然として健康上の影響を指摘する声もあります。確かに早寝早起きが最高には違いありませんが、それでは朝起きて仕事に出かけ、夜となって帰宅する一般人は文鳥と遊ぶことが出来なくなることになります。
しかし、生物には寝る時間が遅ければ朝寝坊したり昼寝をして調整をする柔軟性があるので、過度の心配は無用なのです(そうでなければ人間に夜勤を強いるのは犯罪です)。ただし、毎日放鳥時間を変えたのでは、生活のリズムが保てなくなり健康に問題が起こることが大いに考えられます。その点では同じ昼行性の動物である人間と同じなのです。
昼か夜かを問題とするよりも、一定の生活リズムを保つように飼い主は注意すべきでしょう。
|
※
観葉植物には有毒なものもあり、有毒でなくとも文鳥がむしって遊ぶようだと枯れてしまうので、放鳥時は片付けた方が良いでしょう。
※ 万一逃がしてしまい、周囲を探しても見つからなければ、警察や保健所に届け、近所に張り紙をしましょう。それでも連絡の無い場合は、良い人に拾われる幸運を祈りましょう。
特に手乗り文鳥の場合は、困った時には人間に近づいていくのが普通です。実際、迷い鳥の保護をきっかけに、文鳥を飼いはじめた人も多いものです。逃がしたことへの反省は必要ですが、悲観しすぎるのも考えものです。
◎ 時々の世話
掃除
鳥カゴ底部の格子状間仕切り(フン切り)の下の引き出し部分の底に新聞紙などを敷き、時々取り替えると楽です。取り替える間隔はその時々でさまざまですが、最低でも2週間に1回くらいは取り替えましょう。
※ トレー式のカゴの場合、新聞紙などを敷かずに、毎日引き出し部分を水洗いするのも簡単な方法です。
鳥カゴ付属のフン切りは底部に落ちたフンや古いエサを文鳥に触れさせないためのものですから、頻繁に掃除が出来る場合は必要ないでしょう。
◎◎新聞の敷き方◎◎
鳥カゴの底部、特に引き出しの周りなどにたまったゴミが目立つようになったらふき取り、1年に1回くらいは丸洗いしたほうが良いでしょう。
爪が伸びたら
文鳥の爪を伸ばしたままにしておくと、つぼ巣などに引っかかって動けず、大惨事につながる可能性があります。伸びすぎて服につまづいたりするようなら、人間用の爪切りなどで切らなくてはいけません。
◎◎爪・羽の切り方図◎◎
深爪してしまったら
…
血管部まで切らなくとも、切れ味の甘くなった爪切りを使用したり、爪を横向きに切ると(人間の爪を切る時と同様、正面から刃を当てたほうが良い)、裂けて血が出ることがあります。出血が止まらない時は、火のついたお線香を傷口に一瞬あてて焼いて止血します。慣れないとあわててしまうので、深爪には十分注意しましょう
。
※ 火を当てるのは野蛮で痛そうですが、一瞬で確実で消毒にもなり、薬剤をな
める心配も無く、実はもっとも文鳥に負担の少ない方法だと思います。
羽の切り方
文鳥をカゴの外で遊ばせた時に捕まらなくなったり、危険な超高速飛行を繰り返したり、やむを得ない場合は、必要に応じて翼の羽を切り(クリッピング)、飛翔能力を落とします。具体的には風切り羽を1枚おきにハサミで切ります。
(通常、室内を真っ暗にすれば夜目の効かない文鳥は捕獲しやすくなります)
ステップ1 …外端の1枚を残し、風切り羽を左右3・4枚ずつ1枚間隔に切る(上記『切り方図』を参照)。
※
飛翔能力は少し落ちるだけですが、疲れやすくなります。
生後1年未満では、これ以上切るべきではありません。
| それでも問題があれば |
→
ステップ2
…残りの風切り羽も1枚おきに切る。
※
慣れれば室内飛行は可能ですがスピードは落ちます。 |
| まだ、問題があれば |
→
ステップ3
…先端に1枚残した風切り羽も切る。
※
高いところへの飛行が難しくなります。 |
| どうしようもなくなったら |
→
最終手段
…根元近くの2・3枚を残し、すべての
風切り羽を切ってしまう。
※
最終手段によって文鳥はペンギン化し、反抗心は押さ
えられますが、高い所から落ちて怪我しないように、
十分注意しなければいけません。 |
はえかわる羽
 文鳥は普通5~7月頃に羽が抜け替わります。これを換羽(カンウ・トヤ)といいますが、その様子は個体差があり、また同じ文鳥でも、ほとんどはえかわらない年もあれば、全身ハゲハゲになってしまう激しい年もあります。 文鳥は普通5~7月頃に羽が抜け替わります。これを換羽(カンウ・トヤ)といいますが、その様子は個体差があり、また同じ文鳥でも、ほとんどはえかわらない年もあれば、全身ハゲハゲになってしまう激しい年もあります。
激しい換羽では全身につやがなくなり、病気ではないかと驚きますが、ハゲているようでも新しい羽の芽(白いトゲのようなもの、羽鞘、筆毛)が確認できれば、問題ありません。ただし、トゲ状のものが見当たらず、羽毛がボロボロになるようだと、シラミ類に感染されたなどの可能性があるので、病院で診てもらった方が良いかもしれません(※我が家ではいまだ感染経験なし=きわめて希)。
また飼育書には換羽期の水浴びは厳禁とするものがありますが、それほど気にすることはないでしょう。ジョウロで強制的に水浴びをさせるようなことを止めるだけでよく、水浴び容器を取り上げることはないです。我が家ではそのままにして、文鳥の好きなようにさせています。
ただ、換羽は体力を消耗し、文鳥も神経質になることがあるので、無理な運動をさせるのは控え、少々の乱暴化にも理解が必要です。
→ 換羽の実例写真
|
病気とケガ
◎◎病気・外傷への対応例◎◎
何かあれば診てもらえるように、普段から信頼して小鳥を診てもらえる病院を探しておきましょう。(参照)
踏んでしまったり、落下してしまったりして、骨折が疑われるような場合は、素人判断せずに、早めに獣医さんに診てもらいましょう。
多少の出血程度のケガであれば、自然に治りますが、なかなか出血が止まらないようなら、患部に消毒液をかけるのも良いでしょう。ただし軟膏は、文鳥が気にしてなめてしまうので使用すべきではありません。
文鳥はかなり丈夫な小鳥ですが、羽を膨らまして元気がなく居眠りしていたり、クチバシが青ざめている時は、はっきりと体調不良です。変化を見逃さないように注意しましょう。
異常に気づいたら、まずは静かで暖かなところ(目安は30℃)に隔離します。この時、エサや水がとれるように真っ暗にはしてはいけませんが、だからと言って光熱灯を熱源として温めるのは、明るくなりすぎてはなはだ不適当です。保温器などを普段から用意しておきましょう。
もし、エサが食べられず、水も飲めず、病院に行くのも危険なほど衰弱しているなら、スポーツドリンク(『ポカリスエット』)を薄めずそのまま、スポイトで一滴ずつ、文鳥のクチバシの横にたらして数滴飲ませましょう(激しい呼吸器症状のある時は不可)。
これは、脱水と低血糖から回復させるための応急処置ですが、症状が軽い場合、これだけで自分でエサを食べるまで回復してくれることがあります。
※ 文鳥には、てんかん症状を起こす者がいます。息を吸い込めないような様子で、
バタバタともがくこともあり、その様子に驚かされますが、普通すぐに治まりま
す。こうした呼吸障害を起こしている時に、水分を取らせると誤嚥を起こし危険
です。かわいそうですが、ぶつかって危険なものを取り除き、見守るだけに止め
ましょう。
文鳥の寿命
メスが繁殖を卒業する6歳頃まで達した文鳥の、その後の平均余命は2~3年程度とすると、「平均寿命」は8~9歳と考えられると思います。
人間の年齢で当てはめてみると1年目だけ20歳、その後1年で8歳ずつ加算すれば目安になりそうです。
計算式(2歳以上) 文鳥年齢×8+12
1年20歳・2年28歳・3年36歳・4年44歳・5年52歳・6年60歳・7年68歳・8年76歳・9年84歳
※文鳥の最高長寿は18歳とされているので、人間では156歳となります。
より詳細な年齢換算
156歳はおかしいので、実際の生理的変化のポイント(下記)を人と比較して、より詳細に年齢換算を行い、それに基づき生年月日から換算できるようにしました。
・ポイント1…生後3ヶ月のオスのぐぜりは、男の子の声変わり的。
・ポイント2…生後7ヶ月程度でも産卵することは可能。
・ポイント3…文鳥の産卵停止は6歳、人間の閉経は50歳。
・ポイント4…文鳥の寿命は8、9歳、日本人の寿命は80~85歳。
・ポイント5…文鳥の最長寿は18歳、人間の最長寿122歳。
☆ 生後1年未満は1ヶ月につき1歳ずつ加算します【成長期】。
| 1ヶ月 |
2ヶ月 |
3ヶ月 |
4ヶ月 |
5ヶ月 |
6ヶ月 |
7ヶ月 |
8ヶ月 |
9ヶ月 |
10ヶ月 |
11ヶ月 |
|
9歳 |
10歳 |
11歳 |
12歳 |
13歳 |
14歳 |
15歳 |
16歳 |
17歳 |
18歳 |
19歳 |
☆ その後6歳まで1年につき6歳ずつ加算します【壮年期】。
| 1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
|
20歳 |
26歳 |
32歳 |
38歳 |
44歳 |
50歳 |
☆ 6歳から9歳までは1年につき12歳ずつ加算します【老化期】。
☆ 9歳以降は1年につき4歳ずつ加算します【老境期】。
| 10年 |
11年 |
12年 |
13年 |
14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
|
90歳 |
94歳 |
98歳 |
102歳 |
106歳 |
110歳 |
114歳 |
118歳 |
122歳 |
複雑ですが、加齢変化の実態に近いと思われます。
|
平均より早く死んでしまったとしても、文鳥自身の先天的な体質はもちろん、人為的に見える事故でさえも、多くの場合飼い主の責任とは言い切れません。
第一、長く生きることだけが文鳥の幸せとは言えないはずです。
愛するものの死は、さびしく悲しくつらいものですが、遅かれ早かれ避けがたいはずです。その死を見届けて受け入れることも、飼い主としての責任の一つであり、血の流れる生き物を飼育する人間に必要な覚悟だと思います。
|
戻る 表紙へ
|